 › みやざきNPO・協働支援センターのブログ › 2014年09月
› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › 2014年09月2014年09月23日
『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』第3回 プレゼン講座を開催しました!
9月21日(日)に、計4回の連続講座『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』の第3弾、プレゼン講座をみやざき県民協働支援センターにて開催いたしました!
第3回目の講師は、都城工業高等専門学校 准教授の吉井千周さん。

吉井さんは、鹿児島大学法文学部、慶應義塾大学院政策・メディア研究科修士課程、同博士課程、タイ国立チュラロンコン大学社会調査研究所客員研究員を経て、現在都城工業高等専門学校にて准教授を務められております。タイ北部でのNGO活動を皮切りに国内の複数のNPOでの実践活動にも関わっていらっしゃいます。現在は、都城地区を中心とした社会人勉強会を主催するほか、プレゼンテーションの指導を全国各地の大学で行っていらっしゃいます。
今回は自分たちの団体や活動内容を第三者に分かりやすく伝えるためのプレゼンテーションのコツをお話いただきました!

〇オバマ氏の勝利演説から学ぶ
まずは「yes we can」の言葉が印象的な、オバマ氏の勝利演説から良いプレゼンテーションを考えました。
※伝えたいメッセージを安直な言葉ではなく、ストーリーで語りイメージを売ること。
※プレゼンテーションの目的は、自分の願うとおりに、相手に動いてもらうように仕向けること。
ということに、参加者は気づくことができました。

〇マーケティングの理論に学ぶ
プレゼンテーションでは、マーケティングの考え方が大切だそうです。プレゼンテーションは聞いてくれる人がいなければ意味がありません。自分が言いたいことを言うのではなく、受け手である聴衆のことをしっかり考えましょう。受け手はどんな人物であるか想定し、どんな情報を聞きたがっているのか、シュミレーションすることが大切です。
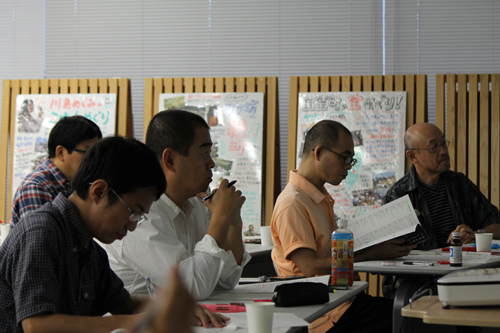

〇具体的なプレゼンの技法
プレゼンテーションではパワーポイントなどのスライドウェアを使うことが多くあります。しかしスライドウェアはプレゼンに必ず必要なものではありません。
悪い使用例やよい使用例から、効果的なスライドウェアの使い方を学びました。
(悪いスライドウェアの使用例)
・文字が多い。
・読みにくいフォント。
・重要なポイントが分からない。
・アニメーションの多様⇒重要なところをアニメーションにすると、表示される時間が短くなってしますので、大事なポイントにも関わらず見落とされる可能性があります。
(良いスライドウェアの使用例)
・文字は少なく。話せば分かることは書かない。
・数字や写真を効果的に使う。
・話題の転換に活用する。
※ポイント※
シンプルで洗練されたスライドを目指しましょう。また、写真には一目で分かるという強みがあります。普段からたくさん写真を撮って活用していきましょう。

〇まとめ〇
1.プレゼンの目的
・相手にどんな行動を起こさせたいのか
・聴衆はどんな人物なのか
2.スライドはシンプルに
・すべてではなく、伝える情報を絞る
3.いきなりスライドを作らない
・マインドマップでアイデアを書き出す
おまけ:プレゼンは時間内(早め)に切り上げる
吉井さんの講座自体が、良いプレゼンのお手本となっていました。ミュージカルのようなしゃべりに引き込まれるあっという間の3時間半でした。
参加者からは
・プレゼン力を磨くことで、「本質」、「一番大事なこと」をつかむ、たどり着く、共有することもできるはずだと実感しました。
・プレゼンって芸術だと感じました。完成度の高いモデルを見せていただきました。吉井さんの目的意識、とても参考になりました。
・人をひきつけるプレゼテーションは、思っていたよりシンプルで、簡単で良いのだと思った。情報があふれているので、伝えたい情報を絞ることの大切さに気づきました。
といったご感想をいただきました!
吉井さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
次回はいよいよ最終回、『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』プレ審査会&振り返りです。
第3回目の講師は、都城工業高等専門学校 准教授の吉井千周さん。

吉井さんは、鹿児島大学法文学部、慶應義塾大学院政策・メディア研究科修士課程、同博士課程、タイ国立チュラロンコン大学社会調査研究所客員研究員を経て、現在都城工業高等専門学校にて准教授を務められております。タイ北部でのNGO活動を皮切りに国内の複数のNPOでの実践活動にも関わっていらっしゃいます。現在は、都城地区を中心とした社会人勉強会を主催するほか、プレゼンテーションの指導を全国各地の大学で行っていらっしゃいます。
今回は自分たちの団体や活動内容を第三者に分かりやすく伝えるためのプレゼンテーションのコツをお話いただきました!

〇オバマ氏の勝利演説から学ぶ
まずは「yes we can」の言葉が印象的な、オバマ氏の勝利演説から良いプレゼンテーションを考えました。
※伝えたいメッセージを安直な言葉ではなく、ストーリーで語りイメージを売ること。
※プレゼンテーションの目的は、自分の願うとおりに、相手に動いてもらうように仕向けること。
ということに、参加者は気づくことができました。

〇マーケティングの理論に学ぶ
プレゼンテーションでは、マーケティングの考え方が大切だそうです。プレゼンテーションは聞いてくれる人がいなければ意味がありません。自分が言いたいことを言うのではなく、受け手である聴衆のことをしっかり考えましょう。受け手はどんな人物であるか想定し、どんな情報を聞きたがっているのか、シュミレーションすることが大切です。
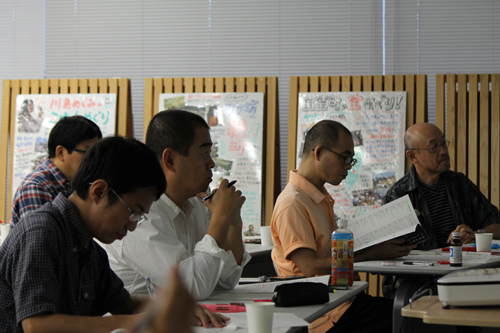

〇具体的なプレゼンの技法
プレゼンテーションではパワーポイントなどのスライドウェアを使うことが多くあります。しかしスライドウェアはプレゼンに必ず必要なものではありません。
悪い使用例やよい使用例から、効果的なスライドウェアの使い方を学びました。
(悪いスライドウェアの使用例)
・文字が多い。
・読みにくいフォント。
・重要なポイントが分からない。
・アニメーションの多様⇒重要なところをアニメーションにすると、表示される時間が短くなってしますので、大事なポイントにも関わらず見落とされる可能性があります。
(良いスライドウェアの使用例)
・文字は少なく。話せば分かることは書かない。
・数字や写真を効果的に使う。
・話題の転換に活用する。
※ポイント※
シンプルで洗練されたスライドを目指しましょう。また、写真には一目で分かるという強みがあります。普段からたくさん写真を撮って活用していきましょう。

〇まとめ〇
1.プレゼンの目的
・相手にどんな行動を起こさせたいのか
・聴衆はどんな人物なのか
2.スライドはシンプルに
・すべてではなく、伝える情報を絞る
3.いきなりスライドを作らない
・マインドマップでアイデアを書き出す
おまけ:プレゼンは時間内(早め)に切り上げる
吉井さんの講座自体が、良いプレゼンのお手本となっていました。ミュージカルのようなしゃべりに引き込まれるあっという間の3時間半でした。
参加者からは
・プレゼン力を磨くことで、「本質」、「一番大事なこと」をつかむ、たどり着く、共有することもできるはずだと実感しました。
・プレゼンって芸術だと感じました。完成度の高いモデルを見せていただきました。吉井さんの目的意識、とても参考になりました。
・人をひきつけるプレゼテーションは、思っていたよりシンプルで、簡単で良いのだと思った。情報があふれているので、伝えたい情報を絞ることの大切さに気づきました。
といったご感想をいただきました!
吉井さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
次回はいよいよ最終回、『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』プレ審査会&振り返りです。
2014年09月10日
『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』第2回 ファシリテーション講座を開催しました!
9月7日(日)に、計4回の連続講座『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』の第2弾、ファシリテーション講座をみやざき県民協働支援センターにて開催いたしました!
第2回目の講師は、NPO法人 日本ファシリテーション協会 フェローの加留部 貴行さん。

加留部さんは、九州大学法学部卒業後、㈱西部ガスに入社。人事、営業、新規事業部門に従事。学生時代からまちづくり活動に携わり、入社後も活 動を継続。2001年には西部ガスより福岡市へNPO・ボランティア支援推進専門員として2年半派遣。西部ガス復帰後は指定管理者制度を担当。2007年からは九州大学へ出向し、大学改革プロジェクトを経て、ファシリテーション導入を通じた教育プログラム開発や学内外プロジェク トを担当。 企業、大学、行政、NPOの4つのセクターを経験している「ひとり産学官民連携」を活かした共働ファシリテーションを実践されています。 2011年4月に独立し、現在は、加留部貴行事務所AN-BAI代表、㈱トライローグ取締役でいらっしゃいます。
今回は会議運営をスムーズにするためのファシリテーションについてお話いただきました!

〇なぜ私達はわざわざ集め・集まって会議を開くのでしょうか?
わざわざ集まって会議を開くには、3つの理由があるという加留部さん。
①個人では限界があるから。・・・会議を開くことで、個人で解決できない物理的な問題を解決できたり、質を上げることができます(知らないことを知る・他の人の経験を追体験できる・気づきがある)
②文字情報には限界があるから。・・・現代社会には情報があふれています。文字情報では伝えたいことが伝わっていない可能性があります。
③互いに確かめあう必要があるから。・・・こちらが伝えたと思っている通りに、相手は受け取ってくれているでしょうか?受け取り方はバラバラかも知れません。確かめ合うために、実際に集まり顔をつき合わせて会議をします。
※パソコンの普及により、私達は画面を見ている時間が長くなり、なかなか顔を見て話す場をもつことを意識できていません。会議は人と人が向き合って話す、貴重な場になりつつあるそうです。
〇ファシリテーション・ファシリテーターとは?
・ファシリテーションは、「引き出す力」。その他にも、「その気にさせる・芽吹かせる」といった意味があります。会議の場という「土」に、参加者という「種」がまかれます。ファシリテーターは、参加者がのびのびと参加できるようにする「発芽促進剤」のイメージだそうです。
・進行役とファシリテーターはどう違うの?
進行役は、議題に沿って会議を進めるという役割ですが、ファシリテーターはより予定調和的でない、場にゆだねた進行をします。「やってみないと分からない!」というところが強いそうです。
〇ファシリテーターの役割
・中立的な立場で、(最後に発言をする)⇒このポイントを意識すれば「お先にどうぞ」の気持ちが生まれます。
・チームのプロセスを管理し、(進め方を意識する)⇒進め方は誘導しますが、内容は誘導しません。「決定の仕方を決める」といった、合意形成を促す役割です。
・チームワークを引き出し、(ひとりでやらない)⇒「ひとりでやらない・ひとりでさせない・ひとりにさせない」という気持ちで気を配ることが大切です。
・そのチームの成果が最大になるよう支援する。
〇プロセスを「交通整理」するファシリテーター
・ガードレールのように、話が逸れそうになったら、議題に戻すのがファシリテーターの役割。
そのためのポイントは、実は私たちが小学生のころから経験している、「議題を板書すること」
議題を始めに目に付くところに書いておくだけで、話が逸れていくのを防ぐことができるそうです。
〇「成果」さることながら、「納得感」を引き出すために注力する。
会議では、すぐ結果が目に見える「成果」の出る結論を出そうとしがちになります。しかし、
まずは、決まったことに対して「それじゃあ、みんなでがんばっていこうか!」と思える納得感のある会議を目指しましょう。(図■部分のイメージ)

〇ワークショップ~五年後の私たちはどのようなくらしをしているでしょうか~
今回は「ワールド・カフェ」という形式で、ワークショップを行いました。
【参考】「ワールド・カフェ」の基本的な進め方
①1グループ4~6人ほどで構成されたテーブルを複数つくる
②進行役から提起される発問についてテーブルで話し合いを進め、そこで
話されたこと、感じたこと、気づいたことなどを模造紙に落書きをする
③20分置きくらいに、ホスト1名を残して、全員席替えをする
④新しいメンバー同士で先程まで自分がいたテーブルで話し合われていた
内容を披露しあう
⑤これを時に数回繰り返し、最後には元のテーブルに戻る
まずは、模造紙中央に大きく議題を書きます!これで議題から逸れた話も自然に戻すことができます。

グループで話しあわれた「みんなの意見」を背負って次のテーブルに移ります。人から聞いたいい意見も、自分のことのように話すことができます。


最後に、自分の中で引っかかったキーワードを、個人で抜き出してもらいました。


参加者からは
・緊張する体質ですが、雰囲気・言葉遣いで意見が言いやすくなることを実感できました。
・6人以下のグループ、雰囲気作り、リズム、声のトーンなど、目からうろこなことがたくさんで勉強になり、勇気が出ました。ありがとうございました。
といったご感想をいただきました!
加留部さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
次回の『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』は第3回・プレゼン講座です。




