2014年02月01日
地域版ヒムカレッジvol.2「実践者から学ぶ地域づくり講座」
1月26日に地域版ヒムカレッジvol.2「実践者から学ぶ地域づくり講座」を開催いたしました。
今回は国富町での開催でしたが、事前申込者の他に「国富町と綾町をまるっと体感ツアー」から参加された方など40名近くの方々に参加して頂きました!
今回の講師は熊日宮原販売センター代表/同志社大学大学院委託講師の岩本剛さん。

岩本さんは1962年、熊本生まれ。1995年、住民参加のまちづくり拠点である 宮原町「まちづくり情報銀行」開設後、7つの民間団体を設立。
住民参加・主導型のまちづくりのほか、子どもの人材育成、大学生のゼミ合宿・地域づくりインターン受入れ等を実践。また、全国の地域づくり団体等との物産交流「わらしべ長者便」、里山保全のための「お歳暮大作戦」等を主宰し、2010年10月より氷川町において熊日宮原販売センター代表に就任。これまでの活動を継続しつつ、ミニコミ紙の発行と子ども記者クラブの立ち上げによる各種事業を展開。2012年4月より同志社大学院の委託講師となり、同大学院の政策研究プロジェクト科目により、広域連携・交流のまちづくりの可能性を追求されています。

子どもたちが将来、帰ってきたいと思える地域づくりとは何か岩本さんがこれまで実践されてきた様々な活動を通してお話して頂きました。
「地域で暮らす人々が身の周りの全ての環境や伝統文化などの潜在的な可能性を追求することにより、経済的な自立性を手に入れ地域社会に立脚した、ゆとりのある生活をめざすこと」
まず初めに岩本さんの考える地域づくりについてお話いただきました。
一石五鳥を目指す。一石二鳥という考えではダメで、1つの事からいくつもの実績をあげていくことを目指し、10年先を見据える設計を子どもたちと一緒に考えていくことが様々なアクションにスムーズに繋がっていくのだと岩本さんは話されました。
小中学生によるビオトープ管理組織の「ギロッチョくらぶ」でもその精神を元に活動されてきたそうです。
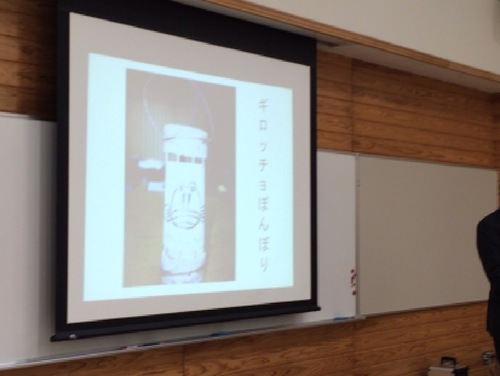
口コミによる力を多大に発揮しているというミニコミ紙の発行も、子どもが記者として情報を発信していく子ども記者クラブの活動と繋がっており、子どもたち自身が地域を知るきっかけづくりにもなっているそうです。
また子ども記者クラブは記事を書くだけではなく、一年間を通して、農業体験やわらしべアイスの商品開発や対面販売、インターン交流会など、様々な活動を通して子どもが地域と直接接する機会を設けており、子どもと地域との大きな架け橋となっています。
時代の変化により家庭環境や教育現場が今と昔では違ったものになったと話す岩本さん。
だからこそ子ども記者クラブや大学生を招いての学習会など普段家庭や学校では教われない「地域について知る」ということが実践出来ており、10年先の将来を見据えたとても意義のある活動なのだと感じました。
「地域と家庭がしっかりと腰を据えて子どもの教育の事を考えると、子どもにとって生まれ育った環境というものは誇れる物になる」という岩本さんの言葉もとても印象的でした。

質問タイムでは
「学校と活動するとなった時に苦労された事や逆に上手くいった事は何ですか?」という参加者からの質問に岩本さんは
「昔と今の家庭環境の違いや先生方の労働環境の悪さから来る問題が多くあるので、そういった所の改善が必要」と答えていました。
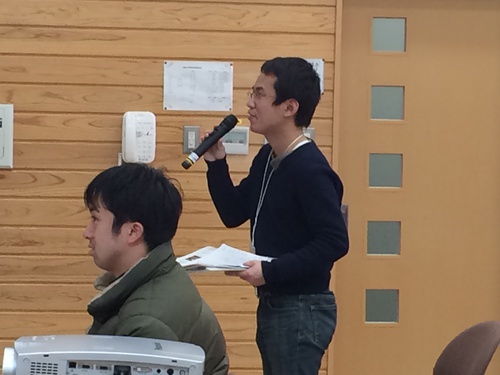
参加者からは、
「子供達が書く事を通して、学ぶ場が地域にあるのが素晴らしいと思った。」
「地域の中の人材をいかにして活動に巻き込んでいく方向性が心に残りました。」
「ストーリー作りが大事なこと。行政がやること、民間がやることの差。」
「今の大人に必要なことを子供がやっている気がしました。良い取り組みだと思いました。」
といったご意見・ご感想をいただきました。
岩本さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!
今回は国富町での開催でしたが、事前申込者の他に「国富町と綾町をまるっと体感ツアー」から参加された方など40名近くの方々に参加して頂きました!
今回の講師は熊日宮原販売センター代表/同志社大学大学院委託講師の岩本剛さん。

岩本さんは1962年、熊本生まれ。1995年、住民参加のまちづくり拠点である 宮原町「まちづくり情報銀行」開設後、7つの民間団体を設立。
住民参加・主導型のまちづくりのほか、子どもの人材育成、大学生のゼミ合宿・地域づくりインターン受入れ等を実践。また、全国の地域づくり団体等との物産交流「わらしべ長者便」、里山保全のための「お歳暮大作戦」等を主宰し、2010年10月より氷川町において熊日宮原販売センター代表に就任。これまでの活動を継続しつつ、ミニコミ紙の発行と子ども記者クラブの立ち上げによる各種事業を展開。2012年4月より同志社大学院の委託講師となり、同大学院の政策研究プロジェクト科目により、広域連携・交流のまちづくりの可能性を追求されています。

子どもたちが将来、帰ってきたいと思える地域づくりとは何か岩本さんがこれまで実践されてきた様々な活動を通してお話して頂きました。
「地域で暮らす人々が身の周りの全ての環境や伝統文化などの潜在的な可能性を追求することにより、経済的な自立性を手に入れ地域社会に立脚した、ゆとりのある生活をめざすこと」
まず初めに岩本さんの考える地域づくりについてお話いただきました。
一石五鳥を目指す。一石二鳥という考えではダメで、1つの事からいくつもの実績をあげていくことを目指し、10年先を見据える設計を子どもたちと一緒に考えていくことが様々なアクションにスムーズに繋がっていくのだと岩本さんは話されました。
小中学生によるビオトープ管理組織の「ギロッチョくらぶ」でもその精神を元に活動されてきたそうです。
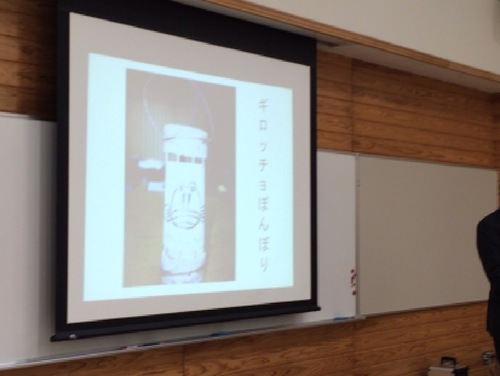
口コミによる力を多大に発揮しているというミニコミ紙の発行も、子どもが記者として情報を発信していく子ども記者クラブの活動と繋がっており、子どもたち自身が地域を知るきっかけづくりにもなっているそうです。
また子ども記者クラブは記事を書くだけではなく、一年間を通して、農業体験やわらしべアイスの商品開発や対面販売、インターン交流会など、様々な活動を通して子どもが地域と直接接する機会を設けており、子どもと地域との大きな架け橋となっています。
時代の変化により家庭環境や教育現場が今と昔では違ったものになったと話す岩本さん。
だからこそ子ども記者クラブや大学生を招いての学習会など普段家庭や学校では教われない「地域について知る」ということが実践出来ており、10年先の将来を見据えたとても意義のある活動なのだと感じました。
「地域と家庭がしっかりと腰を据えて子どもの教育の事を考えると、子どもにとって生まれ育った環境というものは誇れる物になる」という岩本さんの言葉もとても印象的でした。

質問タイムでは
「学校と活動するとなった時に苦労された事や逆に上手くいった事は何ですか?」という参加者からの質問に岩本さんは
「昔と今の家庭環境の違いや先生方の労働環境の悪さから来る問題が多くあるので、そういった所の改善が必要」と答えていました。
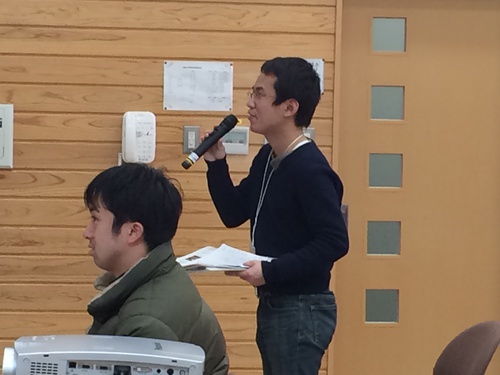
参加者からは、
「子供達が書く事を通して、学ぶ場が地域にあるのが素晴らしいと思った。」
「地域の中の人材をいかにして活動に巻き込んでいく方向性が心に残りました。」
「ストーリー作りが大事なこと。行政がやること、民間がやることの差。」
「今の大人に必要なことを子供がやっている気がしました。良い取り組みだと思いました。」
といったご意見・ご感想をいただきました。
岩本さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!
令和2年度 「日本のひなた 地域づくり実践塾」報告会・審査会
ヒムカレッジVol.4の講師 成田万寿美さんが朝日新聞のコラムに!
ヒムカレッジVol.1「地球が壊れる前に」上映会×西原智昭氏講演会 イベント報告
ヒムカレッジVol.1「地球が壊れる前に」上映会×西原智昭氏講演会 イベント報告 映画部分セリフ編
ヒムカレッジVol.1「地球が壊れる前に」上映会×西原智昭氏講演会 イベント報告 映画部分あらすじ感想編
ヒムカレッジVol.5 「超えろヴィレヴァン、新しい公共施設の在り方」を開催しました。
ヒムカレッジVol.4の講師 成田万寿美さんが朝日新聞のコラムに!
ヒムカレッジVol.1「地球が壊れる前に」上映会×西原智昭氏講演会 イベント報告
ヒムカレッジVol.1「地球が壊れる前に」上映会×西原智昭氏講演会 イベント報告 映画部分セリフ編
ヒムカレッジVol.1「地球が壊れる前に」上映会×西原智昭氏講演会 イベント報告 映画部分あらすじ感想編
ヒムカレッジVol.5 「超えろヴィレヴァン、新しい公共施設の在り方」を開催しました。
Posted by みやざきNPO・協働支援センター at 16:47│Comments(3)
│イベント報告
この記事へのコメント
お世話になります。
危機管理アドバイザーの尾下です。
「共感疲労対策について」
この度、災害ストレスの研究成果が認められ、東日本大震災被災地に中国上海の視察団に同行後「地震大国日本の防災・減災対策」をテーマに講演を行いました。
その中で、支援者のストレス(共感疲労)対策の必要性を痛感いたしました。
東日本大震災で、災害にさらされた人々が呈する外傷後ストレス障害(PTSD)が注目され支援のあり方なども研究報告されています。そのため専門家がトラウマを負った被支援者をケアする機会も増えています。しかし、その際に被支援者の語りを聞く中で支援者側が受ける傷についてはどうだろうか。他者が体験したトラウマとなる出来事に曝されることが、支援する側のトラウマになるという考えを一次的外傷性ストレス障害と呼び、二次的外傷性ストレス障害と区別した。二次的外傷性ストレスとは、支援者がトラウマを負った被支援者によって外傷性の体験に曝された結果として苦痛を経験し、それがストレスとなることです。
症状は、被支援者の体験した出来事に関連する刺激に対する再体験、回避または麻痺、覚醒亢進症状を起こすものに加え、無力感や困惑、孤立無援感があり、そしてその症状が実在する原因に直結しないこともあリます。これは、被支援者に深く共感するために起こる疲労、つまり疲労するということのポジティブな側面に目を向けていると考えるからです。
共感疲労とは、支援者が被支援者のトラウマ体験したことやその内容について知ることにより、苦痛や逆境に見舞われた他者に対する深い共感や悲嘆の感情が起こり、その人の苦痛やその原因を取り除き、癒したいという強い希求を伴うものである。また共に悩み、考え、対処しようとする試みから起きる疲労。状態像としては、被支援者の体験した出来事に関連する刺激に対する再体験、回避または麻痺症状を起こしたりするものである。共感満足は、共感疲労と同じく強い望みを伴う感情から支援をおこない、そこで得られた支援者側の「支援をしてよかった」「役に立てたという感覚がもてた」といったポジティブなものとする。
これらには、支援者側の内的世界観の変容も生じる可能性がある。例えば、ものの見方や心理的ニードにネガティブな変容が生じるのは、共感疲労の結果である。しかし、総合して支援者が「内的な成長」だと受け止めることができるようなポジティブな変容が起きるのならば、それは共感満足の影響といえるだろう。しかし、これは時間軸的には、1つのケースが終結に至った後や、その後に振り返った際に見えてくるものもあると考えられる。
被支援者を支援する相談員を対象とし、① 共感満足・共感疲労に影響を及ぼしているのは、どのような心理的要因か、支援活動において共感疲労を起こした場合には、被支援者のトラウマ体験→支援者のSTS→ 被支援者の二次被害という悪循環が起きると考え、② 支援活動の好循環を作るためにはどのようにすれば良いのか、③ どのようにすれば、被支援者を支援する相談員(災害救援ボランティア)の共感疲労が深刻な状態に進行することを防ぐことができるのかについて明らかにしていくことが肝要である。
今後ともご指導ご鞭撻ご配慮賜れば幸甚に存じます。 尾下拝
危機管理アドバイザーの尾下です。
「共感疲労対策について」
この度、災害ストレスの研究成果が認められ、東日本大震災被災地に中国上海の視察団に同行後「地震大国日本の防災・減災対策」をテーマに講演を行いました。
その中で、支援者のストレス(共感疲労)対策の必要性を痛感いたしました。
東日本大震災で、災害にさらされた人々が呈する外傷後ストレス障害(PTSD)が注目され支援のあり方なども研究報告されています。そのため専門家がトラウマを負った被支援者をケアする機会も増えています。しかし、その際に被支援者の語りを聞く中で支援者側が受ける傷についてはどうだろうか。他者が体験したトラウマとなる出来事に曝されることが、支援する側のトラウマになるという考えを一次的外傷性ストレス障害と呼び、二次的外傷性ストレス障害と区別した。二次的外傷性ストレスとは、支援者がトラウマを負った被支援者によって外傷性の体験に曝された結果として苦痛を経験し、それがストレスとなることです。
症状は、被支援者の体験した出来事に関連する刺激に対する再体験、回避または麻痺、覚醒亢進症状を起こすものに加え、無力感や困惑、孤立無援感があり、そしてその症状が実在する原因に直結しないこともあリます。これは、被支援者に深く共感するために起こる疲労、つまり疲労するということのポジティブな側面に目を向けていると考えるからです。
共感疲労とは、支援者が被支援者のトラウマ体験したことやその内容について知ることにより、苦痛や逆境に見舞われた他者に対する深い共感や悲嘆の感情が起こり、その人の苦痛やその原因を取り除き、癒したいという強い希求を伴うものである。また共に悩み、考え、対処しようとする試みから起きる疲労。状態像としては、被支援者の体験した出来事に関連する刺激に対する再体験、回避または麻痺症状を起こしたりするものである。共感満足は、共感疲労と同じく強い望みを伴う感情から支援をおこない、そこで得られた支援者側の「支援をしてよかった」「役に立てたという感覚がもてた」といったポジティブなものとする。
これらには、支援者側の内的世界観の変容も生じる可能性がある。例えば、ものの見方や心理的ニードにネガティブな変容が生じるのは、共感疲労の結果である。しかし、総合して支援者が「内的な成長」だと受け止めることができるようなポジティブな変容が起きるのならば、それは共感満足の影響といえるだろう。しかし、これは時間軸的には、1つのケースが終結に至った後や、その後に振り返った際に見えてくるものもあると考えられる。
被支援者を支援する相談員を対象とし、① 共感満足・共感疲労に影響を及ぼしているのは、どのような心理的要因か、支援活動において共感疲労を起こした場合には、被支援者のトラウマ体験→支援者のSTS→ 被支援者の二次被害という悪循環が起きると考え、② 支援活動の好循環を作るためにはどのようにすれば良いのか、③ どのようにすれば、被支援者を支援する相談員(災害救援ボランティア)の共感疲労が深刻な状態に進行することを防ぐことができるのかについて明らかにしていくことが肝要である。
今後ともご指導ご鞭撻ご配慮賜れば幸甚に存じます。 尾下拝
Posted by 尾下義男 at 2014年04月10日 08:17
お世話になります。
危機管理アドバイザーの尾下と申します。
7月4日日本医療福祉学会・第10回全国大会が昭和薬科大学で開催されました。基調講演で「災害ストレストと心のケア対策」をお話させて頂いたところ多くの講聴者から共感されました。
更なる精進をして参りますので、ご指導賜りますようお願い申し上げます。尾下拝
危機管理アドバイザーの尾下と申します。
7月4日日本医療福祉学会・第10回全国大会が昭和薬科大学で開催されました。基調講演で「災害ストレストと心のケア対策」をお話させて頂いたところ多くの講聴者から共感されました。
更なる精進をして参りますので、ご指導賜りますようお願い申し上げます。尾下拝
Posted by 尾下義男 at 2015年07月04日 16:48
前略
お世話になります。
いばらき防災大学講師の尾下と申します。
「あなたは、地震等の際に、頭をどのように守りますか?」
地震発生時の頭を守る行動は、素手やカバン等で直接頭を抑えるよう指導しています。
この行動をとると首を左右に動かすことが難しく、視野が90度(正面)のみに止まります。
そこで、私は、頭を素手で覆うときは手のひらを下向き(両手を組まず、左右どちらの手の甲の上に手のひらを重ねる=手のひらに怪我をすると物が持てなくなり、避難行動時に大きな支障をきたします。)ことを提案・指導しています。
つまり、頭の上に空間(約10cm~15cm)をつくると、首がスムーズにまわり、視野が180度に広がり危機を回避することができ、状況・危険度の確認も容易になります。しかも天井等からの落下物が頭を直撃するとしても、その衝撃の緩和策(ヘルメットの構造を参照)にもなります。
机上の空論より、多角的な物事の見方、つまり、「ものは試し」の精神で別のやり方を試してみてください。
このように一コマ(身を守る行動)の動作を積極的に訓練することで、安心、安全の確保の実践的・具体的な動作が市民一人ひとりに浸透して、実効性のある、実りある防災訓練の展開ができると確信しています。
ご理解の上、ご指導賜れば幸甚に存じます。
尾下拝
お世話になります。
いばらき防災大学講師の尾下と申します。
「あなたは、地震等の際に、頭をどのように守りますか?」
地震発生時の頭を守る行動は、素手やカバン等で直接頭を抑えるよう指導しています。
この行動をとると首を左右に動かすことが難しく、視野が90度(正面)のみに止まります。
そこで、私は、頭を素手で覆うときは手のひらを下向き(両手を組まず、左右どちらの手の甲の上に手のひらを重ねる=手のひらに怪我をすると物が持てなくなり、避難行動時に大きな支障をきたします。)ことを提案・指導しています。
つまり、頭の上に空間(約10cm~15cm)をつくると、首がスムーズにまわり、視野が180度に広がり危機を回避することができ、状況・危険度の確認も容易になります。しかも天井等からの落下物が頭を直撃するとしても、その衝撃の緩和策(ヘルメットの構造を参照)にもなります。
机上の空論より、多角的な物事の見方、つまり、「ものは試し」の精神で別のやり方を試してみてください。
このように一コマ(身を守る行動)の動作を積極的に訓練することで、安心、安全の確保の実践的・具体的な動作が市民一人ひとりに浸透して、実効性のある、実りある防災訓練の展開ができると確信しています。
ご理解の上、ご指導賜れば幸甚に存じます。
尾下拝
Posted by 危機管理アドバイザー尾下義男 at 2015年11月23日 16:29









