 › みやざきNPO・協働支援センターのブログ › イベント報告
› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › イベント報告2016年01月09日
地域版ヒムカレッジ in 高千穂 開催しました!
平成27年11月27日(金)に高千穂町にて、コミュニケーションデザイナーの東ヤスオさんをお招きし、人生をデザインする『LEGO®シリアスプレイ®』と題して地域版ヒムカレッジを開催いたしました!
前日のヒムカレッジと同じテーマでLEGO®シリアスプレイ®を使ったワークショップを体験していただきました。

□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
東ヤスオ(アズマ ヤスオ)
コミュニケーションデザイナー
Unitedman代表。
LEGO®シリアスプレイ®公認ファシリテータ
米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ
1975年大阪府藤井寺市生まれ。
自分の「強み」や「使い方」が書かれている「自分取扱説明書」を手に入れて、毎日を楽に自分らしく生きていく方法を世に発信するため、2013年よりプロコーチとして本格始動。経営者やビジネスマンを中心にサポートを行っている。
浪速の笑いのエッセンスを交えながら、パーソナルコーチングやワークショップの場を日々提供中。
●LEGO®シリアスプレイ®を活用したワークショップのご提案
http://azuma-yasuo.com/wp-content/uploads/2015/10/lego_kikaku.pdf
http://matome.naver.jp/odai/2143718779396565201
----------------------------------------------------------------------------
高千穂では、地元の企業の方や役場職員、学生の方、また宮崎市内からこの為に高千穂に来て頂いた方など、23名の方々にご参加いただきました。
前日と同様のテーマのワークショップのため今回はダイジェストで当日の様子をご紹介します!
(プログラムの詳細はヒムカレッジ2015 vol.5の活動レポートをご覧下さい。)
まずはウォーミングアップのタワー作りの様子。


次は未知の生物づくりへ。

「最高の瞬間」はこのような作品が。
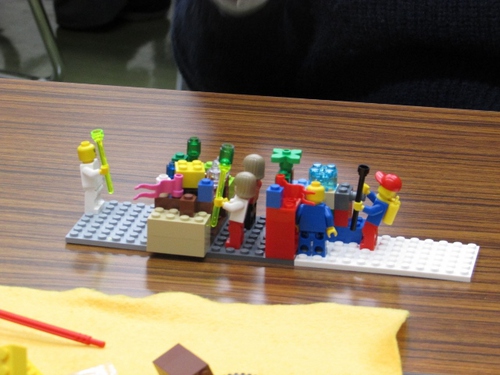
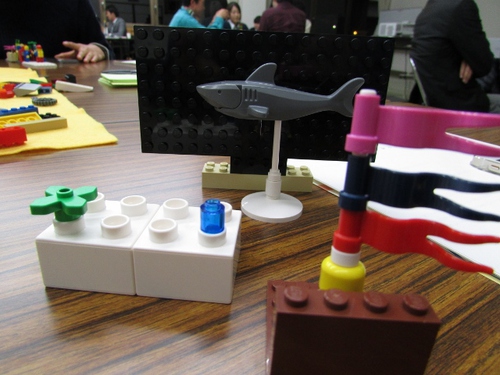
「5年後」の理想の姿の制作へ。
こちらは自分の田んぼで田植えをしている姿ということでした。


「5年後の理想の社会」のモデリングの様子。
こちらは自然と共生する社会を作ったということでした。緑を多く使った色使いに意味づけが表現されています!


高千穂では最後にグループの代表者に感想やワークを通しての気付きなどを発表して頂きました!


ご参加頂いた皆様からは、
「自分の理想とやるべきことを知った。」
「手を動かすことで思考が拡張するのだと気づきました。」
「レゴブロックのモデリングという文字と疲れない手法でコミュニケーションをとることが新鮮で楽しかったです。」
「レゴがこういう使われ方をしていることが面白いと思う。学校とかでもやってみたら良さそうだと思いました。」
といったご感想をいただきました!
最高の瞬間や理想の姿や社会を作るワークでは、自分たちの住む地域の中でのことをレゴで表現する方が多く、
前日に宮崎で行ったヒムカレッジよりも、自分たちの住む高千穂という地域をより意識しながらワークに取組まれていたご様子でした。
自分の人生を考える中で、地域の中での自分自身の人生を考えることにも繋がったのではないかなと感じた今回の地域版ヒムカレッジとなりました。
参加していただいた皆様、そして講師の東さん、本当にありがとうございました!
LEGO®シリアスプレイ®が気になった方やうちの職場や団体でもやってみたいと思った方は
東さんのブログやfacebookなどをチェックしていただきメールなどでお問い合わせ下さいヽ(´∀`。)ノ
mail: info@azuma-yasuo.com
blog: azuma-yasuo.com
facebook: facebook.com/hugstance
前日のヒムカレッジと同じテーマでLEGO®シリアスプレイ®を使ったワークショップを体験していただきました。

□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
東ヤスオ(アズマ ヤスオ)
コミュニケーションデザイナー
Unitedman代表。
LEGO®シリアスプレイ®公認ファシリテータ
米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ
1975年大阪府藤井寺市生まれ。
自分の「強み」や「使い方」が書かれている「自分取扱説明書」を手に入れて、毎日を楽に自分らしく生きていく方法を世に発信するため、2013年よりプロコーチとして本格始動。経営者やビジネスマンを中心にサポートを行っている。
浪速の笑いのエッセンスを交えながら、パーソナルコーチングやワークショップの場を日々提供中。
●LEGO®シリアスプレイ®を活用したワークショップのご提案
http://azuma-yasuo.com/wp-content/uploads/2015/10/lego_kikaku.pdf
http://matome.naver.jp/odai/2143718779396565201
----------------------------------------------------------------------------
高千穂では、地元の企業の方や役場職員、学生の方、また宮崎市内からこの為に高千穂に来て頂いた方など、23名の方々にご参加いただきました。
前日と同様のテーマのワークショップのため今回はダイジェストで当日の様子をご紹介します!
(プログラムの詳細はヒムカレッジ2015 vol.5の活動レポートをご覧下さい。)
まずはウォーミングアップのタワー作りの様子。


次は未知の生物づくりへ。

「最高の瞬間」はこのような作品が。
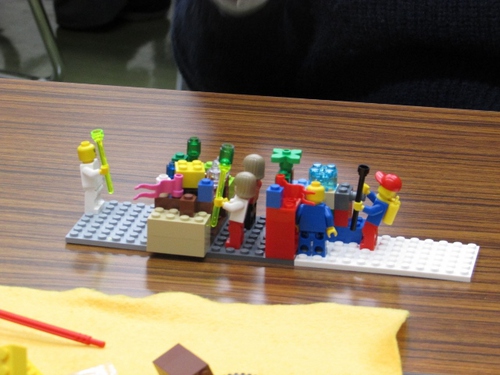
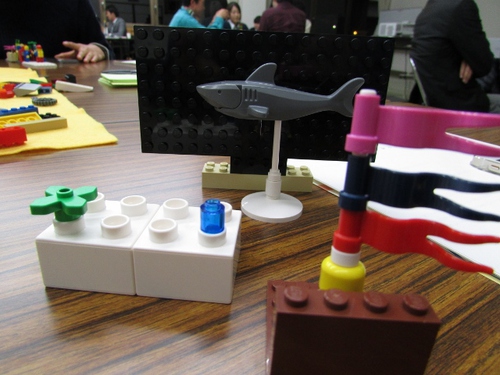
「5年後」の理想の姿の制作へ。
こちらは自分の田んぼで田植えをしている姿ということでした。


「5年後の理想の社会」のモデリングの様子。
こちらは自然と共生する社会を作ったということでした。緑を多く使った色使いに意味づけが表現されています!


高千穂では最後にグループの代表者に感想やワークを通しての気付きなどを発表して頂きました!


ご参加頂いた皆様からは、
「自分の理想とやるべきことを知った。」
「手を動かすことで思考が拡張するのだと気づきました。」
「レゴブロックのモデリングという文字と疲れない手法でコミュニケーションをとることが新鮮で楽しかったです。」
「レゴがこういう使われ方をしていることが面白いと思う。学校とかでもやってみたら良さそうだと思いました。」
といったご感想をいただきました!
最高の瞬間や理想の姿や社会を作るワークでは、自分たちの住む地域の中でのことをレゴで表現する方が多く、
前日に宮崎で行ったヒムカレッジよりも、自分たちの住む高千穂という地域をより意識しながらワークに取組まれていたご様子でした。
自分の人生を考える中で、地域の中での自分自身の人生を考えることにも繋がったのではないかなと感じた今回の地域版ヒムカレッジとなりました。
参加していただいた皆様、そして講師の東さん、本当にありがとうございました!
LEGO®シリアスプレイ®が気になった方やうちの職場や団体でもやってみたいと思った方は
東さんのブログやfacebookなどをチェックしていただきメールなどでお問い合わせ下さいヽ(´∀`。)ノ
mail: info@azuma-yasuo.com
blog: azuma-yasuo.com
facebook: facebook.com/hugstance
2016年01月09日
「ヒムカレッジ2015 vol.5」開催しました!
平成27年11月26日(木)に、コミュニケーションデザイナーの東ヤスオさんをお招きし、
人生をデザインする『LEGO®シリアスプレイ®』と題して今年度5回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
東ヤスオ(アズマ ヤスオ)
コミュニケーションデザイナー
Unitedman代表。
LEGO®シリアスプレイ®公認ファシリテータ
米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ
1975年大阪府藤井寺市生まれ。
自分の「強み」や「使い方」が書かれている「自分取扱説明書」を手に入れて、毎日を楽に自分らしく生きていく方法を世に発信するため、2013年よりプロコーチとして本格始動。経営者やビジネスマンを中心にサポートを行っている。
浪速の笑いのエッセンスを交えながら、パーソナルコーチングやワークショップの場を日々提供中。
●LEGO®シリアスプレイ®を活用したワークショップのご提案
http://azuma-yasuo.com/wp-content/uploads/2015/10/lego_kikaku.pdf
http://matome.naver.jp/odai/2143718779396565201
----------------------------------------------------------------------------
今回も、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など幅広い年代層の26名の方々にご参加いただきました。
また今回は最初から机をグループ分けしており、それぞれの机の上にランダムにレゴブロックが置かれた状態でスタートしました!

○LEGO®シリアスプレイ®とは?
【見えないものを「見える化」し、新しい気づきを得る】
という問題解決手法で、2001年に LEGO本社のあるデンマークで生まれました。

“手と脳は連携を取り、相互に信号のやり取りしながら、新たな知識を構築する”
という理論に基づき開発されたそうです。
2003年には2度のスペースシャトルの事故を受けて組織された
「NASAの安全対策チーム」にて研究者やエンジニアといったメンバー間の
・コミュニケーションを活性化し、
・意味のある意見の提案や議論を行う環境を創り出し、
・チームとしての一体感を強化すること
を狙いとしてLEGO®シリアスプレイ®が導入された事例があります。
わずか5時間のワークショップで行った結果、
後続のプログラムが効果的に進むきっかけになったということでした。
普段は「組織のビジョン作り」「新しいアイデアの創出」「個人のキャリア開発」「チームビルディング」などでLEGO®シリアスプレイ®は活用されているということでしたが、
今回は「人生」をデザインするということで個人のキャリア開発に焦点を当てたワークショップとして取組んでいただきました。
○目的の共有
① 実現したい「未来」を明確にする
② 具体的な「行動」を自ら選択する
次に今回はこの2つを目的にするということを全体で共有しました。
○ウォーミングアップ①
まずはウォーミングアップとして誰よりも高い「タワー」を作っていただきました!
単純な組立て方に思えるかもしれませんが、形も大きさもバラバラなレゴを使わないといけないので意外と難しさを感じている方が多いご様子でした。

○ウォーミングアップ②
続いて、まず直感で選んだ好きなパーツを10個取り、
そのパーツを使って「未知の生物」を作ることに。

この辺りから皆さん集中して黙々と作っておりましたー。
そして、ここからがレゴシリアスプレイを体験する上で重要なポイントで、
作ったものに無理やりにでも意味づけをして、それを他者に説明するということです。
ここで作って頂いた未知の生物に関する特徴や背景などを説明してグループ内でシェアし、気になる作品には質問を。

更にこの未知の生物を自分に置き換えて特徴などを説明しながら自己紹介を行っていただきました。
説明に戸惑う様子も見受けられましたが、皆さん何とか言葉を紡ぎながら自分が作った作品を自分の言葉で説明しておりました。
このように作品を通して作品のストーリーを発表し共有したり、周りからの質問に答えることにより、
自分の内観(思いや考え方)に気付くことが出来るということでした。
○ルール
実際のワークに進む前に以下の5つのルールが設定されました。
① 手を信じて、手が動くのに任せる
② モデルを見ながら、モデルを通して話す
③ 後付け、こじつけOK!とにかく言葉に
④ 芸術作品を作るワークではない
⑤ 作ったモデルは写真に撮っておく
○モデリング① これまでの人生での「最高の瞬間」
そして、ここからいよいよモデリングへ。
具体的でも抽象的でもどちらでもいいので、これまでの人生での「最高の瞬間」をレゴで作っていただきました。

出されたお題に戸惑いながらも、頭で考えずにまず手を動かすことを重視して制作へ。
更に集中力が増して黙々と作業を進めていました!
ここでも出来た作品を説明し、
「この色のブロックをなぜ使ったのか?」「この配置の意味は?」などの意味付けを促進させる質問をしてグループ内で更に深堀していきました。


そして東さんから今作った作品が「なぜ最高の瞬間なのか?」という問いかけが。
東さんがこのワークを実際に自分で行った時に「自分自身が誰かに認められるという価値観」というキーワードが出たらしく、そんな時に自分は「最高の瞬間」だと思えると気付いたそうです。
このワークでは自分で「なぜ最高の瞬間なのか?」を考えることや、この「最高の瞬間」にもう一度味わうには今の自分には何が足りないか?などを考えることが大切だということでした。
また、ここからのワークで気付きになったことは机にある付箋などに忘れずに書いて頂きました。
○モデリング② あなたの「5年後」の理想の姿
続いてはあなたの「5年後」の理想の姿をレゴブロックで表していただきました。


そして先程と同様に、出来た作品を説明し、出てきた質問に答えることをグループ内で行っていただきました。
そしてここで作った作品は崩さずそのままで次のワークへ。
○モデリング③ グループ全員で作る「5年後の理想の社会」
最後のモデリングはグループで「5年後の理想の社会」をテーマに一つの作品を作るワークへ。

まずは「5年後」の理想の姿のワークで作った作品の譲れない部分「核心」だけをそれぞれ抜き出してもらい、なぜその核心を抜き出したのかを全員で共有しました。
そして、他のレゴも使いながら全員の意見を「もれなく」入れることを条件に統合していきました。
自分自身のこだわりを持ちつつ、全員の意見を入れて一つの作品を作ることの難しさを感じながらも、個人で黙々と制作に取組んでいたワークとは打って変わって、
どのグループも熱のこもった話し合いをしながら制作に取組んでいました。
完成後は、なぜこの作品が理想の社会なのかについての理由やそれぞれのレゴが表す意味やストーリーをグループ全員で共有して頂き、代表者に発表していただきました。

○具体的なアクション
最後にこれまでのワークを通して、自分の理想の姿・社会の為に、
明日からできること
明日からやめること
を考え、それぞれ付箋やノートに書いて頂き、自分の中に落とし込んでいただ今回のヒムカレッジは終了となりました。
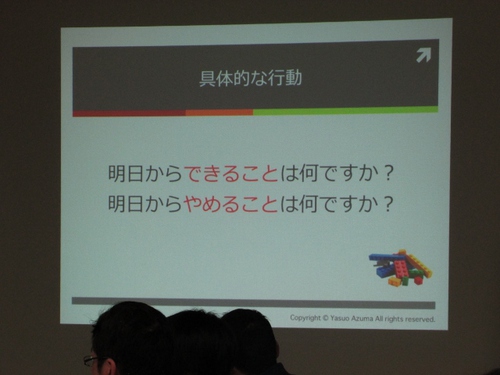
ご参加頂いた皆様からは、
「無意識に遊び作り上げたものに自分がよく表れていて面白かった。」
「自分の大切にしている価値観に気づくことが出来ました。」
「形に表す事、後づけの説明、など作るから話す事へ移行する事で自分の内部にあるものが少し具体化しスッキリしました。」
「実際に何となく作ってみることで、偶然のレゴとの出会いがあったり、そこからの気づきがあったりした。たまたまなのに、いや、だからこそ、潜在的なものを顕在化させることができるのかもと思った。」
といったご感想をいただきました!
みなさんレゴを使って自分の求める理想や未来を創造する過程で、
自分でも思っても見なかった思いや気づきを感じていたご様子でした。
そして、講座の最後に東さんが
「最後のワークで自分自信の思いやこだわりを持ちより、理想の社会をグループで作ることが出来たということは、自分が理想の姿に近づけば社会もそうなるはず。一人一人が集まって社会。今回のレゴシリアスプレイを通しての気付きを活かしてこれから自分の理想の姿を実現していってほしい。」
と話したように、今回のヒムカレッジが参加していただいた方にとって自分自身の理想の姿や人生の実現に繋がるきっかけになって頂けたらうれしいなと感じた今回のヒムカレッジでした。
参加していただいた皆様、そして講師の東さん、本当にありがとうございました!
LEGO®シリアスプレイ®が気になった方やうちの職場や団体でもやってみたいと思った方は
東さんのブログやfacebookなどをチェックしていただきメールなどでお問い合わせ下さいヽ(´∀`。)ノ
mail: info@azuma-yasuo.com
blog: azuma-yasuo.com
facebook: facebook.com/hugstance
人生をデザインする『LEGO®シリアスプレイ®』と題して今年度5回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
東ヤスオ(アズマ ヤスオ)
コミュニケーションデザイナー
Unitedman代表。
LEGO®シリアスプレイ®公認ファシリテータ
米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ
1975年大阪府藤井寺市生まれ。
自分の「強み」や「使い方」が書かれている「自分取扱説明書」を手に入れて、毎日を楽に自分らしく生きていく方法を世に発信するため、2013年よりプロコーチとして本格始動。経営者やビジネスマンを中心にサポートを行っている。
浪速の笑いのエッセンスを交えながら、パーソナルコーチングやワークショップの場を日々提供中。
●LEGO®シリアスプレイ®を活用したワークショップのご提案
http://azuma-yasuo.com/wp-content/uploads/2015/10/lego_kikaku.pdf
http://matome.naver.jp/odai/2143718779396565201
----------------------------------------------------------------------------
今回も、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など幅広い年代層の26名の方々にご参加いただきました。
また今回は最初から机をグループ分けしており、それぞれの机の上にランダムにレゴブロックが置かれた状態でスタートしました!

○LEGO®シリアスプレイ®とは?
【見えないものを「見える化」し、新しい気づきを得る】
という問題解決手法で、2001年に LEGO本社のあるデンマークで生まれました。

“手と脳は連携を取り、相互に信号のやり取りしながら、新たな知識を構築する”
という理論に基づき開発されたそうです。
2003年には2度のスペースシャトルの事故を受けて組織された
「NASAの安全対策チーム」にて研究者やエンジニアといったメンバー間の
・コミュニケーションを活性化し、
・意味のある意見の提案や議論を行う環境を創り出し、
・チームとしての一体感を強化すること
を狙いとしてLEGO®シリアスプレイ®が導入された事例があります。
わずか5時間のワークショップで行った結果、
後続のプログラムが効果的に進むきっかけになったということでした。
普段は「組織のビジョン作り」「新しいアイデアの創出」「個人のキャリア開発」「チームビルディング」などでLEGO®シリアスプレイ®は活用されているということでしたが、
今回は「人生」をデザインするということで個人のキャリア開発に焦点を当てたワークショップとして取組んでいただきました。
○目的の共有
① 実現したい「未来」を明確にする
② 具体的な「行動」を自ら選択する
次に今回はこの2つを目的にするということを全体で共有しました。
○ウォーミングアップ①
まずはウォーミングアップとして誰よりも高い「タワー」を作っていただきました!
単純な組立て方に思えるかもしれませんが、形も大きさもバラバラなレゴを使わないといけないので意外と難しさを感じている方が多いご様子でした。

○ウォーミングアップ②
続いて、まず直感で選んだ好きなパーツを10個取り、
そのパーツを使って「未知の生物」を作ることに。

この辺りから皆さん集中して黙々と作っておりましたー。
そして、ここからがレゴシリアスプレイを体験する上で重要なポイントで、
作ったものに無理やりにでも意味づけをして、それを他者に説明するということです。
ここで作って頂いた未知の生物に関する特徴や背景などを説明してグループ内でシェアし、気になる作品には質問を。

更にこの未知の生物を自分に置き換えて特徴などを説明しながら自己紹介を行っていただきました。
説明に戸惑う様子も見受けられましたが、皆さん何とか言葉を紡ぎながら自分が作った作品を自分の言葉で説明しておりました。
このように作品を通して作品のストーリーを発表し共有したり、周りからの質問に答えることにより、
自分の内観(思いや考え方)に気付くことが出来るということでした。
○ルール
実際のワークに進む前に以下の5つのルールが設定されました。
① 手を信じて、手が動くのに任せる
② モデルを見ながら、モデルを通して話す
③ 後付け、こじつけOK!とにかく言葉に
④ 芸術作品を作るワークではない
⑤ 作ったモデルは写真に撮っておく
○モデリング① これまでの人生での「最高の瞬間」
そして、ここからいよいよモデリングへ。
具体的でも抽象的でもどちらでもいいので、これまでの人生での「最高の瞬間」をレゴで作っていただきました。

出されたお題に戸惑いながらも、頭で考えずにまず手を動かすことを重視して制作へ。
更に集中力が増して黙々と作業を進めていました!
ここでも出来た作品を説明し、
「この色のブロックをなぜ使ったのか?」「この配置の意味は?」などの意味付けを促進させる質問をしてグループ内で更に深堀していきました。


そして東さんから今作った作品が「なぜ最高の瞬間なのか?」という問いかけが。
東さんがこのワークを実際に自分で行った時に「自分自身が誰かに認められるという価値観」というキーワードが出たらしく、そんな時に自分は「最高の瞬間」だと思えると気付いたそうです。
このワークでは自分で「なぜ最高の瞬間なのか?」を考えることや、この「最高の瞬間」にもう一度味わうには今の自分には何が足りないか?などを考えることが大切だということでした。
また、ここからのワークで気付きになったことは机にある付箋などに忘れずに書いて頂きました。
○モデリング② あなたの「5年後」の理想の姿
続いてはあなたの「5年後」の理想の姿をレゴブロックで表していただきました。


そして先程と同様に、出来た作品を説明し、出てきた質問に答えることをグループ内で行っていただきました。
そしてここで作った作品は崩さずそのままで次のワークへ。
○モデリング③ グループ全員で作る「5年後の理想の社会」
最後のモデリングはグループで「5年後の理想の社会」をテーマに一つの作品を作るワークへ。

まずは「5年後」の理想の姿のワークで作った作品の譲れない部分「核心」だけをそれぞれ抜き出してもらい、なぜその核心を抜き出したのかを全員で共有しました。
そして、他のレゴも使いながら全員の意見を「もれなく」入れることを条件に統合していきました。
自分自身のこだわりを持ちつつ、全員の意見を入れて一つの作品を作ることの難しさを感じながらも、個人で黙々と制作に取組んでいたワークとは打って変わって、
どのグループも熱のこもった話し合いをしながら制作に取組んでいました。
完成後は、なぜこの作品が理想の社会なのかについての理由やそれぞれのレゴが表す意味やストーリーをグループ全員で共有して頂き、代表者に発表していただきました。

○具体的なアクション
最後にこれまでのワークを通して、自分の理想の姿・社会の為に、
明日からできること
明日からやめること
を考え、それぞれ付箋やノートに書いて頂き、自分の中に落とし込んでいただ今回のヒムカレッジは終了となりました。
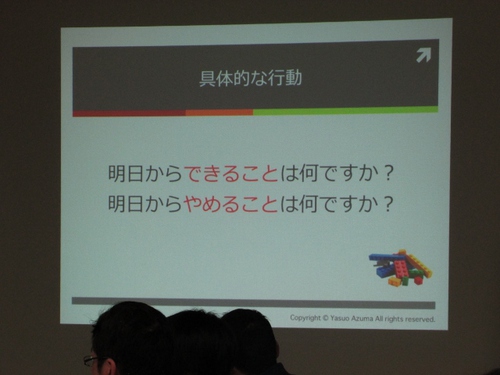
ご参加頂いた皆様からは、
「無意識に遊び作り上げたものに自分がよく表れていて面白かった。」
「自分の大切にしている価値観に気づくことが出来ました。」
「形に表す事、後づけの説明、など作るから話す事へ移行する事で自分の内部にあるものが少し具体化しスッキリしました。」
「実際に何となく作ってみることで、偶然のレゴとの出会いがあったり、そこからの気づきがあったりした。たまたまなのに、いや、だからこそ、潜在的なものを顕在化させることができるのかもと思った。」
といったご感想をいただきました!
みなさんレゴを使って自分の求める理想や未来を創造する過程で、
自分でも思っても見なかった思いや気づきを感じていたご様子でした。
そして、講座の最後に東さんが
「最後のワークで自分自信の思いやこだわりを持ちより、理想の社会をグループで作ることが出来たということは、自分が理想の姿に近づけば社会もそうなるはず。一人一人が集まって社会。今回のレゴシリアスプレイを通しての気付きを活かしてこれから自分の理想の姿を実現していってほしい。」
と話したように、今回のヒムカレッジが参加していただいた方にとって自分自身の理想の姿や人生の実現に繋がるきっかけになって頂けたらうれしいなと感じた今回のヒムカレッジでした。
参加していただいた皆様、そして講師の東さん、本当にありがとうございました!
LEGO®シリアスプレイ®が気になった方やうちの職場や団体でもやってみたいと思った方は
東さんのブログやfacebookなどをチェックしていただきメールなどでお問い合わせ下さいヽ(´∀`。)ノ
mail: info@azuma-yasuo.com
blog: azuma-yasuo.com
facebook: facebook.com/hugstance
2015年12月21日
「ヒムカレッジ2015 vol.4」開催しました!
「ヒムカレッジ2015 vol.4」開催しました!
11月1日(日)に、日本電気マネジメントパートナー株式会社人材開発サービス事業部エグゼクティブコンサルタント/NPO法人はたらく場研究所~最高の居場所~代表理事/一般社団法人組織共創アカデミー代表の中島崇学さんをお招きし、今年度4回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
中島 崇学 氏
日本電気マネジメントパートナー株式会社
人材開発サービス事業部エグゼクティブコンサルタント
NPO法人はたらく場研究所~最高の居場所~代表理事
一般社団法人組織共創アカデミー代表
NECでは人事や広報を歴任し、海外勤務を経て、
現在、組織開発や人材育成業務に携わる。
NRC社内では、「3,000 人の対話集会」をはじめとする
組織開発の経験を積み、社外でもNPOや人材育成組織を
立ち上げ、パラレルキャリアで広く組織風土改革や
ファシリテーター養成を推進する。
著書として、
『私が会社を変えるんですか?』(日本能率協会マネジメント
センター)がある。(本間正人氏と共著)
----------------------------------------------------------------------------
当日は、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など幅広い年代層の41名の方々にご参加いただきました。
今回はそのワークショップの形式から参加者一同が円となる形で始まりました。

参加者同士の対話を中心としたワークショップを体験しながら、
「あり方(自分を知る)」×「関係性(参加者との関係性)」×「スキル・ツール(場のデザ
インスキル)」というファシリテーションに大切な要素を学んでいただきました!
●グランドルール
まず始めに今回の様々なワークショップを行う上でのグランドルールが提示されました。今回はこの4つ。
・守秘義務
・相互サポート
・失敗を祝福する
・誰も間違っていない(小さな声も尊重する)

一見、ルールを決めると発言が制限されてしまうのではと思ってしまいますが、
ワークショップや会議の場ではこの様なルールを決めることで、話しにくい雰囲気や声の大きな人の存在など、みんなが話し易い場を阻害する要因を取り除く事ができスムーズに議論に入ることができるということでした。
また、「今思っていること」「今感じていること」を大切にし、それらをセッションごとに振り返ることで体験を知恵に昇華させることができると中島さんは話されました。
ここで導入となるワークへ。
「今日は私、運がいいんですよ。なぜなら・・・」という言葉の後に自分自身にとって今日感じた運がいいことを参加者同士で発表し合っていただきました。

「運がいいこと」を考えて頭がプラス思考になると同時に、実際に立って動くことで緊張が一気にほぐれました。
○チェックイン
ここで、3グループに分かれ
「名前・仕事の近況・プライベートの近況など」と
「「今の正直な気持ち」や「気になっていること」」を話してもらうチェックインが行われました。

中島さんは会議の場ではすぐに議題に入らずにこのチェックインを行うそうです。
その理由は、今”、自分にある気がかりを話し、気がかりを言葉に出して置いておくことで、場に溶け込む効果があったり、今”、の気持ちに関して嘘のない素直な発言をすることにより、お互いの背景を理解し合い、人間関係の質の向上につながる効果があるからということでした。
チェックインが終わりここでファシリテーターについて話されました。
辞書によると、
「促進する人」、「容易にする人」、「司会者」、「目標達成のための準備を手伝う人」とありますが、もっと具体的に言うと
会議の参加者が「問題解決者・創造者」だとすると、ファシリテーターは「問題解決・創造を導く人」であり、「バラバラの参加者がゴールに向かうのを臨機応変にサポートする黒子」のような存在だということでした。
そして場にファシリテーションが用いられることにより、
参加者がプロセスよりも内容に集中することができたり、参加者同士のチーム団結力や会議の効率性が高まるなどの利点があるということでした。
また今なぜファシリテーションが求められているかについては、
昔に比べ、今は、個人より「本当に社会を良くすることに向かって、みんなで一緒に考え、自分事で行動し続けることが大切な時代。」になってきているからだと中島さんは話されました。
○傾聴
ここで二人組みになってもらい、対面での緊張をなくすため90度ずれた形でワークへ。

話し手は「最近、感情が動いたこと」を話し、聞き手は相手の気持ちを察しながら、その気持ちに寄り添って聴き、感情の奥にあるニーズをつかみとれたらフィードバックする、というワークを行いました。
特に聞き手には「傾聴」することを念頭に取り組んでいただきました。
「傾聴する」とは
・目と体を向けて相手に集中する(言葉以外のメッセージも重要)
・好奇心、共感を持って聞く
傾聴のポイントとしては
・あいづち・・・相手の話に相槌を打ったり、表情や態度で反応する
基本的にはハ行 「なるほど」「おっしゃるとおりですね」などもある
・うなずき・・・相手の話を聴きながらうなずく
・繰り返し・・・「いつも細かな注文が多くてこまっちゃうんですよ」
⇒ 「細かな注文が多いんですね」
この3つをうまく使うことが大切だということでした。
短い会話でも聴き方を変えるだけで、お互いの親密度も増しているようでした。
特に気持ちを察する、共感する、受け止める。(内容はあまり考えない)「感情傾聴」が場をデザインしていくためには必要だということでした。
○YES AND
続いてコミュニケーションを行う上で相手を傷つけずに気持ちを伝える手法「YES AND」

「いいや違う」「私の思っていることはこうだ」とという「NO BUT」や、
「だけど」「しかし」「でもね」を使った「YES BUT」の返答や会話になってしまう方が多いのではないでしょうか?
しかし、共創の雰囲気作りやアイデアの収穫、接点を探るという、いい場をデザインするためにはこの「YES AND」が効果的だということでした。
ポイントは、
☆そして
☆さらに
☆加えて言うと
☆ならば
☆だとすれば
といった接続詞を使うことで、相手の言葉に光を当てながら自分の意見を乗せていくことが出来、いい場づくりにもつながるということでした。
ここで3人組みになってのワークへ。
「YES AND」を意識しながら「宝くじが一億円当たったので3人で使い道を考える」といったテーマで話し合っていただきました。

このYES ANDを意識することで、とてもいい雰囲気ができ自然と皆さんも笑顔になっておりました。
○AI
ありたい姿に対する想い・意志に焦点をあて積もる感情や主観を見極めた課題の抽出を行うポジティブアプローチの中でも代表的なAIというツールを使ったインタビュー形式のワークへ。
AIは、appreciative Inquiryの略語で、
Appreciativeとは、肯定的
動詞Appreciateのもつ2つの意味
①認識する行為(強み、健全さ、生命力、最善の状態)
②価値をさらに高める行為
Inquiryとは、
①探求すること
②発見すること
③問いかけること
「あなたの素晴らしい体験」と「あなたにとっての宮崎」といった2つのテーマでお互いにインタビューを行って頂きました。
相手の話されている内容に積極的に耳を傾け、相手の方がイメージしやすいように相手に寄り添いながらペースを作ることを意識していただきながら取組んでいただきました。
次にグループ内で、インタビューした人の「他者紹介」を行いました。ここではその人の素晴らしさを情景が浮かぶように伝えることを意識してもらいながら取組んで頂きました。

そしてインタビュー内容や他者紹介を受けてのグループ内での強みを、「質より量」を重要視して出して頂きました。出た意見は必ず「いいねー」と言ってもらい否定をしないような場づくりで行って頂きました。
一番多くの意見を出したグループには参加者全員からの「思いきり拍手」が送られました!
○内省
その後、個人で今日受けた講義やワークを自分の中で振り返ってもらう「内省」の時間が設けられ、参加者一人一人が自分の中での気付きや印象に残ったキーワードを自分の中に落とし込んでいただきました。そして再度インタビュー形式でお互いに聞き合ってもらい振り返りを行っていただきました。
○チェックアウト
最後は全体で3つのグループに分かれ、今日の気付きや感想といった振り返りを1人1人に発表して頂く「チェックアウト」を行いました。
そして参加者全員が参加者全員に向けた「思い切り拍手」で今回のヒムカレッジは締め括られました。

ご参加頂いた皆様からは、
「自身の話の聴き方を改めたいと思いました。相手に寄り添って内容より心に重視して見たいと思います。」
「場をつくるためには、相手の雰囲気・声・表現に寄り添うことがたいせつだということに気づきました」
「会議のスタイルに取り入れていきたいと思ってます。」
「ファシリテーションの講座をまたやってほしい!」
といったご感想をいただきました!
前回の長友まさ美さんを講師に迎えて開催したモチベーションアップのヒムカレッジにも通じる、
相手に好奇心・好感をもって“「聴く(傾聴する)」ということの大切”さや“関係性の大切さ”がファシリテーションのスキルにも重要だということを改めて実感させられた今回のヒムカレッジでした。
また中島さんが実際に参加者の皆さんの「円」の中に入り、参加者と対話しながら進めていく場面もあり、
とてもリラックスした雰囲気の中、参加者の皆様には参加して頂けたのではないかと感じました。
今回も多くの方にご参加頂き、いつも以上に年齢層も幅広く、改めてファシリテーションスキルが今求められてるものなのだなと感じました(*´∀`*)
参加していただいた皆様、そして講師の中島さん、本当にありがとうございました!
11月1日(日)に、日本電気マネジメントパートナー株式会社人材開発サービス事業部エグゼクティブコンサルタント/NPO法人はたらく場研究所~最高の居場所~代表理事/一般社団法人組織共創アカデミー代表の中島崇学さんをお招きし、今年度4回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
中島 崇学 氏
日本電気マネジメントパートナー株式会社
人材開発サービス事業部エグゼクティブコンサルタント
NPO法人はたらく場研究所~最高の居場所~代表理事
一般社団法人組織共創アカデミー代表
NECでは人事や広報を歴任し、海外勤務を経て、
現在、組織開発や人材育成業務に携わる。
NRC社内では、「3,000 人の対話集会」をはじめとする
組織開発の経験を積み、社外でもNPOや人材育成組織を
立ち上げ、パラレルキャリアで広く組織風土改革や
ファシリテーター養成を推進する。
著書として、
『私が会社を変えるんですか?』(日本能率協会マネジメント
センター)がある。(本間正人氏と共著)
----------------------------------------------------------------------------
当日は、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など幅広い年代層の41名の方々にご参加いただきました。
今回はそのワークショップの形式から参加者一同が円となる形で始まりました。

参加者同士の対話を中心としたワークショップを体験しながら、
「あり方(自分を知る)」×「関係性(参加者との関係性)」×「スキル・ツール(場のデザ
インスキル)」というファシリテーションに大切な要素を学んでいただきました!
●グランドルール
まず始めに今回の様々なワークショップを行う上でのグランドルールが提示されました。今回はこの4つ。
・守秘義務
・相互サポート
・失敗を祝福する
・誰も間違っていない(小さな声も尊重する)

一見、ルールを決めると発言が制限されてしまうのではと思ってしまいますが、
ワークショップや会議の場ではこの様なルールを決めることで、話しにくい雰囲気や声の大きな人の存在など、みんなが話し易い場を阻害する要因を取り除く事ができスムーズに議論に入ることができるということでした。
また、「今思っていること」「今感じていること」を大切にし、それらをセッションごとに振り返ることで体験を知恵に昇華させることができると中島さんは話されました。
ここで導入となるワークへ。
「今日は私、運がいいんですよ。なぜなら・・・」という言葉の後に自分自身にとって今日感じた運がいいことを参加者同士で発表し合っていただきました。

「運がいいこと」を考えて頭がプラス思考になると同時に、実際に立って動くことで緊張が一気にほぐれました。
○チェックイン
ここで、3グループに分かれ
「名前・仕事の近況・プライベートの近況など」と
「「今の正直な気持ち」や「気になっていること」」を話してもらうチェックインが行われました。

中島さんは会議の場ではすぐに議題に入らずにこのチェックインを行うそうです。
その理由は、今”、自分にある気がかりを話し、気がかりを言葉に出して置いておくことで、場に溶け込む効果があったり、今”、の気持ちに関して嘘のない素直な発言をすることにより、お互いの背景を理解し合い、人間関係の質の向上につながる効果があるからということでした。
チェックインが終わりここでファシリテーターについて話されました。
辞書によると、
「促進する人」、「容易にする人」、「司会者」、「目標達成のための準備を手伝う人」とありますが、もっと具体的に言うと
会議の参加者が「問題解決者・創造者」だとすると、ファシリテーターは「問題解決・創造を導く人」であり、「バラバラの参加者がゴールに向かうのを臨機応変にサポートする黒子」のような存在だということでした。
そして場にファシリテーションが用いられることにより、
参加者がプロセスよりも内容に集中することができたり、参加者同士のチーム団結力や会議の効率性が高まるなどの利点があるということでした。
また今なぜファシリテーションが求められているかについては、
昔に比べ、今は、個人より「本当に社会を良くすることに向かって、みんなで一緒に考え、自分事で行動し続けることが大切な時代。」になってきているからだと中島さんは話されました。
○傾聴
ここで二人組みになってもらい、対面での緊張をなくすため90度ずれた形でワークへ。

話し手は「最近、感情が動いたこと」を話し、聞き手は相手の気持ちを察しながら、その気持ちに寄り添って聴き、感情の奥にあるニーズをつかみとれたらフィードバックする、というワークを行いました。
特に聞き手には「傾聴」することを念頭に取り組んでいただきました。
「傾聴する」とは
・目と体を向けて相手に集中する(言葉以外のメッセージも重要)
・好奇心、共感を持って聞く
傾聴のポイントとしては
・あいづち・・・相手の話に相槌を打ったり、表情や態度で反応する
基本的にはハ行 「なるほど」「おっしゃるとおりですね」などもある
・うなずき・・・相手の話を聴きながらうなずく
・繰り返し・・・「いつも細かな注文が多くてこまっちゃうんですよ」
⇒ 「細かな注文が多いんですね」
この3つをうまく使うことが大切だということでした。
短い会話でも聴き方を変えるだけで、お互いの親密度も増しているようでした。
特に気持ちを察する、共感する、受け止める。(内容はあまり考えない)「感情傾聴」が場をデザインしていくためには必要だということでした。
○YES AND
続いてコミュニケーションを行う上で相手を傷つけずに気持ちを伝える手法「YES AND」

「いいや違う」「私の思っていることはこうだ」とという「NO BUT」や、
「だけど」「しかし」「でもね」を使った「YES BUT」の返答や会話になってしまう方が多いのではないでしょうか?
しかし、共創の雰囲気作りやアイデアの収穫、接点を探るという、いい場をデザインするためにはこの「YES AND」が効果的だということでした。
ポイントは、
☆そして
☆さらに
☆加えて言うと
☆ならば
☆だとすれば
といった接続詞を使うことで、相手の言葉に光を当てながら自分の意見を乗せていくことが出来、いい場づくりにもつながるということでした。
ここで3人組みになってのワークへ。
「YES AND」を意識しながら「宝くじが一億円当たったので3人で使い道を考える」といったテーマで話し合っていただきました。

このYES ANDを意識することで、とてもいい雰囲気ができ自然と皆さんも笑顔になっておりました。
○AI
ありたい姿に対する想い・意志に焦点をあて積もる感情や主観を見極めた課題の抽出を行うポジティブアプローチの中でも代表的なAIというツールを使ったインタビュー形式のワークへ。
AIは、appreciative Inquiryの略語で、
Appreciativeとは、肯定的
動詞Appreciateのもつ2つの意味
①認識する行為(強み、健全さ、生命力、最善の状態)
②価値をさらに高める行為
Inquiryとは、
①探求すること
②発見すること
③問いかけること
「あなたの素晴らしい体験」と「あなたにとっての宮崎」といった2つのテーマでお互いにインタビューを行って頂きました。
相手の話されている内容に積極的に耳を傾け、相手の方がイメージしやすいように相手に寄り添いながらペースを作ることを意識していただきながら取組んでいただきました。
次にグループ内で、インタビューした人の「他者紹介」を行いました。ここではその人の素晴らしさを情景が浮かぶように伝えることを意識してもらいながら取組んで頂きました。

そしてインタビュー内容や他者紹介を受けてのグループ内での強みを、「質より量」を重要視して出して頂きました。出た意見は必ず「いいねー」と言ってもらい否定をしないような場づくりで行って頂きました。
一番多くの意見を出したグループには参加者全員からの「思いきり拍手」が送られました!
○内省
その後、個人で今日受けた講義やワークを自分の中で振り返ってもらう「内省」の時間が設けられ、参加者一人一人が自分の中での気付きや印象に残ったキーワードを自分の中に落とし込んでいただきました。そして再度インタビュー形式でお互いに聞き合ってもらい振り返りを行っていただきました。
○チェックアウト
最後は全体で3つのグループに分かれ、今日の気付きや感想といった振り返りを1人1人に発表して頂く「チェックアウト」を行いました。
そして参加者全員が参加者全員に向けた「思い切り拍手」で今回のヒムカレッジは締め括られました。

ご参加頂いた皆様からは、
「自身の話の聴き方を改めたいと思いました。相手に寄り添って内容より心に重視して見たいと思います。」
「場をつくるためには、相手の雰囲気・声・表現に寄り添うことがたいせつだということに気づきました」
「会議のスタイルに取り入れていきたいと思ってます。」
「ファシリテーションの講座をまたやってほしい!」
といったご感想をいただきました!
前回の長友まさ美さんを講師に迎えて開催したモチベーションアップのヒムカレッジにも通じる、
相手に好奇心・好感をもって“「聴く(傾聴する)」ということの大切”さや“関係性の大切さ”がファシリテーションのスキルにも重要だということを改めて実感させられた今回のヒムカレッジでした。
また中島さんが実際に参加者の皆さんの「円」の中に入り、参加者と対話しながら進めていく場面もあり、
とてもリラックスした雰囲気の中、参加者の皆様には参加して頂けたのではないかと感じました。
今回も多くの方にご参加頂き、いつも以上に年齢層も幅広く、改めてファシリテーションスキルが今求められてるものなのだなと感じました(*´∀`*)
参加していただいた皆様、そして講師の中島さん、本当にありがとうございました!
2015年10月27日
「ヒムカレッジ2015 vol.3」開催しました!
9月26日(土)に、サンワード・ラボ株式会社 代表取締役/「宮崎てげてげ通信」会長の長友 まさ美さんをお招きし、今年度第3回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
長友 まさ美 氏
サンワード・ラボ株式会社 代表取締役
「宮崎てげてげ通信」会長
起業から5 年間で延べ400 人以上、2000 時間以上のセッション
を行い、クライアントは、経営者、起業家、アーティスト、政治家、
教師、会社員、同業のコーチ等、多岐にわたる。
「経営もスタッフもいきいきと幸せにはたらく会社づくり」を
テーマに企業研修、チームビルディング等を実施。その活動は、
宮崎県内にとどまらず、日本全国に広がる。
また、人材育成、組織開発の手法を地域づくりにも活かし、キー
パーソン育成、新商品開発WS、まちづくりWS などを開催。
日本一のローカルウェブメディア「宮崎てげてげ通信」会長で
もある。
「サンワード・ラボ株式会社」(http://sunward-lab.com/)
「宮崎てげてげ通信」(http://visit.miyazaki.jp/)
----------------------------------------------------------------------------
当日は、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など32名の方々にご参加いただきました。
また今回はワークショップが中心となるため、あらかじめグループが作られた状態での講座となりました。

今回は躍進するテゲツーチームのお話を交えながら、参加者同士でモチベーションアップにつながるワークショップを行っていく内容のヒムカレッジとなりました。
●強いチームを作る
長友さんが代表を務めるサンワード・ラボ株式会社では「強いチームづくり」の為にチームビルディングの支援や本当に自分のありたい姿になる為のコミュニケーション手法コーチングを使った支援を行い社会問題を解決するなどの活動を行っております。
そして、チームづくりの支援だけでなく、自分のチームを作って世の中に価値を生むプロジェクトも行っており、その中の一つが宮崎てげてげ通信というローカルWEBメディアです。
人と人をつなげ、宮崎県を豊かにする!
そんなヴィジョンを掲げるテゲツーは、
スタートから一年半で月間50万PVを達成するなど、急速に成長し続けています。
★ヤフーニュースに掲載された記事
「ローカルメディア日本一を目指す「宮崎てげてげ通信」。野望は商店街の買い占め」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/fujisiro/20150709-00047200/
●個々のやりたいことを大事にする
自分のやりたいことを行う為には、昇給やペナルティなどからくる外発的動機づけよりも、
やりたい!わくわくといった想いの源泉からくる「内発的動機づけ」が重要だと話す長友さん。
本業の傍ら活動を行うテゲツーのメンバーも、
自分のやりたいことを形にする内発的な動機がチームを動かす原動力になっているということでした。
ここで最初のワークショップへ。
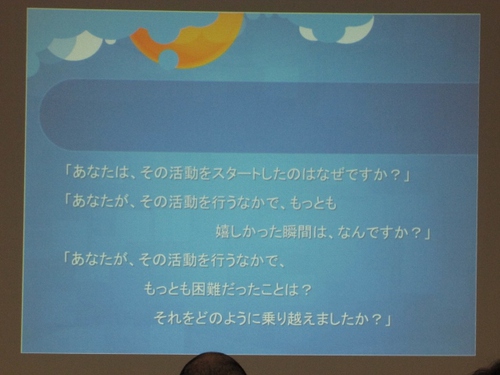
二人組みになってもらい、
「あなたは、その活動をスタートしたのはなぜですか?」
「あなたが、その活動を行うなかで、もっとも嬉しかった瞬間は、なんですか?」
「あなたが、その活動を行うなかで、もっとも困難だったことは?それをどのように乗り越えましたか?」といった質問を
お互いにインタビューしていただきました。
一般的には、
話し上手=コミュニケーション能力が高いとされがちですが
、実は相手に好奇心を持ち話しやすい雰囲気をつくる「聴き上手」になることこそが
コミュニケーションには大事だということでした。
インタビュアー側になった人は「聴き上手」になることに意識を持っていただきながらワークを行っていただきました。


次に先程の2人組を2組合わせ4人1組になってペアだった人のことを紹介する「他己紹介」を行いました。
ここでも紹介する人が話しやすい場づくりと、紹介される人の素晴らしさや良い所をちゃんと聞く意識をもっていただきながら行いました。
参加者の方から「自分が気付けていないような長所に気付くことができました。」という声が多く上がったほど自分以外じゃないと中々気付けない部分があることを感じるのと同時に、
人から良い所を言ってもらえる嬉しさがチームの関係性をより良いものにしていくのだと感じたワークとなりました。

●違う才能を活かし合う
4人いるテゲツー編集部の中でも長友さんは自分の得意なコミュニケーション能力を活かした「つなげ役」としての役割を担っているということでした。
他の3人にもIT面や運営面、得意とする記事など様々な違う才能や好きなことがあり、それをテゲツーを通して一致させ、活かし合うことで、テゲツーチームは上手く機能しているのだと長友さんは話されました。
●関係性の質を上げる
ここではマサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提言する関係性の好循環モデルが紹介されました。

例えば、お店の売り上げが落ちたという時に私たちは、
セールをしようとか、DMを送ろうとか、行動を変えようとしますが、
いくら行動を変えても思考が変わらずに、
焦りからくる行動をしても上手く結果に結びつかないことが多いといいます。
そして結果に結びつかないと、あの部署が悪いんだとか、あの人に責任があるんだとか、人のせいにしてしまい関係性がギクシャクしてしまうという様なことになってしまいます。
そんなことにならない為には、一見遠回りのように思えますが、
お互いを助け合おうという姿勢と対話を通した「関係性の質」を上げることが必要だということでした。

そして長友さんがこれまで色んな組織やチームを見て来た中で、
強いチームには共通する3つの要素があったということでした。
・感謝
「ありがとう」などの感謝の言葉が飛び交っていること
・肯定的な言葉がけ
相手のアイデアや意見に対して「それは無理やろ」と否定するのではなく、「いいね」「それやろうよ」といった肯定的な言葉がけをしている
・まるごと認める
相手の足りない面や上手く出来ていないことも含めてまるごと認めること
●感謝のワーク
続いて関係性の質を上げるためにも重要な「感謝」することをテーマにしたワークへ。
グループ内で、自分が感謝していること(今の活動や仕事をやる上でチームの仲間の○○に感謝しているとか、活動をやっていく中でこんな成長が起きていて感謝しているなど)を出来るだけたくさん出してもらいました。
チームの中で日常的に「感謝」の言葉が出る関係性がとても重要で、その様な関係性を作ることがモチベーションアップに繋がっていくということでした。

●本質を悟り、「みんなごと」に
テゲツーでは月に1回編集部会議を行っており、
そこでは、(地域)課題についての想いや考えをそれぞれが持ち寄り、共有し対話することを行っていると話す長友さん。
そうした対話により、「じぶんごと」が「みんなごと」に変わっていき、チームの一体感が増していくということでした。
●本当にありたい未来を語る
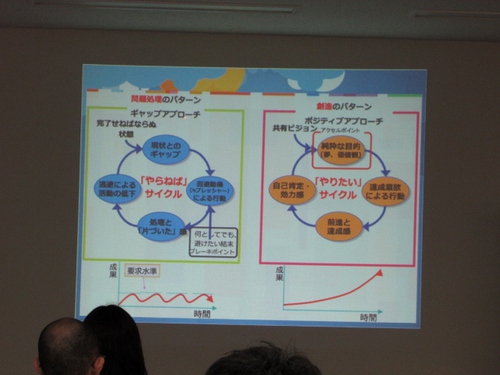
普段私たちは問題解決を念頭に置き現状とのギャップを回避する為に「やらねばサイクル」という、義務感・責任感での行動になりがちです。
しかしそれでは成果が上がってもモチベーションの維持に繋がらず「成り行きの未来」になってしまうということでした。
そうならない為には「こんな未来をつくりたい」という「ありたい未来」を実現する為の「やりたいサイクル」で行動していくことが重要だと長友さんは話します。
テゲツーはそんな「ありたい未来」をチーム全員で共有することによって、メンバー1人1人の自発的な行動やチームのモチベーションアップに繋がっているということでした。
そして、「あなたが創りたい未来は?」という問いかけから、
グループで「10年後の「宮崎」で創りたい未来」を考えるワークショップを行いました。


「質より量」を重視して、とにかく思いついたアイデアをたくさん書いていただきました。
そして出た意見は否定せず、肯定する姿勢を持つことを念頭に取組んで頂きました。

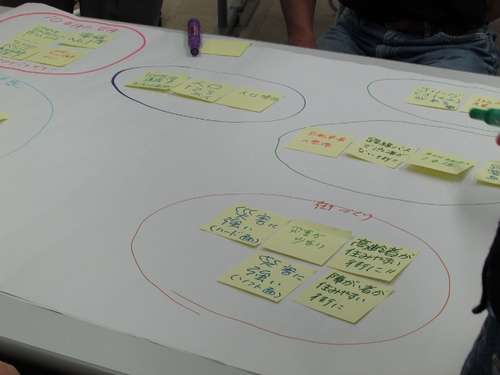
またアイデアは多様な人達と話すことでより広がっていくということで、
ホストとなる人以外のグループメンバーを途中でシャッフルし、
ホストとなった人は自分のグループで出た意見をシャッフルしたグループメンバーへ共有して頂きました。

自分たちの活動を自分たちのチームの中だけで喋ると視野が狭くなってしまう為、
どんどん外に発信していくことが大切で、そこから共鳴し仲間が増えていくことにも繋がると長友さんは話されました。
そして全員元のグループに戻り、
ホスト役の方に、シャッフル後の話し合いの中で出た意見を元のグループメンバーに共有して頂きました。


最後に、グループで出た意見の中でも「特にこれをやったら効果的だというアイデア」を2つと、「これはだぶんこのチームでしか出ていないようなユニークなアイデア」を1つ選び発表して頂きました。

ご参加頂いた皆様からは、
「ワークショップ形式で様々な人が集まってアイデアを出す事、リラックスした環境で出るアイデアの創造性を感じました。」
「関係性の質を上げるためのヒントとして会話の時間の大切さを学びました。」
「改めてチームビルディングや人と人とをつなぐ能力の高さを感じました。さすがは宮崎の太陽や!」
「素晴らしいです。宮崎でこんな内容のセミナーを聴けるとは思いませんでした。」
といったご感想をいただきました!
「『関係性の質を上げる』ことがモチベーションアップに繋がっていく。」ということを、
グループで意見やアイデアを出していく実践的なワークショップを行う中で、
参加者一人一人が体感していたような今回のヒムカレッジでした。
そして長友さんの言葉やエネルギーを受け、
今回の講座が参加者の皆様の仕事や様々な活動の原動力になったのではないかと強く感じました (●´∀`●)
長友さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
長友 まさ美 氏
サンワード・ラボ株式会社 代表取締役
「宮崎てげてげ通信」会長
起業から5 年間で延べ400 人以上、2000 時間以上のセッション
を行い、クライアントは、経営者、起業家、アーティスト、政治家、
教師、会社員、同業のコーチ等、多岐にわたる。
「経営もスタッフもいきいきと幸せにはたらく会社づくり」を
テーマに企業研修、チームビルディング等を実施。その活動は、
宮崎県内にとどまらず、日本全国に広がる。
また、人材育成、組織開発の手法を地域づくりにも活かし、キー
パーソン育成、新商品開発WS、まちづくりWS などを開催。
日本一のローカルウェブメディア「宮崎てげてげ通信」会長で
もある。
「サンワード・ラボ株式会社」(http://sunward-lab.com/)
「宮崎てげてげ通信」(http://visit.miyazaki.jp/)
----------------------------------------------------------------------------
当日は、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など32名の方々にご参加いただきました。
また今回はワークショップが中心となるため、あらかじめグループが作られた状態での講座となりました。

今回は躍進するテゲツーチームのお話を交えながら、参加者同士でモチベーションアップにつながるワークショップを行っていく内容のヒムカレッジとなりました。
●強いチームを作る
長友さんが代表を務めるサンワード・ラボ株式会社では「強いチームづくり」の為にチームビルディングの支援や本当に自分のありたい姿になる為のコミュニケーション手法コーチングを使った支援を行い社会問題を解決するなどの活動を行っております。
そして、チームづくりの支援だけでなく、自分のチームを作って世の中に価値を生むプロジェクトも行っており、その中の一つが宮崎てげてげ通信というローカルWEBメディアです。
人と人をつなげ、宮崎県を豊かにする!
そんなヴィジョンを掲げるテゲツーは、
スタートから一年半で月間50万PVを達成するなど、急速に成長し続けています。
★ヤフーニュースに掲載された記事
「ローカルメディア日本一を目指す「宮崎てげてげ通信」。野望は商店街の買い占め」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/fujisiro/20150709-00047200/
●個々のやりたいことを大事にする
自分のやりたいことを行う為には、昇給やペナルティなどからくる外発的動機づけよりも、
やりたい!わくわくといった想いの源泉からくる「内発的動機づけ」が重要だと話す長友さん。
本業の傍ら活動を行うテゲツーのメンバーも、
自分のやりたいことを形にする内発的な動機がチームを動かす原動力になっているということでした。
ここで最初のワークショップへ。
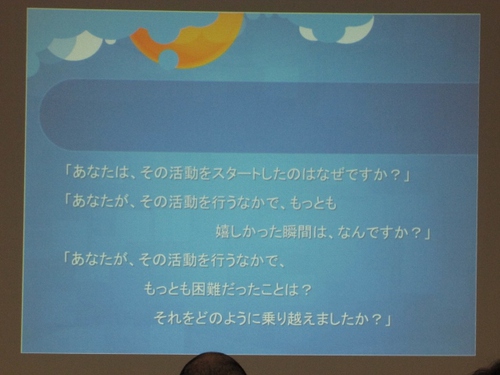
二人組みになってもらい、
「あなたは、その活動をスタートしたのはなぜですか?」
「あなたが、その活動を行うなかで、もっとも嬉しかった瞬間は、なんですか?」
「あなたが、その活動を行うなかで、もっとも困難だったことは?それをどのように乗り越えましたか?」といった質問を
お互いにインタビューしていただきました。
一般的には、
話し上手=コミュニケーション能力が高いとされがちですが
、実は相手に好奇心を持ち話しやすい雰囲気をつくる「聴き上手」になることこそが
コミュニケーションには大事だということでした。
インタビュアー側になった人は「聴き上手」になることに意識を持っていただきながらワークを行っていただきました。


次に先程の2人組を2組合わせ4人1組になってペアだった人のことを紹介する「他己紹介」を行いました。
ここでも紹介する人が話しやすい場づくりと、紹介される人の素晴らしさや良い所をちゃんと聞く意識をもっていただきながら行いました。
参加者の方から「自分が気付けていないような長所に気付くことができました。」という声が多く上がったほど自分以外じゃないと中々気付けない部分があることを感じるのと同時に、
人から良い所を言ってもらえる嬉しさがチームの関係性をより良いものにしていくのだと感じたワークとなりました。

●違う才能を活かし合う
4人いるテゲツー編集部の中でも長友さんは自分の得意なコミュニケーション能力を活かした「つなげ役」としての役割を担っているということでした。
他の3人にもIT面や運営面、得意とする記事など様々な違う才能や好きなことがあり、それをテゲツーを通して一致させ、活かし合うことで、テゲツーチームは上手く機能しているのだと長友さんは話されました。
●関係性の質を上げる
ここではマサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提言する関係性の好循環モデルが紹介されました。

例えば、お店の売り上げが落ちたという時に私たちは、
セールをしようとか、DMを送ろうとか、行動を変えようとしますが、
いくら行動を変えても思考が変わらずに、
焦りからくる行動をしても上手く結果に結びつかないことが多いといいます。
そして結果に結びつかないと、あの部署が悪いんだとか、あの人に責任があるんだとか、人のせいにしてしまい関係性がギクシャクしてしまうという様なことになってしまいます。
そんなことにならない為には、一見遠回りのように思えますが、
お互いを助け合おうという姿勢と対話を通した「関係性の質」を上げることが必要だということでした。

そして長友さんがこれまで色んな組織やチームを見て来た中で、
強いチームには共通する3つの要素があったということでした。
・感謝
「ありがとう」などの感謝の言葉が飛び交っていること
・肯定的な言葉がけ
相手のアイデアや意見に対して「それは無理やろ」と否定するのではなく、「いいね」「それやろうよ」といった肯定的な言葉がけをしている
・まるごと認める
相手の足りない面や上手く出来ていないことも含めてまるごと認めること
●感謝のワーク
続いて関係性の質を上げるためにも重要な「感謝」することをテーマにしたワークへ。
グループ内で、自分が感謝していること(今の活動や仕事をやる上でチームの仲間の○○に感謝しているとか、活動をやっていく中でこんな成長が起きていて感謝しているなど)を出来るだけたくさん出してもらいました。
チームの中で日常的に「感謝」の言葉が出る関係性がとても重要で、その様な関係性を作ることがモチベーションアップに繋がっていくということでした。

●本質を悟り、「みんなごと」に
テゲツーでは月に1回編集部会議を行っており、
そこでは、(地域)課題についての想いや考えをそれぞれが持ち寄り、共有し対話することを行っていると話す長友さん。
そうした対話により、「じぶんごと」が「みんなごと」に変わっていき、チームの一体感が増していくということでした。
●本当にありたい未来を語る
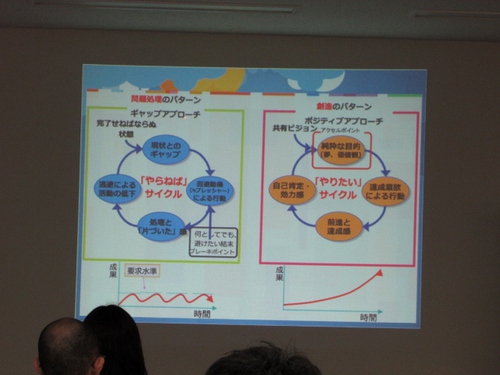
普段私たちは問題解決を念頭に置き現状とのギャップを回避する為に「やらねばサイクル」という、義務感・責任感での行動になりがちです。
しかしそれでは成果が上がってもモチベーションの維持に繋がらず「成り行きの未来」になってしまうということでした。
そうならない為には「こんな未来をつくりたい」という「ありたい未来」を実現する為の「やりたいサイクル」で行動していくことが重要だと長友さんは話します。
テゲツーはそんな「ありたい未来」をチーム全員で共有することによって、メンバー1人1人の自発的な行動やチームのモチベーションアップに繋がっているということでした。
そして、「あなたが創りたい未来は?」という問いかけから、
グループで「10年後の「宮崎」で創りたい未来」を考えるワークショップを行いました。


「質より量」を重視して、とにかく思いついたアイデアをたくさん書いていただきました。
そして出た意見は否定せず、肯定する姿勢を持つことを念頭に取組んで頂きました。

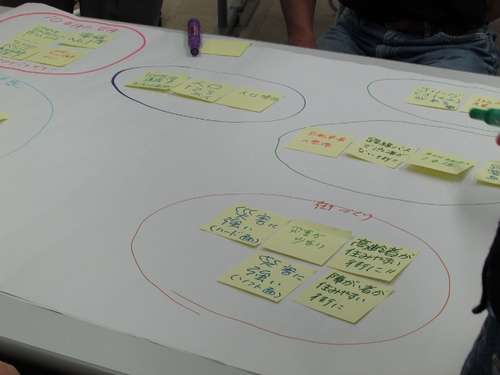
またアイデアは多様な人達と話すことでより広がっていくということで、
ホストとなる人以外のグループメンバーを途中でシャッフルし、
ホストとなった人は自分のグループで出た意見をシャッフルしたグループメンバーへ共有して頂きました。

自分たちの活動を自分たちのチームの中だけで喋ると視野が狭くなってしまう為、
どんどん外に発信していくことが大切で、そこから共鳴し仲間が増えていくことにも繋がると長友さんは話されました。
そして全員元のグループに戻り、
ホスト役の方に、シャッフル後の話し合いの中で出た意見を元のグループメンバーに共有して頂きました。


最後に、グループで出た意見の中でも「特にこれをやったら効果的だというアイデア」を2つと、「これはだぶんこのチームでしか出ていないようなユニークなアイデア」を1つ選び発表して頂きました。

ご参加頂いた皆様からは、
「ワークショップ形式で様々な人が集まってアイデアを出す事、リラックスした環境で出るアイデアの創造性を感じました。」
「関係性の質を上げるためのヒントとして会話の時間の大切さを学びました。」
「改めてチームビルディングや人と人とをつなぐ能力の高さを感じました。さすがは宮崎の太陽や!」
「素晴らしいです。宮崎でこんな内容のセミナーを聴けるとは思いませんでした。」
といったご感想をいただきました!
「『関係性の質を上げる』ことがモチベーションアップに繋がっていく。」ということを、
グループで意見やアイデアを出していく実践的なワークショップを行う中で、
参加者一人一人が体感していたような今回のヒムカレッジでした。
そして長友さんの言葉やエネルギーを受け、
今回の講座が参加者の皆様の仕事や様々な活動の原動力になったのではないかと強く感じました (●´∀`●)
長友さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
2015年09月06日
「ヒムカレッジ2015 vol.2」開催しました!
8月26日(水)に、塩尻市役所企画政策部企画課 シティプロモーション係 主任/ nanoda 代表の山田崇さんをお招きし、今年度第2回目となるヒムカレッジを開催いたしました!
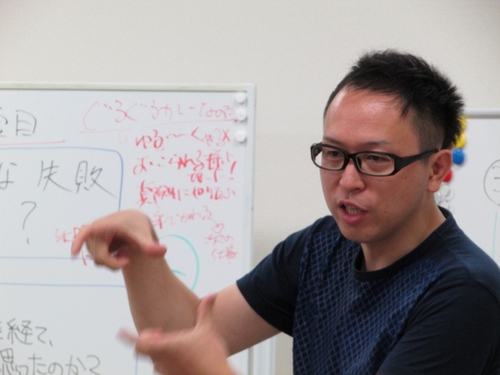
□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
山田 崇 氏
塩尻市役所企画政策部企画課
シティプロモーション係 主任
n a n o d a 代表
1975 年塩尻市生まれ。
千葉大学工学部応用化学科卒業。
「地域の課題を想像で捉えるのではなく、実際に住んでみないと商店街の現状・課題はわからない」と、地元塩尻の"大門商店街"に空き家を借り、可能な限り閉まってしまったシャッターを開ける。
そんな空き家/空き店舗を活用した「空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト nanoda(なのだ)」を2012 年 4 月より開始。
http://www.shiojiring.jp/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-nanoda/
http://inaka-pipe.net/coordinator/p15/
「公務員が元気なら、地域は絶対元気になる」と、その熱に巻き込まれたメンバーと共 に、nanoda を拠点に多様な活動を実施。
人と人、人と地域をつなげる。
○2014 年 1 月「地域に飛び出す公務員アウォード 2013」大賞を受賞。
http://t-k-award.sakura.ne.jp/2013/index.html
○TEDトークでの動画
「元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取組み」が話題に。
http://logmi.jp/23372
○空き家プロジェクト nanoda - Shiojiring シオジリング
当初は、塩尻市役所職員の有志が月1,000円を出し合って空き家を借りて、空き家の維持管理、
商店街の賑わい創出の様々な企画を実施。
shiojiring.jp
----------------------------------------------------------------------------
当日は、地域づくりに関わる方や会社員・公務員・大学生など、57名の方々にご参加いただきました。前回同様、定員数を越える参加者数となったため今回もスクール形式での開催となりました。

空き家プロジェクト「nanoda」 等の地域活性化につながる取り組みについて、また市の職員でありながらなぜアグレッシブに地域に入っていくことが出来るのか、活動する上での取り組み方や姿勢などについてもお話いただきました。
「あなたは今何をしているの?将来何をやっているの?」
2013年にカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したフランス映画「アデル、ブルーは熱い色」の劇中に出てくる台詞の紹介から講演はスタートしました。
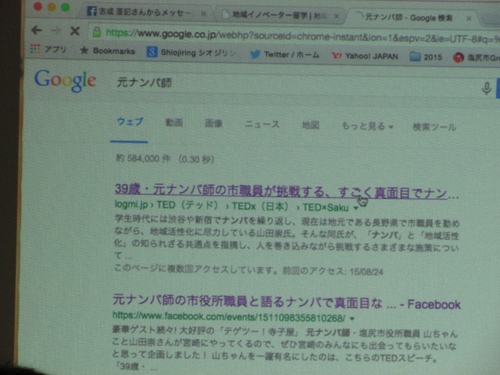
元ナンパ師でもある山田さん。
なんと今ではグーグル検索で「元ナンパ師」で検索するとトップに山田さんを紹介したページ(「39歳・元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取り組み」http://logmi.jp/23372)が出てくるのです!会場からも大きな笑い声が響いておりました笑
(講演前日、東京でイベントだった山田さん。参加者から「僕、白いペンギン持ってます!」と言って実際に白いペンギンの置物?ぬいぐるみ?を持ってこられた方が!白いペンギンについての詳細はコチラの動画をご覧ください⇒https://www.youtube.com/watch?v=oFX8XWcm0EA)
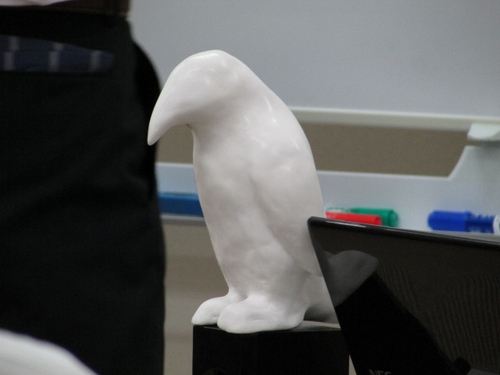
〇剛力彩芽とひざ神フルーツポンチ村上を塩尻に呼ぶ
長野県塩尻市は人口6万7千人。
いつもは人通りの少ない中心市街地。
そこで行われるハロウィンイベントに昨年、剛力彩芽を呼び、例年7000人程の参加者が2万人に。
(https://www.youtube.com/watch?v=AhVPNZ2XcNI)
きっかけは山田さんが今年の3月まで勤めていた商工会議所のある議員が6年前から「a-nation」を塩尻でやりたいと言っていたことでした。
たまたまテレビ東京に友達のプロデューサーがいた山田さんは15分だけ打ち合わせをしに東京へ。すると前の打ち合わせが長引いており、待ち時間の間に紹介された方がたまたまavexの方でした。
その方へ塩尻で開催する祭りやイベントを紹介し、提案する中で元々オスカープロモーションで剛力彩芽を育てていた方だということが分かり、「剛力彩芽であれば10月ならスケジュール的に大丈夫」だと言われました。
有名タレントだということもあり、予算的に厳しかったそうですが補助金や「剛力彩芽が来るなら!」と商店街の人がお金を出してくれたり商工会議所の方々の力もあり、資金を集め、イベントは大成功を収めました。
今年の7月には短歌の街としても知られる塩尻市で、お笑いコンビ フルーツポンチの村上さん(村上さんは東京でも短歌のライブを行っているそうです)をゲストに招き、高校生向けの詠み会を開催しました。二回講演で100人ずつの参加がある程の大盛況だったそうです。
〇若者を応援する大人を地域に増やす
塩尻市は全国で二番目に早く「地方版総合戦略」を策定し、9年間で緩やかに人口を減らしていこうという人口ヴィジョンを掲げています。
2040年に全国的に896の自治体が消滅すると言われていますが、
そうならないために山田さんは「若者を応援する大人が多い地域は生き残っていく」と話されました。
また全国で人口が減る中、全国で移住定住のセクションは増え続け、移住・定住者を奪い合う現状に疑問を感じている山田さん。
とにかく生き残って行く地域になるには若者が挑戦できる、そしてその責任をとれる大人が増えることが必要だと仰っていました。
その為には「よく分からないことをまず大人が軽くやってみる」
現在、手がけている木質バイオマス発電所を使った持続可能な再生計画もそのひとつだということでした。
〇『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』
読書家の山田さん。きっかけは、
中学生の時に骨肉腫で1週間入院したときに読んだ村上春樹の「ノルウェイの森」そして、その作中で主人公が読んでいたスコット・フィッツジェラルドの作品の作品に出会い、それからこの2人の作者の本を読み続けてきたということでした。
そんなスコット・フィッツジェラルドが言った
『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』
この言葉から、地方が抱える課題も多様化して複雑化してきている現状があり、何か1つの事業で色んな課題を解決していくことが必要だと話されました。
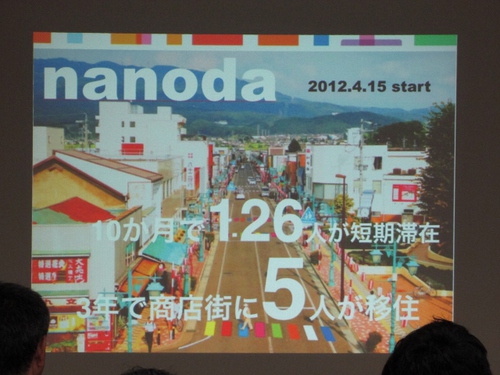
〇空き家プロジェクト「nanoda」のはじまり
5年前から始め、毎月行っている塩尻市の若手職員の勉強会。
目をキラキラ光らせやってくる職員がたくさんいるが全員が希望の部署に行けず、また仮に希望の部署に入っても3年経てば異動してしまう。片や商店街には若者がいない――
そんな状況を打破する為に、意欲のある若手職員が商店街に空き家を自分たちで自腹で借り、何か挑戦してみようという人材育成の為に空き家プロジェクト「nanoda」は始まりました。
『矛盾とは世界の発展の原動力である』
田坂広志さんの「未来を予見する「5つの法則」」に書いてある言葉から、
「営利」「非営利」どちらか一方とるのではなく、振り子の様に両方を考えることが重要だと話され、
一対一の個別学習など昔は寺子屋でやっていたものが今また求められるといいます。
「nanoda」にもこのような考え方を用いて活動しているということでした。
「塩尻市と宮崎市では地域の持つ課題が違い、宮﨑の中でも地区によって異なる課題がある。そんな状況の中で自治体の職員が住民に一番近い立場で地域の課題を紐解き解決する。
しかも一つの事業でいくつもの課題を解決していくことが必要。」山田さんはそう語ります。
2012年4月15日から「nanoda」はスタート
「nanoda」を始める前に市民活動のセクションを担当していた山田さんですがある会議の場で、市民活動団体の方に公開で怒られる程の大失敗をしてしまったことがあったそうです。
その時、なぜ自分が失敗したのかを考えると、
「自分自身が市民活動をしたことがなかった」
という結論に至りました。
そして以前から関心を持っていた、東京の田町にある「三田の家」(「大学の傍らにある、自主運営のラウンジ的な教室」を目指して、慶應義塾大学教員・(元)学生有志等と三田商店街振興組合が共同で運営するプロジェクト。2013年10月をもって閉家)に
塩尻から自分で交通費を出して東京に通い、閉家するまでの二年間、そこでの活動に参加しました。
「自分がやったことがないなら、自分でやってみる」
この行動力が山田さんのこれまでの活動の推進力になっているのだと感じたエピソードでした。
そして三田の家での活動を参考に、
最初はとりあえず空き家を借りてみて3ヶ月間、平日出勤前の7時~8時まで空けるということを行いました。
「何か街に変化が起きるんじゃないか」
結果、5年間で商店街に5人の移住者が生まれ、お風呂がない「nanoda」にも関わらず全国から多くの宿泊者が来るなど、
「何か面白いことをやっている街がある」という噂を聞きつけた人々が塩尻に来るようになり、少しづつ街にもいい変化が生まれたということでした。

〇積極的に補助金をとる
これまで9つの事業を新規で立上げた山田さんは、自治体の職員は積極的に補助金をとらないといけないと話します。
その理由に、
「地域にお金がおちるから」
「スタートアップが出来るから」
そして、
「300万円以上のソフトの事業なら行政であれば3年前から事業計画をつくり一年前に予算が決まるので、それから始めると本当に困っている人たちはいなくなってしまう。積極的に補助金は取って、すぐにでも事業を起こしていくスピードが今の時代には必要」ということを挙げられました。
○公務員が元気なら地域は元気になる
山田さんが雑誌などで取り上げられる際には特に自分から発している訳ではないのに、『公務員が元気なら地域は元気になる』という言葉が書かれるそうです。
「どんなに小さな自治体でも公務員はいる。公務員のいない地域はない。そんな中で公務員のやることはかなり変わって来ている」と話す山田さん。
「2000年4月に地方分権一括法が施行され、これまでは国が決めた施策を県を通して通達を受けて金太郎飴のような施策をやっていれば時代だったが、今は目の前にいる困っている人はそれぞれ違うので、自分たちで考えて施策を作っていかなければならない」
自分たちの地域のことを自分たちで考え、つくっていくことが、今の地方には必要なのだと感じました。
「図書館」「子育て支援・青少年交流」「シニア活動支援」「ビジネス支援」「市民活動支援」の5つの重点分野を機能融合させた「えんぱーく」という市民交流センターに関わる市民との協働の業務も担当していた山田さん。
その頃に前述した失敗があり、その時の経験から
「対面ではなく隣で同じ方向をみるということを、行政の職員も地域に飛び出して、関心のある地域課題を取り上げて自分のお金でやってみる。そこから何が困っていることかを考えて、行政がやれることをやらないといけない」ということを学んだということでした。

○50年続く自分のオリジナルの仕事
リンダ・グラットンの「ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図」から、
「ソニーやパナソニックなどの大企業が危うくなっている中で50年続く仕事はあるか。自治体も50年続くか分からない。
そんな中でコンピューターに取って代わられないアジアの安い賃金で取って代わられない貴方だけの仕事をつくることが必要」と話す山田さん。
元ナンパ師で、市役所の職員でありながら商工会議所の経験が3年あり、空き家のプロジェクトをやっている、そんな自分自身のキャリアを引き合いに出し、自分だけのキャリア・仕事を身につけていくこともこれから必要だということでした。
○まずやってみる。挑戦させてくれる上司の存在
山田さんのこれまでの活動には何でも挑戦させてくれる上司の存在があったことが大きいということでした。
商工会議所時代の会頭には「手柄は全部山田君のもの。失敗したら全部私のせいにいしなさい。とにかくやらなきゃわからないだろ」と言われ
更に「これから生まれてくる子どもの出来がいいか考えて作らないやつはいないだろ。とにかくやれ。生まれてくる子どもの出来がいいか悪いかは次の話」と冗談交じりに続けたそうですが、そんな上司の存在が山田さんの原動力に繋がったということでした。
えんぱーく建設の際にも「とにかく自分で考えて行動しろ。責任は俺がとる。一歩も踏み出せない職員ばっかりだ。自分で考えて一歩踏み出せ。一歩目、二歩目、三歩目。三歩目が俺が思っている方向と違っていたらそっと肩をたたいてやる。とにかくやれ。」と言ってくれる上司に恵まれたということでした。
○非営利でやるために大切なこと
P.F.ドラッカーの「非営利組織の運営に必要な3つのこと」から非営利組織の運営に大切な3つのことを学んだという山田さん。
・機会は、何か、ニーズは何か
・それはわれわれ向きの機会か、われわれの強みにあっているか
・問うべきは、心底価値を信じているか
この3つを念頭に置き「nanoda」を運営しているということでした。
○仕掛ける「nanoda」
一年間を通して行う高校生向けのアートのワークショップを行った際に、ある男子高校生と出会い、話をする中で、家庭に問題があり高校卒業後は家を出て友達の家とネットカフェを行き来しながら浪人をすると言うので、それだったらnanodaに住むようにと彼に伝えました。ただし朝7時~8時までは一緒にシャッターを開けることを条件に。
そうして高校生と2人でご飯を食べたりコーヒーを飲んだりする中で、
「これみんなでやったらどうだ」と思い、朝食nanodaという毎月1回、商店街で朝ごはんを食べるイベントを始めました。
そうやって商店街の中でイベントを行う上で、一つ大切にしているのが
「民間の方の邪魔をしない」ということでした。
商店街を盛り上げるためにも「nanoda」でお店を出して、既存店の売り上げが落ちるということは絶対にやってはいけないと感じた山田さん。
当時、朝食を出しているお店は商店街には一軒もなかったので朝食nanodaも開催出来たと話します。
また商店街にカレー屋が一軒もなかったので、喫茶店の方など商店街のお店の人にカレーを作ってもらい参加者に食べ歩きをしてもらおうという「ぐるぐるカレーなのだ!」というイベントも行っているということでした。
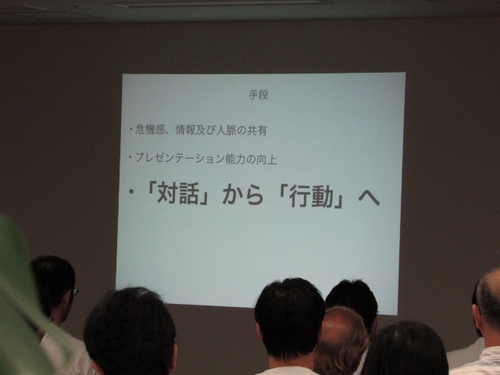
○「対話から行動へ」
「50年後の塩尻市が豊かであるために」というテーマで2011年の1月から勉強会をスタートさせた山田さん。
志の高い若い人が市役所に入ってくる中、そんな若手を上手く扱えない上司が多いことに問題を感じました。
前述した通りこれまでいい上司に恵まれたと話す山田さんは「人脈よりいい上司を共有する」ことが大切だと考えました。
そして、知識が増えたことや人脈が増えることで頭でっかちになりるよりも「必ず行動に移す」ということも大切だと感じていたそうです。
市民にも公開で行われた勉強会では結論や答えを出すことよりも、対話をすることに重きを置いて開かれました。
同時に必ずプロミスカードを書かせどんなに些細なこと(早起きする・歩いて出勤する・本を一冊買う)でもいいので、そこに書いたことを実行し「行動」につなげるということもやっていたということでした。
この対話を通じて、市の職員がフィールドで様々なプロトタイプが出来る場をつくることが「nanoda」の始まりにもなったということでした。
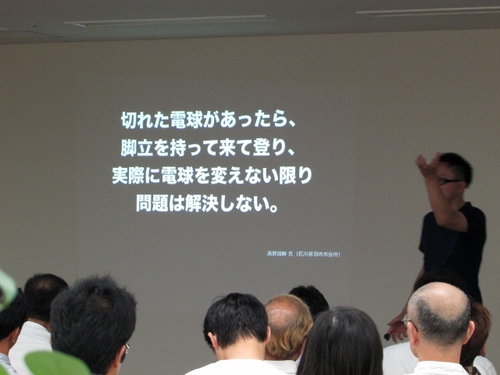
○『切れた電球があったら脚立を持ってきて登り、実際に電球を変えない限り問題は解決しない』
限界集落を蘇らせた、『スーパー公務員』として知られる高野誠鮮さんとワークショップを開いた際に、
「行政で何時間も会議をやっても意味はなく、そこに切れかけの電球(問題)があれば、実際に職員が行って電球を替えないと何も変わらない」という言葉が印象に残ったということでした。
また行動する時は全員がパイオニアでなくてもフォロワーとしてでもいいので出来れば誰かと一緒にやった方がいいと続ける山田さん。
『ひとりじゃ円陣組めない』
「nanoda」を始める時にも、空き家を借りることを聞きつけた先輩の職員が賛同して、
協力しながら始まっていった経緯もあったということでした。
「みなさん、やりましょう。時間だけが過ぎていってしまいます」
山田さんが力強く言ったその言葉がとても印象的でした。
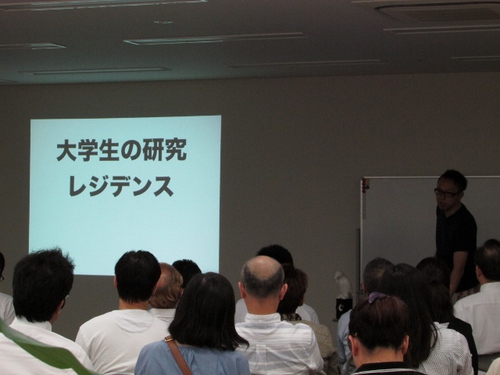
○若者の集まる街へ
今年は中央大学の大学生が研究の対象として滞在するなど、多くの大学生が集まるようになりました。
「若者を応援したいんだ」と発信しつづけた山田さんの声が全国の若者に届いているのだと強く感じました。
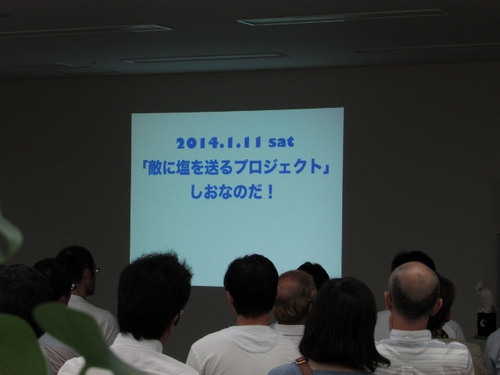
○「塩」を活かした仕掛け
塩尻という地名は日本海側と太平洋側からそれぞれ塩が運ばれて、ちょうど塩尻の辺りで両者が合流することから塩の道の終点=塩尻という説があるそうです。
また上杉謙信が武田信玄に塩を送った義塩伝説があり、その塩を送ったと言われる1月11日に合わせて、
敵に塩を送るプロジェクト「しおなのだ!」を開催。
全国から塩を送ってもらいお米やゆで卵などと塩との相性を確かめる試食会や塩ソムリエ講座を開催するなど、古くから地域に根付く塩文化をnanodaとかけ合せて、新しい塩文化の価値観を提示しました。
この他にも大門商店街(長野県塩尻市)と中四国のメンバーがオールナイトで商店街の魅力を日本中に発信するイベント「オールナイト商店街」など様々なイベントやプロジェクトをこれまで行ってきた山田さん。
「やりたい時にやってみましょう」
これまでの山田さんの活動を表すような力強い言葉で講演は終了しました。
★ワークショップ
ワークショップでは、グループ内での自己紹介から始まり、「講演会で、どんな学びや気づきがありましたか?」というテーマで話し合って頂き、山田さんへの質問を考えていただきました。

質疑応答では、
「仲間を集める時の口説き文句や秘訣は何ですか?」という質問に対して山田さんは「コアメンバーの場合は3人集める。3人いても思いや趣旨は違ってくるので一点を目指すのではなく同じ輪の中で活動していくイメージを持った方がいい。あとは大きな目標を設定すること。」とコメントされていました。

ご参加頂いた皆様からは、
「こういう行政職員が増えれば地域は活性化する!」
「上司にあきらめを覚えていましたが、塩を送る話を聞いて勇気がでました。」
「宮崎の商店街もシャッターがしまり、さみしい通りになっています。市が市民か取り組める方法のヒントがたくさんありました。1人ではできないけど仲間と共に何かやりたいですね。」
といったご感想をいただきました!
山田さんのこれまでの活動と姿勢、そして人を惹き付ける魅力と話術に、二時間半の時間があっという間に感じられるほど、講演もワークショップもとても密度の高い時間となりました(●´∀`●)
山田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
◎山田さんが講演の中で紹介された本・映画リスト
【映画】
アデル、ブルーは熱い色
【本】
イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」
安宅和人
未来を予見する「5つの法則」
田坂広志
SCHOOL OF DESIGN(スクール オブ デザイン)
水野 学
ノルウェイの森
村上春樹
スコット・フィッツジェラルドの作品
インテグレーティブ・シンキング
ロジャー マーティン
黒板とワイン―もう一つの学び場「三田の家」
坂倉杏介
ソトコト 2015年 3月号
TURNS(ターンズ) 2013年7月号 VOL.5
星の王子さま
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
その幸運は偶然ではないんです!
J.D.クランボルツ
ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図
リンダ・グラットン
トリツカレ男
いしい しんじ
ドラッカー名著集 4 非営利組織の経営
P.F.ドラッカー
未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語ればいいのだろう――震災後日本の「コミュニティ再生」への挑戦
野村恭彦
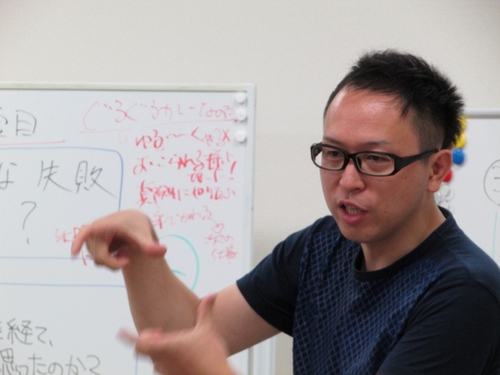
□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
山田 崇 氏
塩尻市役所企画政策部企画課
シティプロモーション係 主任
n a n o d a 代表
1975 年塩尻市生まれ。
千葉大学工学部応用化学科卒業。
「地域の課題を想像で捉えるのではなく、実際に住んでみないと商店街の現状・課題はわからない」と、地元塩尻の"大門商店街"に空き家を借り、可能な限り閉まってしまったシャッターを開ける。
そんな空き家/空き店舗を活用した「空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト nanoda(なのだ)」を2012 年 4 月より開始。
http://www.shiojiring.jp/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-nanoda/
http://inaka-pipe.net/coordinator/p15/
「公務員が元気なら、地域は絶対元気になる」と、その熱に巻き込まれたメンバーと共 に、nanoda を拠点に多様な活動を実施。
人と人、人と地域をつなげる。
○2014 年 1 月「地域に飛び出す公務員アウォード 2013」大賞を受賞。
http://t-k-award.sakura.ne.jp/2013/index.html
○TEDトークでの動画
「元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取組み」が話題に。
http://logmi.jp/23372
○空き家プロジェクト nanoda - Shiojiring シオジリング
当初は、塩尻市役所職員の有志が月1,000円を出し合って空き家を借りて、空き家の維持管理、
商店街の賑わい創出の様々な企画を実施。
shiojiring.jp
----------------------------------------------------------------------------
当日は、地域づくりに関わる方や会社員・公務員・大学生など、57名の方々にご参加いただきました。前回同様、定員数を越える参加者数となったため今回もスクール形式での開催となりました。

空き家プロジェクト「nanoda」 等の地域活性化につながる取り組みについて、また市の職員でありながらなぜアグレッシブに地域に入っていくことが出来るのか、活動する上での取り組み方や姿勢などについてもお話いただきました。
「あなたは今何をしているの?将来何をやっているの?」
2013年にカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したフランス映画「アデル、ブルーは熱い色」の劇中に出てくる台詞の紹介から講演はスタートしました。
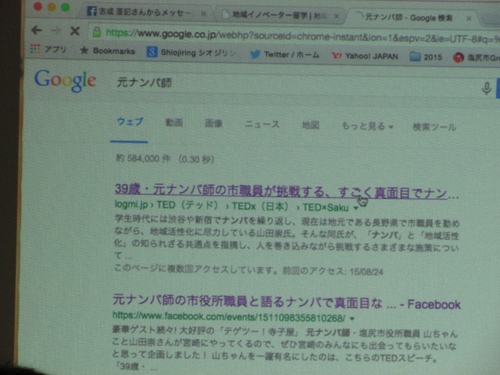
元ナンパ師でもある山田さん。
なんと今ではグーグル検索で「元ナンパ師」で検索するとトップに山田さんを紹介したページ(「39歳・元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取り組み」http://logmi.jp/23372)が出てくるのです!会場からも大きな笑い声が響いておりました笑
(講演前日、東京でイベントだった山田さん。参加者から「僕、白いペンギン持ってます!」と言って実際に白いペンギンの置物?ぬいぐるみ?を持ってこられた方が!白いペンギンについての詳細はコチラの動画をご覧ください⇒https://www.youtube.com/watch?v=oFX8XWcm0EA)
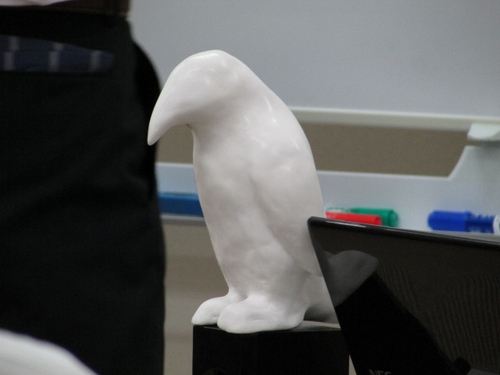
〇剛力彩芽とひざ神フルーツポンチ村上を塩尻に呼ぶ
長野県塩尻市は人口6万7千人。
いつもは人通りの少ない中心市街地。
そこで行われるハロウィンイベントに昨年、剛力彩芽を呼び、例年7000人程の参加者が2万人に。
(https://www.youtube.com/watch?v=AhVPNZ2XcNI)
きっかけは山田さんが今年の3月まで勤めていた商工会議所のある議員が6年前から「a-nation」を塩尻でやりたいと言っていたことでした。
たまたまテレビ東京に友達のプロデューサーがいた山田さんは15分だけ打ち合わせをしに東京へ。すると前の打ち合わせが長引いており、待ち時間の間に紹介された方がたまたまavexの方でした。
その方へ塩尻で開催する祭りやイベントを紹介し、提案する中で元々オスカープロモーションで剛力彩芽を育てていた方だということが分かり、「剛力彩芽であれば10月ならスケジュール的に大丈夫」だと言われました。
有名タレントだということもあり、予算的に厳しかったそうですが補助金や「剛力彩芽が来るなら!」と商店街の人がお金を出してくれたり商工会議所の方々の力もあり、資金を集め、イベントは大成功を収めました。
今年の7月には短歌の街としても知られる塩尻市で、お笑いコンビ フルーツポンチの村上さん(村上さんは東京でも短歌のライブを行っているそうです)をゲストに招き、高校生向けの詠み会を開催しました。二回講演で100人ずつの参加がある程の大盛況だったそうです。
〇若者を応援する大人を地域に増やす
塩尻市は全国で二番目に早く「地方版総合戦略」を策定し、9年間で緩やかに人口を減らしていこうという人口ヴィジョンを掲げています。
2040年に全国的に896の自治体が消滅すると言われていますが、
そうならないために山田さんは「若者を応援する大人が多い地域は生き残っていく」と話されました。
また全国で人口が減る中、全国で移住定住のセクションは増え続け、移住・定住者を奪い合う現状に疑問を感じている山田さん。
とにかく生き残って行く地域になるには若者が挑戦できる、そしてその責任をとれる大人が増えることが必要だと仰っていました。
その為には「よく分からないことをまず大人が軽くやってみる」
現在、手がけている木質バイオマス発電所を使った持続可能な再生計画もそのひとつだということでした。
〇『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』
読書家の山田さん。きっかけは、
中学生の時に骨肉腫で1週間入院したときに読んだ村上春樹の「ノルウェイの森」そして、その作中で主人公が読んでいたスコット・フィッツジェラルドの作品の作品に出会い、それからこの2人の作者の本を読み続けてきたということでした。
そんなスコット・フィッツジェラルドが言った
『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』
この言葉から、地方が抱える課題も多様化して複雑化してきている現状があり、何か1つの事業で色んな課題を解決していくことが必要だと話されました。
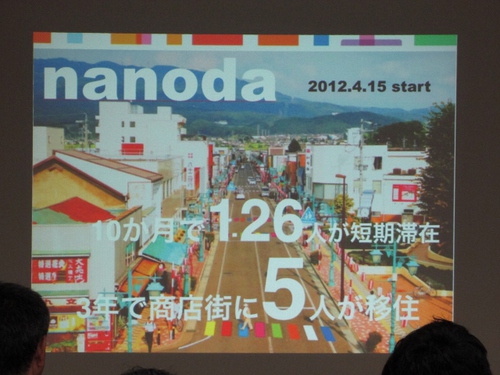
〇空き家プロジェクト「nanoda」のはじまり
5年前から始め、毎月行っている塩尻市の若手職員の勉強会。
目をキラキラ光らせやってくる職員がたくさんいるが全員が希望の部署に行けず、また仮に希望の部署に入っても3年経てば異動してしまう。片や商店街には若者がいない――
そんな状況を打破する為に、意欲のある若手職員が商店街に空き家を自分たちで自腹で借り、何か挑戦してみようという人材育成の為に空き家プロジェクト「nanoda」は始まりました。
『矛盾とは世界の発展の原動力である』
田坂広志さんの「未来を予見する「5つの法則」」に書いてある言葉から、
「営利」「非営利」どちらか一方とるのではなく、振り子の様に両方を考えることが重要だと話され、
一対一の個別学習など昔は寺子屋でやっていたものが今また求められるといいます。
「nanoda」にもこのような考え方を用いて活動しているということでした。
「塩尻市と宮崎市では地域の持つ課題が違い、宮﨑の中でも地区によって異なる課題がある。そんな状況の中で自治体の職員が住民に一番近い立場で地域の課題を紐解き解決する。
しかも一つの事業でいくつもの課題を解決していくことが必要。」山田さんはそう語ります。
2012年4月15日から「nanoda」はスタート
「nanoda」を始める前に市民活動のセクションを担当していた山田さんですがある会議の場で、市民活動団体の方に公開で怒られる程の大失敗をしてしまったことがあったそうです。
その時、なぜ自分が失敗したのかを考えると、
「自分自身が市民活動をしたことがなかった」
という結論に至りました。
そして以前から関心を持っていた、東京の田町にある「三田の家」(「大学の傍らにある、自主運営のラウンジ的な教室」を目指して、慶應義塾大学教員・(元)学生有志等と三田商店街振興組合が共同で運営するプロジェクト。2013年10月をもって閉家)に
塩尻から自分で交通費を出して東京に通い、閉家するまでの二年間、そこでの活動に参加しました。
「自分がやったことがないなら、自分でやってみる」
この行動力が山田さんのこれまでの活動の推進力になっているのだと感じたエピソードでした。
そして三田の家での活動を参考に、
最初はとりあえず空き家を借りてみて3ヶ月間、平日出勤前の7時~8時まで空けるということを行いました。
「何か街に変化が起きるんじゃないか」
結果、5年間で商店街に5人の移住者が生まれ、お風呂がない「nanoda」にも関わらず全国から多くの宿泊者が来るなど、
「何か面白いことをやっている街がある」という噂を聞きつけた人々が塩尻に来るようになり、少しづつ街にもいい変化が生まれたということでした。

〇積極的に補助金をとる
これまで9つの事業を新規で立上げた山田さんは、自治体の職員は積極的に補助金をとらないといけないと話します。
その理由に、
「地域にお金がおちるから」
「スタートアップが出来るから」
そして、
「300万円以上のソフトの事業なら行政であれば3年前から事業計画をつくり一年前に予算が決まるので、それから始めると本当に困っている人たちはいなくなってしまう。積極的に補助金は取って、すぐにでも事業を起こしていくスピードが今の時代には必要」ということを挙げられました。
○公務員が元気なら地域は元気になる
山田さんが雑誌などで取り上げられる際には特に自分から発している訳ではないのに、『公務員が元気なら地域は元気になる』という言葉が書かれるそうです。
「どんなに小さな自治体でも公務員はいる。公務員のいない地域はない。そんな中で公務員のやることはかなり変わって来ている」と話す山田さん。
「2000年4月に地方分権一括法が施行され、これまでは国が決めた施策を県を通して通達を受けて金太郎飴のような施策をやっていれば時代だったが、今は目の前にいる困っている人はそれぞれ違うので、自分たちで考えて施策を作っていかなければならない」
自分たちの地域のことを自分たちで考え、つくっていくことが、今の地方には必要なのだと感じました。
「図書館」「子育て支援・青少年交流」「シニア活動支援」「ビジネス支援」「市民活動支援」の5つの重点分野を機能融合させた「えんぱーく」という市民交流センターに関わる市民との協働の業務も担当していた山田さん。
その頃に前述した失敗があり、その時の経験から
「対面ではなく隣で同じ方向をみるということを、行政の職員も地域に飛び出して、関心のある地域課題を取り上げて自分のお金でやってみる。そこから何が困っていることかを考えて、行政がやれることをやらないといけない」ということを学んだということでした。

○50年続く自分のオリジナルの仕事
リンダ・グラットンの「ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図」から、
「ソニーやパナソニックなどの大企業が危うくなっている中で50年続く仕事はあるか。自治体も50年続くか分からない。
そんな中でコンピューターに取って代わられないアジアの安い賃金で取って代わられない貴方だけの仕事をつくることが必要」と話す山田さん。
元ナンパ師で、市役所の職員でありながら商工会議所の経験が3年あり、空き家のプロジェクトをやっている、そんな自分自身のキャリアを引き合いに出し、自分だけのキャリア・仕事を身につけていくこともこれから必要だということでした。
○まずやってみる。挑戦させてくれる上司の存在
山田さんのこれまでの活動には何でも挑戦させてくれる上司の存在があったことが大きいということでした。
商工会議所時代の会頭には「手柄は全部山田君のもの。失敗したら全部私のせいにいしなさい。とにかくやらなきゃわからないだろ」と言われ
更に「これから生まれてくる子どもの出来がいいか考えて作らないやつはいないだろ。とにかくやれ。生まれてくる子どもの出来がいいか悪いかは次の話」と冗談交じりに続けたそうですが、そんな上司の存在が山田さんの原動力に繋がったということでした。
えんぱーく建設の際にも「とにかく自分で考えて行動しろ。責任は俺がとる。一歩も踏み出せない職員ばっかりだ。自分で考えて一歩踏み出せ。一歩目、二歩目、三歩目。三歩目が俺が思っている方向と違っていたらそっと肩をたたいてやる。とにかくやれ。」と言ってくれる上司に恵まれたということでした。
○非営利でやるために大切なこと
P.F.ドラッカーの「非営利組織の運営に必要な3つのこと」から非営利組織の運営に大切な3つのことを学んだという山田さん。
・機会は、何か、ニーズは何か
・それはわれわれ向きの機会か、われわれの強みにあっているか
・問うべきは、心底価値を信じているか
この3つを念頭に置き「nanoda」を運営しているということでした。
○仕掛ける「nanoda」
一年間を通して行う高校生向けのアートのワークショップを行った際に、ある男子高校生と出会い、話をする中で、家庭に問題があり高校卒業後は家を出て友達の家とネットカフェを行き来しながら浪人をすると言うので、それだったらnanodaに住むようにと彼に伝えました。ただし朝7時~8時までは一緒にシャッターを開けることを条件に。
そうして高校生と2人でご飯を食べたりコーヒーを飲んだりする中で、
「これみんなでやったらどうだ」と思い、朝食nanodaという毎月1回、商店街で朝ごはんを食べるイベントを始めました。
そうやって商店街の中でイベントを行う上で、一つ大切にしているのが
「民間の方の邪魔をしない」ということでした。
商店街を盛り上げるためにも「nanoda」でお店を出して、既存店の売り上げが落ちるということは絶対にやってはいけないと感じた山田さん。
当時、朝食を出しているお店は商店街には一軒もなかったので朝食nanodaも開催出来たと話します。
また商店街にカレー屋が一軒もなかったので、喫茶店の方など商店街のお店の人にカレーを作ってもらい参加者に食べ歩きをしてもらおうという「ぐるぐるカレーなのだ!」というイベントも行っているということでした。
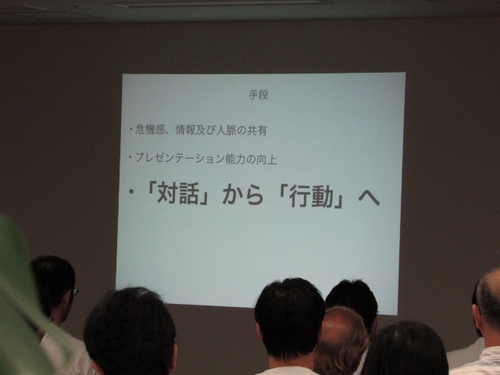
○「対話から行動へ」
「50年後の塩尻市が豊かであるために」というテーマで2011年の1月から勉強会をスタートさせた山田さん。
志の高い若い人が市役所に入ってくる中、そんな若手を上手く扱えない上司が多いことに問題を感じました。
前述した通りこれまでいい上司に恵まれたと話す山田さんは「人脈よりいい上司を共有する」ことが大切だと考えました。
そして、知識が増えたことや人脈が増えることで頭でっかちになりるよりも「必ず行動に移す」ということも大切だと感じていたそうです。
市民にも公開で行われた勉強会では結論や答えを出すことよりも、対話をすることに重きを置いて開かれました。
同時に必ずプロミスカードを書かせどんなに些細なこと(早起きする・歩いて出勤する・本を一冊買う)でもいいので、そこに書いたことを実行し「行動」につなげるということもやっていたということでした。
この対話を通じて、市の職員がフィールドで様々なプロトタイプが出来る場をつくることが「nanoda」の始まりにもなったということでした。
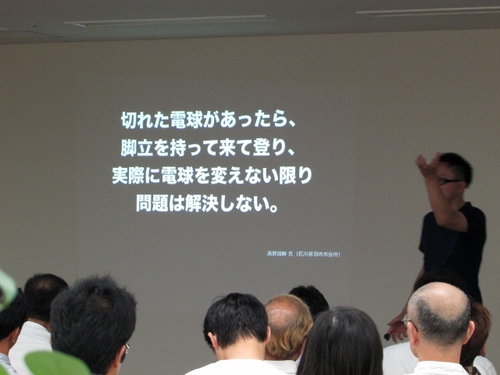
○『切れた電球があったら脚立を持ってきて登り、実際に電球を変えない限り問題は解決しない』
限界集落を蘇らせた、『スーパー公務員』として知られる高野誠鮮さんとワークショップを開いた際に、
「行政で何時間も会議をやっても意味はなく、そこに切れかけの電球(問題)があれば、実際に職員が行って電球を替えないと何も変わらない」という言葉が印象に残ったということでした。
また行動する時は全員がパイオニアでなくてもフォロワーとしてでもいいので出来れば誰かと一緒にやった方がいいと続ける山田さん。
『ひとりじゃ円陣組めない』
「nanoda」を始める時にも、空き家を借りることを聞きつけた先輩の職員が賛同して、
協力しながら始まっていった経緯もあったということでした。
「みなさん、やりましょう。時間だけが過ぎていってしまいます」
山田さんが力強く言ったその言葉がとても印象的でした。
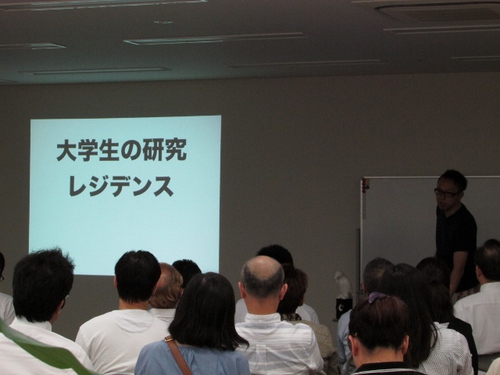
○若者の集まる街へ
今年は中央大学の大学生が研究の対象として滞在するなど、多くの大学生が集まるようになりました。
「若者を応援したいんだ」と発信しつづけた山田さんの声が全国の若者に届いているのだと強く感じました。
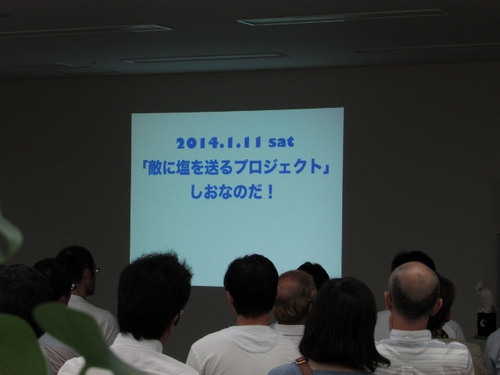
○「塩」を活かした仕掛け
塩尻という地名は日本海側と太平洋側からそれぞれ塩が運ばれて、ちょうど塩尻の辺りで両者が合流することから塩の道の終点=塩尻という説があるそうです。
また上杉謙信が武田信玄に塩を送った義塩伝説があり、その塩を送ったと言われる1月11日に合わせて、
敵に塩を送るプロジェクト「しおなのだ!」を開催。
全国から塩を送ってもらいお米やゆで卵などと塩との相性を確かめる試食会や塩ソムリエ講座を開催するなど、古くから地域に根付く塩文化をnanodaとかけ合せて、新しい塩文化の価値観を提示しました。
この他にも大門商店街(長野県塩尻市)と中四国のメンバーがオールナイトで商店街の魅力を日本中に発信するイベント「オールナイト商店街」など様々なイベントやプロジェクトをこれまで行ってきた山田さん。
「やりたい時にやってみましょう」
これまでの山田さんの活動を表すような力強い言葉で講演は終了しました。
★ワークショップ
ワークショップでは、グループ内での自己紹介から始まり、「講演会で、どんな学びや気づきがありましたか?」というテーマで話し合って頂き、山田さんへの質問を考えていただきました。

質疑応答では、
「仲間を集める時の口説き文句や秘訣は何ですか?」という質問に対して山田さんは「コアメンバーの場合は3人集める。3人いても思いや趣旨は違ってくるので一点を目指すのではなく同じ輪の中で活動していくイメージを持った方がいい。あとは大きな目標を設定すること。」とコメントされていました。

ご参加頂いた皆様からは、
「こういう行政職員が増えれば地域は活性化する!」
「上司にあきらめを覚えていましたが、塩を送る話を聞いて勇気がでました。」
「宮崎の商店街もシャッターがしまり、さみしい通りになっています。市が市民か取り組める方法のヒントがたくさんありました。1人ではできないけど仲間と共に何かやりたいですね。」
といったご感想をいただきました!
山田さんのこれまでの活動と姿勢、そして人を惹き付ける魅力と話術に、二時間半の時間があっという間に感じられるほど、講演もワークショップもとても密度の高い時間となりました(●´∀`●)
山田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
◎山田さんが講演の中で紹介された本・映画リスト
【映画】
アデル、ブルーは熱い色
【本】
イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」
安宅和人
未来を予見する「5つの法則」
田坂広志
SCHOOL OF DESIGN(スクール オブ デザイン)
水野 学
ノルウェイの森
村上春樹
スコット・フィッツジェラルドの作品
インテグレーティブ・シンキング
ロジャー マーティン
黒板とワイン―もう一つの学び場「三田の家」
坂倉杏介
ソトコト 2015年 3月号
TURNS(ターンズ) 2013年7月号 VOL.5
星の王子さま
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
その幸運は偶然ではないんです!
J.D.クランボルツ
ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図
リンダ・グラットン
トリツカレ男
いしい しんじ
ドラッカー名著集 4 非営利組織の経営
P.F.ドラッカー
未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語ればいいのだろう――震災後日本の「コミュニティ再生」への挑戦
野村恭彦
2015年07月31日
「ヒムカレッジ2015 vol.1」開催しました!
7月26日(日)に、パワープレイス株式会社 シニアディレクター プロダクトデザイナーの若杉浩一さんをお招きし、今年度第1回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
若杉 浩一 氏
パワープレイス株式会社 シニアディレクター プロダクトデザイナー
1959年生まれ 熊本県天草郡出身
1984年九州芸術工科大学芸術工学部工業設計学科卒
同年株式会社内田洋行入社、デザイン、製品企画、
知的生産性研究所 テクニカルデザインセンター、を経て
内田洋行のデザイン会社 パワープレイス株式会社にて
リレーションデザインセンター設立、同部門シニアディレクター
東京芸術大学美術学部非常勤講師
企業の枠やジャンルの枠にこだわらない活動を行う
やりすぎてデザイナーを首になるも性懲りもなく、企業と個人、社会の接点を模索している。
スチール家具メーカなのに何故か、日本全国スギダラケクラブを南雲勝志氏と設立。
ドイツIF賞、DESIGNPLUS特別賞受賞、全国都市再生まちづくり会議2007にて2007年度まちづくり大賞をスギダラケ倶楽部にて受賞
----------------------------------------------------------------------------
当日は、地域づくりに関わる方や大学生など、幅広い世代の45名の方々にご参加いただきました。当初予定してた定員数を越える参加者数となったため今回はスクール形式での開催となりました。

「杉」という地域資源を活用し人・地域・企業をつなげる取り組みや、若杉さんのこれまでの経歴や仕事に対する姿勢など盛りだくさんの内容をお話頂きました。
○田舎の人間関係が嫌いだった
熊本県の天草出身の若杉さん。
現在の人柄からは想像できませんが、子どもの頃は近所づきあいや日常的に濃い人間関係が苦手だったそうです。
また山の中での環境で育った為、子どもの頃からよく山へ草刈などに行っており、その頃から山の美しさと同時に厳しさを体感していたということでした。
○デザインの仕事へ
大学卒業後、若杉さんは株式会社内田洋行に入社しデザイナーとして数々のヒット商品を生み出しました。
しかし、「やってもやっても面白くない。先が見えないし、豊かな感じがしない」と思い始めた若杉さん。
とにかく売れるものや利益を優先した営業方針に疑問を覚え始め、自分が本当に売りたい商品を作ることが出来なかったといいます。
また会社の中でのデザイナーの立ち位置も厳しく、上手くいけば持て囃されるが、ダメなときにはすぐにチームが解体されるような状況だったということでした。
その頃はとにかく「谷あり底あり」の人生だったそうです。
○デザイナーをクビになり社内の職務を転々とした30代。
しかし、とうとうデザイナーをクビになり、OLさんと一緒にコピーをとったり会議室の予約などの内務の仕事をやったりと、
うだつの上がらない日々を過ごした30代。
そんな頃、若杉さんの師匠である家具プロデューサーの鈴木恵三さんから声がかかり、鈴木さんの会社の仕事を手伝い始めました。
そこは日本を代表するデザイナーが仕事をする環境で、普段デザインの仕事が出来ない状況もあり、
そこに行くと「デザインと繋がっている」と感じられ、とてもいい刺激になったそうです。
また鈴木さんに言われた「企業デザイナーはやめるな。日本のデザイナーは世界に通じる腕前を持っている。しかしそれが欧米に叶わないのはなぜかというと、デザインを流通させる企業側が非力だからだ。だからお前は企業側にいてデザインを強くしろ」という言葉から大きな力をもらい絶対にやめないことを若杉さんは決意しました。

○40代になり再びデザイナーの世界へ。そしてスギダラケ倶楽部の始動。
再びデザイナーとしての仕事を始めた若杉さんは、
利益の為のデザインではなく「楽しくかっこいいこと」をデザインでやりたいという思いからスギダラケ倶楽部の活動を始めました。
また自分のふるさとや地域、その中にある林業ががどんどん衰退していく状況に危機感を感じていた為、
「デザインの力で町を再生させることが出来るのではないか」と若杉さんは考え、そのこともスギダラケ倶楽部を始めるきっかけになりました。
日本全国スギダラケ倶楽部は現在、会員1800名。17支部あり、全国で活動が行われています。
戦後の植林によって杉だらけになってしまった日本の山林をやっかいもの扱いせず、材木としての杉の魅力 をきちんと評価し、産地・加工者・流通・デザイン・販売など杉を取り囲むシステムを結びつけることで、杉をもっと積極的に活用していく運動を行っています。
設立から14年経った現在でも活動が続いている理由を若杉さんは、女性の会員の力が大きいと言います。
元々男性の多い林業界なので、女性の視点や支援は活動の潤滑油になり継続的な活動には必要だということでした。

○世の中に広まっていくデザインとしての兆しが見えた「杉太」
若杉さんと一緒にスギダラケ倶楽部として活動を行う南雲勝志さんがデザインしたイス「杉太」
一本2000円の角材にステンレスの脚がついただけのとてもシンプルなイスを見た瞬間に、これは未来のデザインとして世に広まることを確信した若杉さん。
一本2000円程の角材にわずかなプロダクトをつけだけで2万円に。全国どこにでもある角材に企業のプロダクトがデザインで結ばれる「地域と企業がデザインで結ばれる」ことによって新しい価値が生まれ2000円が2万円の価値になるマジックに確かな手応えを感じていました。
若杉さんは「杉太」を会社で販売しようと話を持ちかけましたが取り合ってもらえず、「木目や色がバラバラになってしまうような商品は売れないし傷もつくし割れるしクレームの塊だ」と一蹴されてしまいます。
しかし「エンドユーザーは絶対に喜んでくれるし、地域の方も喜んでくれる」と確信を持っていた若杉さんは自分たちで自給自足的に販売を始めました。結果的に「杉太」は飛ぶように売れ、様々なバリエーションの商品の開発も進みスギダラケ倶楽部の本格的な活動がここから始まりました。
○スギダラケ倶楽部の活動を全国へ
全国の「地域に足を伸ばすことを始めたスギダラケ倶楽部。
地域に行くと荒れた山や限界集落に行きあたり、地域の問題にもぶつかりました。
そんな地域での活動を通して、普段会社でやっている仕事にはない、自分たちのデザインの力を求められている確かな意識と、
実際に地域の人からの「ありがとう」という感謝の言葉が何よりも嬉しく、活動のカンフル剤になったと若杉さんは語ります。
経済とは裏腹にある地域のことを見つめる中で、
やはり地域には「デザイン」が必要だと強く感じ、全国的なスギダラケ倶楽部の活動は始まりました。


・廃業になった高千穂鉄道のトロッコ列車を再び走らせるプロジェクト
・岐阜の長良杉の伐採体験などを行うツアー
・鹿沼のお祭りでの「屋台屋」プロジェクト
・・・全国の神様を象ったスギオメンや、木で出来た金魚をすくう「木んぎょすくい」などを杉で出来た屋台での出展
このような木を使った「生活・町・モノ」づくりが再生されるような活動は「楽しければ次もやろう」というようなスタンスで続けてきたそうですが、いつの間にか町の風物詩として、町の誇りになっていっていることを感じ、「デザインはこういうことから始まるんだな」と若杉さんは思ったそうです。
また鹿沼市ではスギダラケ倶楽部の活動から始まった町の盛り上がりに行政が着目し、助成金をだすなどの流れも出てきているということでした。
また「まちづくりは1年や2年では答えがでない。商品開発も仕込が2年あって製品開発して、、、となると売り上げが出始めるのは5年ぐらいたってから」
面白くて楽しい取り組みを広めていくには短い期間で結果を出そうとせず、長い期間での継続的な活動が必要だとということでした。

○日向市駅プロジェクト
県や市等が一丸となって地元の杉で駅舎を作った「宮崎県日向市駅プロジェクト」
その取り組みの中で小学生に課外授業を行い、小学生による「地元の杉で屋台を作る」という取り組みも行われました。
子ども達自身がデザイナーになり、地元の地域資源に触れ、またデザインする事に触れ、現在、そして未来の地域づくりに繋がっていきました。
その他にも
・宮崎空港プロジェクト
・函館空港プロジェクト
などスギダラケ倶楽部の活動は全国に拡がっています。
また「杉=和風だという固定概念があるが、杉をモダンに現代の生活に合うようにデザインする知恵とか工夫が人間サイドになかったので杉の価値を落としてしまった。これからは杉はすごいんだと、財産だと、言い続けることが必要だ」という若杉さんの言葉が印象的でした。

○「obisugi-design」プロジェクト
日南の飫肥杉から作られた工芸品の商品開発・発信を行う「obisugi-design」プロジェクト。
日南市の市役所職員を中心に活動を行い、内田洋行との共同開発で出来たアシカラシリーズなどの家具や、
飫肥杉で出来たご祝儀袋やトロフィーなどのスギフトシリーズなどバラエティに富んだ製品を開発・発信しています。
中心メンバーである市役所の職員は自分たちの本来の業務とは別に無償で活動を行い、
その熱量に若杉さんも強く心を打たれたということでした。
○ネーミングの重要性
スギダラケ倶楽部には「杉太」や「連結決傘(連結できるようにした傘状の屋台)」など特徴的なネーミングの商品が多くありますが、ネーミングは重要だと語る若杉さん。名前がついた瞬間に生命を帯びていき愛着がわくのでネーミングには一番時間をかけるそうです。

○赤ちゃん木育広場
子どもの想像性を育み、そして大人も一緒にいて楽しめる空間を考えて作られらたということでした。
また運用スタッフには、山での伐採から実際にその空間にあるプロダクトづくりに関わってもらい、愛着が沸いてメンテナンスの面などでも上手く運営が出来るように体制を確立していったということでした。
○木育から新しい価値創造へ
モノより大切なものは「モノガタリ」である。
誇り・愛着・感謝。お金に変えられないものこそが、モノの価値を上げていく。
こういった共感価値こそが木の暮らし・文化の再生、そして文化価値の再生に繋がっていくのだと若杉さんは仰っていました。
そして世界第3位の森林保有国であり昔から木と共に暮らしてきた日本人だからこそ、
杉などの木材・地域資源に宿る文化や魂を見つめ直し、木材と木材を囲む財産の関係性のデザインが重要だということでした。
そして行政・企業・市民がそれぞれの間を線引きするのではなく多様な主体が繋がり、
ハーモナイズさせることによって、大きなものになっていくということでした。
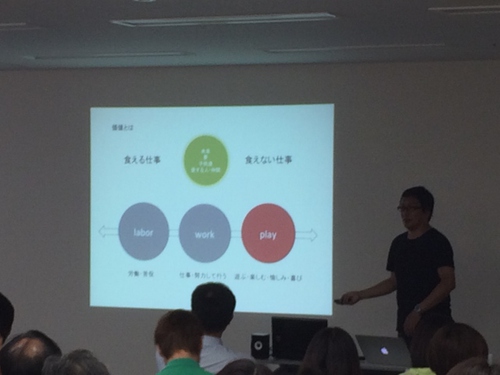
○食える仕事・食えない仕事
Labor(労働・苦役)
work(仕事・努力して行う)
play(遊ぶ・楽しむ・愉しみ・喜び)
「Laborは食える仕事だけど、労働であり苦役になってしまう。
Play=未来 は食えないけど楽しいし、喜びになり、そしてこの食えない仕事こそが社会や企業にとって重要だ」と話す若杉さん。
○価値創造とは
ものづくりやまちづくりは、0から1を創り上げる時が重要であり、
その時にいかに面白がれるかで、そこから出てくる「熱」や「ムーブメント」に繋がる。
若杉さんのこれまでの活動を象徴するような言葉でした。
この他にも講演時間内に収まりきれないほど多岐に渡って活動を展開されている若杉さん。
またこれまで関わってきた人々を「血の繋がってない親戚」だと仰っており、その関わり合いの深さを強く感じました。
★ワークショップ
ワークショップでは、グループ内での自己紹介と若杉さんへの質問を考えていただきました。

質疑応答では、
「特徴的なネーミングはどうやったら思いつくのですか」という質問に対して若杉さんは「若いうちはとにかくくだらないことをたくさん経験した方がいい。それが発想する力や自分の将来にも繋がる」とコメントされていました。

ご参加頂いた皆様からは、
「面白くてあっという間でした」
「『物語』の重要性、多様な主体との協働の重要性、楽しむこと、金儲けの発想からの脱却などの気づきがありました」
「杉はこうして使うもの、杉の価値はこれ、子どもはこんなものだと勝手に決め付けていたんだなと思いました。あらゆるものにあらゆる可能性があるんだなと感じました。」
といったご感想をいただきました!
今回のヒムカレッジは終始笑いの絶えない講演会となり、若杉さんの人柄、そして人間力に更に心を掴まれた参加者の方も多かったのではないでしょうか(●´∀`●)
若杉さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

□講師紹介
----------------------------------------------------------------------------
若杉 浩一 氏
パワープレイス株式会社 シニアディレクター プロダクトデザイナー
1959年生まれ 熊本県天草郡出身
1984年九州芸術工科大学芸術工学部工業設計学科卒
同年株式会社内田洋行入社、デザイン、製品企画、
知的生産性研究所 テクニカルデザインセンター、を経て
内田洋行のデザイン会社 パワープレイス株式会社にて
リレーションデザインセンター設立、同部門シニアディレクター
東京芸術大学美術学部非常勤講師
企業の枠やジャンルの枠にこだわらない活動を行う
やりすぎてデザイナーを首になるも性懲りもなく、企業と個人、社会の接点を模索している。
スチール家具メーカなのに何故か、日本全国スギダラケクラブを南雲勝志氏と設立。
ドイツIF賞、DESIGNPLUS特別賞受賞、全国都市再生まちづくり会議2007にて2007年度まちづくり大賞をスギダラケ倶楽部にて受賞
----------------------------------------------------------------------------
当日は、地域づくりに関わる方や大学生など、幅広い世代の45名の方々にご参加いただきました。当初予定してた定員数を越える参加者数となったため今回はスクール形式での開催となりました。

「杉」という地域資源を活用し人・地域・企業をつなげる取り組みや、若杉さんのこれまでの経歴や仕事に対する姿勢など盛りだくさんの内容をお話頂きました。
○田舎の人間関係が嫌いだった
熊本県の天草出身の若杉さん。
現在の人柄からは想像できませんが、子どもの頃は近所づきあいや日常的に濃い人間関係が苦手だったそうです。
また山の中での環境で育った為、子どもの頃からよく山へ草刈などに行っており、その頃から山の美しさと同時に厳しさを体感していたということでした。
○デザインの仕事へ
大学卒業後、若杉さんは株式会社内田洋行に入社しデザイナーとして数々のヒット商品を生み出しました。
しかし、「やってもやっても面白くない。先が見えないし、豊かな感じがしない」と思い始めた若杉さん。
とにかく売れるものや利益を優先した営業方針に疑問を覚え始め、自分が本当に売りたい商品を作ることが出来なかったといいます。
また会社の中でのデザイナーの立ち位置も厳しく、上手くいけば持て囃されるが、ダメなときにはすぐにチームが解体されるような状況だったということでした。
その頃はとにかく「谷あり底あり」の人生だったそうです。
○デザイナーをクビになり社内の職務を転々とした30代。
しかし、とうとうデザイナーをクビになり、OLさんと一緒にコピーをとったり会議室の予約などの内務の仕事をやったりと、
うだつの上がらない日々を過ごした30代。
そんな頃、若杉さんの師匠である家具プロデューサーの鈴木恵三さんから声がかかり、鈴木さんの会社の仕事を手伝い始めました。
そこは日本を代表するデザイナーが仕事をする環境で、普段デザインの仕事が出来ない状況もあり、
そこに行くと「デザインと繋がっている」と感じられ、とてもいい刺激になったそうです。
また鈴木さんに言われた「企業デザイナーはやめるな。日本のデザイナーは世界に通じる腕前を持っている。しかしそれが欧米に叶わないのはなぜかというと、デザインを流通させる企業側が非力だからだ。だからお前は企業側にいてデザインを強くしろ」という言葉から大きな力をもらい絶対にやめないことを若杉さんは決意しました。

○40代になり再びデザイナーの世界へ。そしてスギダラケ倶楽部の始動。
再びデザイナーとしての仕事を始めた若杉さんは、
利益の為のデザインではなく「楽しくかっこいいこと」をデザインでやりたいという思いからスギダラケ倶楽部の活動を始めました。
また自分のふるさとや地域、その中にある林業ががどんどん衰退していく状況に危機感を感じていた為、
「デザインの力で町を再生させることが出来るのではないか」と若杉さんは考え、そのこともスギダラケ倶楽部を始めるきっかけになりました。
日本全国スギダラケ倶楽部は現在、会員1800名。17支部あり、全国で活動が行われています。
戦後の植林によって杉だらけになってしまった日本の山林をやっかいもの扱いせず、材木としての杉の魅力 をきちんと評価し、産地・加工者・流通・デザイン・販売など杉を取り囲むシステムを結びつけることで、杉をもっと積極的に活用していく運動を行っています。
設立から14年経った現在でも活動が続いている理由を若杉さんは、女性の会員の力が大きいと言います。
元々男性の多い林業界なので、女性の視点や支援は活動の潤滑油になり継続的な活動には必要だということでした。

○世の中に広まっていくデザインとしての兆しが見えた「杉太」
若杉さんと一緒にスギダラケ倶楽部として活動を行う南雲勝志さんがデザインしたイス「杉太」
一本2000円の角材にステンレスの脚がついただけのとてもシンプルなイスを見た瞬間に、これは未来のデザインとして世に広まることを確信した若杉さん。
一本2000円程の角材にわずかなプロダクトをつけだけで2万円に。全国どこにでもある角材に企業のプロダクトがデザインで結ばれる「地域と企業がデザインで結ばれる」ことによって新しい価値が生まれ2000円が2万円の価値になるマジックに確かな手応えを感じていました。
若杉さんは「杉太」を会社で販売しようと話を持ちかけましたが取り合ってもらえず、「木目や色がバラバラになってしまうような商品は売れないし傷もつくし割れるしクレームの塊だ」と一蹴されてしまいます。
しかし「エンドユーザーは絶対に喜んでくれるし、地域の方も喜んでくれる」と確信を持っていた若杉さんは自分たちで自給自足的に販売を始めました。結果的に「杉太」は飛ぶように売れ、様々なバリエーションの商品の開発も進みスギダラケ倶楽部の本格的な活動がここから始まりました。
○スギダラケ倶楽部の活動を全国へ
全国の「地域に足を伸ばすことを始めたスギダラケ倶楽部。
地域に行くと荒れた山や限界集落に行きあたり、地域の問題にもぶつかりました。
そんな地域での活動を通して、普段会社でやっている仕事にはない、自分たちのデザインの力を求められている確かな意識と、
実際に地域の人からの「ありがとう」という感謝の言葉が何よりも嬉しく、活動のカンフル剤になったと若杉さんは語ります。
経済とは裏腹にある地域のことを見つめる中で、
やはり地域には「デザイン」が必要だと強く感じ、全国的なスギダラケ倶楽部の活動は始まりました。


・廃業になった高千穂鉄道のトロッコ列車を再び走らせるプロジェクト
・岐阜の長良杉の伐採体験などを行うツアー
・鹿沼のお祭りでの「屋台屋」プロジェクト
・・・全国の神様を象ったスギオメンや、木で出来た金魚をすくう「木んぎょすくい」などを杉で出来た屋台での出展
このような木を使った「生活・町・モノ」づくりが再生されるような活動は「楽しければ次もやろう」というようなスタンスで続けてきたそうですが、いつの間にか町の風物詩として、町の誇りになっていっていることを感じ、「デザインはこういうことから始まるんだな」と若杉さんは思ったそうです。
また鹿沼市ではスギダラケ倶楽部の活動から始まった町の盛り上がりに行政が着目し、助成金をだすなどの流れも出てきているということでした。
また「まちづくりは1年や2年では答えがでない。商品開発も仕込が2年あって製品開発して、、、となると売り上げが出始めるのは5年ぐらいたってから」
面白くて楽しい取り組みを広めていくには短い期間で結果を出そうとせず、長い期間での継続的な活動が必要だとということでした。

○日向市駅プロジェクト
県や市等が一丸となって地元の杉で駅舎を作った「宮崎県日向市駅プロジェクト」
その取り組みの中で小学生に課外授業を行い、小学生による「地元の杉で屋台を作る」という取り組みも行われました。
子ども達自身がデザイナーになり、地元の地域資源に触れ、またデザインする事に触れ、現在、そして未来の地域づくりに繋がっていきました。
その他にも
・宮崎空港プロジェクト
・函館空港プロジェクト
などスギダラケ倶楽部の活動は全国に拡がっています。
また「杉=和風だという固定概念があるが、杉をモダンに現代の生活に合うようにデザインする知恵とか工夫が人間サイドになかったので杉の価値を落としてしまった。これからは杉はすごいんだと、財産だと、言い続けることが必要だ」という若杉さんの言葉が印象的でした。

○「obisugi-design」プロジェクト
日南の飫肥杉から作られた工芸品の商品開発・発信を行う「obisugi-design」プロジェクト。
日南市の市役所職員を中心に活動を行い、内田洋行との共同開発で出来たアシカラシリーズなどの家具や、
飫肥杉で出来たご祝儀袋やトロフィーなどのスギフトシリーズなどバラエティに富んだ製品を開発・発信しています。
中心メンバーである市役所の職員は自分たちの本来の業務とは別に無償で活動を行い、
その熱量に若杉さんも強く心を打たれたということでした。
○ネーミングの重要性
スギダラケ倶楽部には「杉太」や「連結決傘(連結できるようにした傘状の屋台)」など特徴的なネーミングの商品が多くありますが、ネーミングは重要だと語る若杉さん。名前がついた瞬間に生命を帯びていき愛着がわくのでネーミングには一番時間をかけるそうです。

○赤ちゃん木育広場
子どもの想像性を育み、そして大人も一緒にいて楽しめる空間を考えて作られらたということでした。
また運用スタッフには、山での伐採から実際にその空間にあるプロダクトづくりに関わってもらい、愛着が沸いてメンテナンスの面などでも上手く運営が出来るように体制を確立していったということでした。
○木育から新しい価値創造へ
モノより大切なものは「モノガタリ」である。
誇り・愛着・感謝。お金に変えられないものこそが、モノの価値を上げていく。
こういった共感価値こそが木の暮らし・文化の再生、そして文化価値の再生に繋がっていくのだと若杉さんは仰っていました。
そして世界第3位の森林保有国であり昔から木と共に暮らしてきた日本人だからこそ、
杉などの木材・地域資源に宿る文化や魂を見つめ直し、木材と木材を囲む財産の関係性のデザインが重要だということでした。
そして行政・企業・市民がそれぞれの間を線引きするのではなく多様な主体が繋がり、
ハーモナイズさせることによって、大きなものになっていくということでした。
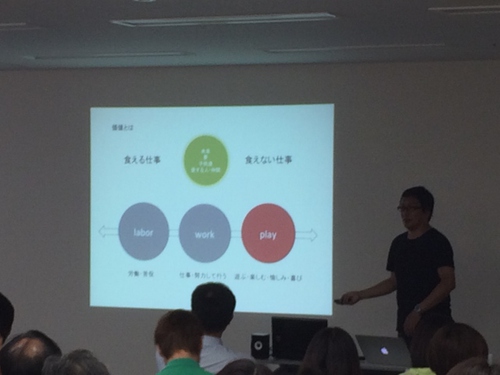
○食える仕事・食えない仕事
Labor(労働・苦役)
work(仕事・努力して行う)
play(遊ぶ・楽しむ・愉しみ・喜び)
「Laborは食える仕事だけど、労働であり苦役になってしまう。
Play=未来 は食えないけど楽しいし、喜びになり、そしてこの食えない仕事こそが社会や企業にとって重要だ」と話す若杉さん。
○価値創造とは
ものづくりやまちづくりは、0から1を創り上げる時が重要であり、
その時にいかに面白がれるかで、そこから出てくる「熱」や「ムーブメント」に繋がる。
若杉さんのこれまでの活動を象徴するような言葉でした。
この他にも講演時間内に収まりきれないほど多岐に渡って活動を展開されている若杉さん。
またこれまで関わってきた人々を「血の繋がってない親戚」だと仰っており、その関わり合いの深さを強く感じました。
★ワークショップ
ワークショップでは、グループ内での自己紹介と若杉さんへの質問を考えていただきました。

質疑応答では、
「特徴的なネーミングはどうやったら思いつくのですか」という質問に対して若杉さんは「若いうちはとにかくくだらないことをたくさん経験した方がいい。それが発想する力や自分の将来にも繋がる」とコメントされていました。

ご参加頂いた皆様からは、
「面白くてあっという間でした」
「『物語』の重要性、多様な主体との協働の重要性、楽しむこと、金儲けの発想からの脱却などの気づきがありました」
「杉はこうして使うもの、杉の価値はこれ、子どもはこんなものだと勝手に決め付けていたんだなと思いました。あらゆるものにあらゆる可能性があるんだなと感じました。」
といったご感想をいただきました!
今回のヒムカレッジは終始笑いの絶えない講演会となり、若杉さんの人柄、そして人間力に更に心を掴まれた参加者の方も多かったのではないでしょうか(●´∀`●)
若杉さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
2015年03月03日
『Design Lab Miyazaki vol.5 のべおか三蔵協議会地域づくり講演会』を開催しました!
2月25日(水)に、「Design Lab Miyazaki vol.5 のべおか三蔵協議会地域づくり講演会~競争から『共創』へ 地域の新しいPR戦略とは…?」を実施しました。
今回の講師は、のべおか三蔵協議会のキーパーソン、永野時彦さんと、武井千穂さんです。

★三蔵協議会の仕掛け人! ひでじビール代表取締役 / 永野時彦氏
1968年日之影町出身。1996年にひでじビールの創業会社:ニシダに入社。2010年ニシダによるビール事業撤退・事業閉鎖の危機に従業員による事業買収を実行し、同年11月宮崎ひでじビール株式会社を設立。自社企画『宮崎農援プロジェクト』を新たに立ち上げ、宮崎の農作物をビールの原料に取り入れるなど、地域資源を生かした商品開発に取り組んでいる。『JBA全国地ビール醸造者協議会理事』等の要職を務める傍ら、『のべおか三蔵協議会』等の地域づくり活動にも積極的に関わる。
★お酒好きの縁で広報担当に!のべおか三蔵コーディネーター / 武井千穂氏
横浜出身、明治大学農学部農芸化学科卒業。東京にて食品、化学品メーカーの技術系職を経た後、2009年延岡に。趣味の釣りがきっかけで徐々に地域づくりや観光に関わることになり、延岡市観光振興ビジョン策定のメンバーとなる。酒類全般に興味が有り、趣味で利酒師やワインエキスパートの資格を取得していたことが縁を繋ぎ、2014年5月に発足した「のべおか三蔵協議会」のコーディネーターに。3つの企業のどこにも属さない、フリーな立ち居地で広報を担当している。
当日は、地域づくりに関わる方、お酒造りに関わる方、大学生など、31名の方がご参加くださいました。

同じ地域で同じアルコール市場という本来であればライバル同士にもなりえる三つの蔵が、何をねらいとして、どのように協議会を結成したのでしょうか?「競争から『共創』へ」をテーマに、地域の新しいPR戦略の秘訣を実践事例からお話いただきました。
のべおか三蔵協議会とは?
延岡には焼酎(佐藤焼酎)・日本酒(千徳酒造)・地ビール(ひでじビール)と三種の酒蔵がそれぞれ一つずつあり、この条件がそろっているのは全国的にも延岡だけだということに気づかれた永野さん。それぞれの蔵が「世界一」「全国一」「全国初」「最南端」などさまざまな実績をもち、高いレベルでお互いに刺激しあっていましたが、「三蔵」として手を取り合うことで、さらに活動を発展させていけるのではということで結成されました。
〇佐藤焼酎:祝川沿いにある、美術館のように美しい焼酎蔵。日本で初めて「栗焼酎」を作った。
〇千徳酒造:延岡市の市街地近辺、大瀬川沿いの日本最南端の日本酒蔵。暑い地域で日本酒を作ることは大変だが、工夫を凝らしながら製造に取り組んでいる。
〇ひでじビール:行縢山の麓に製造所を構え、地ビール世界一の実力をもつ。近年の地ビールブームで、蔵には見学者も多い。
のべおか三蔵協議会が結成されるまで
昨年の5月に結成された三蔵会。結成前は、「地元の人がどの酒を選ぶのか?」という点で、やはりライバル同士だったそうです。結成のきっかけは、5年前にそれぞれの蔵の若手造り手だけで企画した『呑み会』でした。実際に話す場をもってみると、「種類の違う酒の造り方には、自分の酒蔵で生かせるヒントがたくさんある!定期的にやりたい!」ということになりました。そのときに『三蔵』の名前も生まれ、
・三つの蔵の商品ギフトがほしい!
・同じ品種の米を使用した酒の同時蔵出しをしてみてはどうか
・自分の蔵で生かすために別の蔵で仕込み体験をしたい
などなど様々な企画があげられました。
しかしそこから実現に移すまでには、各蔵の社長の同意をなかなか得られなかったりと、困難もありました。そんな状況を打開したのは、『三蔵』という名前と、そこに関わる第三者の存在でした。
名前の一人歩きと第三者の存在
永野さんたちは三蔵協議会が正式に結成される前から、呑み会を機に『三蔵』という言葉を積極的に使うようにされました。『三蔵』という言葉を使い続けることで、あたかも三社がセットであるかのような勘違い(?)が各方面で発生⇒行政・メディアが取り上げてくれるようになり、東九州自動車道の開通に合わせて注目が高まってきました。そのような流れから、いよいよ連携の必要性に各社が興味をもちます。
また、結成には『第三者』の助けが大きく関わりました。「利き酒師・ワインエキスパート・都会から来たよそ者・べっぴんさん」という条件を兼ね備えた武井千穂さんの働きかけや、地元情報サイトpawanaviを取り仕切る松田秀人さんの企画による「三蔵社長鼎談」の実現により、のべおか三蔵協議会がついに結成されました。
ポイント!:当事者だけではなかなか進めない。第三者の存在が必要。
三蔵協議会のねらい
結成の一番のねらいはPR力のアップ。
・行政の公的機関が支援しやすくなる。(単独企業には支援をしにくい)
・メディアが取り上げやすくなる。
三蔵の活動・今後の展望
〇これまでの活動
・観光冊子の発行
・三蔵共同のブース出展
・三蔵での鏡割り(日本酒・焼酎、そしてビールでも樽で鏡割り!市民の気運もアップした)
・イベントの目玉企画として、のべおか三蔵を楽しむプランが増えた。
・「三蔵を楽しむ夕べin福岡」など、県外でも多数のイベントが行われた。
〇今後の展望
・三蔵めぐりの強化⇒三蔵でお酒を飲んでいただくことは、延岡での宿泊者増につながり、経済への貢献にも!
・自前予算の総合パンフレットの作成
・地元消費増をねらった販促活動
・三蔵合同での海外進出(現在台湾と商談中)
「水郷」延岡のPR
武井さんには、コーディネーターの視点から見た三蔵会についてお話いただきました。
三蔵協議会結成前の三社は、単独で見てもレベルが高いが、小規模なので発信力が弱かったそうです。
しかし共通点としてはどの蔵も美しい水のある場所に蔵を建てられています。酒造りで「水郷・延岡」を証明することは、観光にも繋がるのではと語られました。
コーディネーターの役割
武井さんは、『三蔵の魅力は延岡の魅力』だと考えているそうです。
・三種の酒蔵の珍しさ
・同じ市内にあり、それぞれが30分以内で回れる範囲。また、三社をめぐることで、川、まち、山、全てを見ることができます。
コーディネーターとして大切にされていることは、「過大評価と過小評価の取り違えをなくしていくこと」だそうです。
他所から来たという、地元の人と違った目線を活かしてアドバイスをされています。例えば地元の人たちが「知っていて当然」という過大評価的な意識から説明不足になりがちな点は、観光客に対して分かりやすい説明になるように指摘をしたり、逆に当たり前だと思っていて過小評価されているところは、すばらしさを伝えたりされています。
三蔵を、みんなが満足する「満蔵」にしていきたいという言葉でしめてくださいました。
試飲
参加者の皆さんに三蔵の商品を試飲していただきました♪
栗からできた焼酎、栗や桃のリキュール、きんかんフレーバーのビールと、珍しいお酒がたくさん並びました!


ワークショップ
ワークショップでは、5班に分かれ気付きの振り返りと、永野さん・武井さんへの質問を考えていただきました。


気付きの振り返りでは、
・夢や目標という‘キーワード’を言い続けることの大切さ。
・協力のpower!(連携+第三者+上手なPRやマーケティング)
・県民性としてのPR下手⇒「ヨソモノ」の存在による気付き。
・行政が乗っかる仕組みづくり
といったことがあげられました。
質疑応答では時間に収まりきらないほどの質問があがりました。「ボランティアから収益になる方法が聞きたい」という質問に対して、お二人は、「やはり収益がなくボランティアだけでは活動は続かない。」「はじめはボランティア的な関わりもあったが、活動する中で評価してくれた周囲の人々が、職になるよう働きかけてくれた。」とコメントされていました。よそ者としての風当たりも強いなか、地域の人々との結びつきの強さを感じました。
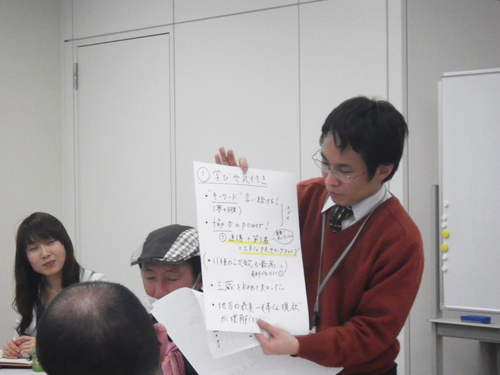

ご参加いただいた皆様からは
・酒の仲間とはいえ、ライバルの三社が協力して町おこしをしようという発想は気付きであり発見でした。
・三蔵はレアケースでもあると思います。この中の「外の目線」をエッセンスとして異なるエリアにも転用したいと考えました。
・地域の中にある資源、他と差別化できる特質にいかに気付き、価値に変えていけるか。長いスパンで価値をどう磨き上げていくか。その過程で大事なのは、ゆるぎない思いと情熱なのだと感じました。
といったご感想をいただきました!
永野さん、武井さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
今回の講師は、のべおか三蔵協議会のキーパーソン、永野時彦さんと、武井千穂さんです。

★三蔵協議会の仕掛け人! ひでじビール代表取締役 / 永野時彦氏
1968年日之影町出身。1996年にひでじビールの創業会社:ニシダに入社。2010年ニシダによるビール事業撤退・事業閉鎖の危機に従業員による事業買収を実行し、同年11月宮崎ひでじビール株式会社を設立。自社企画『宮崎農援プロジェクト』を新たに立ち上げ、宮崎の農作物をビールの原料に取り入れるなど、地域資源を生かした商品開発に取り組んでいる。『JBA全国地ビール醸造者協議会理事』等の要職を務める傍ら、『のべおか三蔵協議会』等の地域づくり活動にも積極的に関わる。
★お酒好きの縁で広報担当に!のべおか三蔵コーディネーター / 武井千穂氏
横浜出身、明治大学農学部農芸化学科卒業。東京にて食品、化学品メーカーの技術系職を経た後、2009年延岡に。趣味の釣りがきっかけで徐々に地域づくりや観光に関わることになり、延岡市観光振興ビジョン策定のメンバーとなる。酒類全般に興味が有り、趣味で利酒師やワインエキスパートの資格を取得していたことが縁を繋ぎ、2014年5月に発足した「のべおか三蔵協議会」のコーディネーターに。3つの企業のどこにも属さない、フリーな立ち居地で広報を担当している。
当日は、地域づくりに関わる方、お酒造りに関わる方、大学生など、31名の方がご参加くださいました。

同じ地域で同じアルコール市場という本来であればライバル同士にもなりえる三つの蔵が、何をねらいとして、どのように協議会を結成したのでしょうか?「競争から『共創』へ」をテーマに、地域の新しいPR戦略の秘訣を実践事例からお話いただきました。
のべおか三蔵協議会とは?
延岡には焼酎(佐藤焼酎)・日本酒(千徳酒造)・地ビール(ひでじビール)と三種の酒蔵がそれぞれ一つずつあり、この条件がそろっているのは全国的にも延岡だけだということに気づかれた永野さん。それぞれの蔵が「世界一」「全国一」「全国初」「最南端」などさまざまな実績をもち、高いレベルでお互いに刺激しあっていましたが、「三蔵」として手を取り合うことで、さらに活動を発展させていけるのではということで結成されました。
〇佐藤焼酎:祝川沿いにある、美術館のように美しい焼酎蔵。日本で初めて「栗焼酎」を作った。
〇千徳酒造:延岡市の市街地近辺、大瀬川沿いの日本最南端の日本酒蔵。暑い地域で日本酒を作ることは大変だが、工夫を凝らしながら製造に取り組んでいる。
〇ひでじビール:行縢山の麓に製造所を構え、地ビール世界一の実力をもつ。近年の地ビールブームで、蔵には見学者も多い。
のべおか三蔵協議会が結成されるまで
昨年の5月に結成された三蔵会。結成前は、「地元の人がどの酒を選ぶのか?」という点で、やはりライバル同士だったそうです。結成のきっかけは、5年前にそれぞれの蔵の若手造り手だけで企画した『呑み会』でした。実際に話す場をもってみると、「種類の違う酒の造り方には、自分の酒蔵で生かせるヒントがたくさんある!定期的にやりたい!」ということになりました。そのときに『三蔵』の名前も生まれ、
・三つの蔵の商品ギフトがほしい!
・同じ品種の米を使用した酒の同時蔵出しをしてみてはどうか
・自分の蔵で生かすために別の蔵で仕込み体験をしたい
などなど様々な企画があげられました。
しかしそこから実現に移すまでには、各蔵の社長の同意をなかなか得られなかったりと、困難もありました。そんな状況を打開したのは、『三蔵』という名前と、そこに関わる第三者の存在でした。
名前の一人歩きと第三者の存在
永野さんたちは三蔵協議会が正式に結成される前から、呑み会を機に『三蔵』という言葉を積極的に使うようにされました。『三蔵』という言葉を使い続けることで、あたかも三社がセットであるかのような勘違い(?)が各方面で発生⇒行政・メディアが取り上げてくれるようになり、東九州自動車道の開通に合わせて注目が高まってきました。そのような流れから、いよいよ連携の必要性に各社が興味をもちます。
また、結成には『第三者』の助けが大きく関わりました。「利き酒師・ワインエキスパート・都会から来たよそ者・べっぴんさん」という条件を兼ね備えた武井千穂さんの働きかけや、地元情報サイトpawanaviを取り仕切る松田秀人さんの企画による「三蔵社長鼎談」の実現により、のべおか三蔵協議会がついに結成されました。
ポイント!:当事者だけではなかなか進めない。第三者の存在が必要。
三蔵協議会のねらい
結成の一番のねらいはPR力のアップ。
・行政の公的機関が支援しやすくなる。(単独企業には支援をしにくい)
・メディアが取り上げやすくなる。
三蔵の活動・今後の展望
〇これまでの活動
・観光冊子の発行
・三蔵共同のブース出展
・三蔵での鏡割り(日本酒・焼酎、そしてビールでも樽で鏡割り!市民の気運もアップした)
・イベントの目玉企画として、のべおか三蔵を楽しむプランが増えた。
・「三蔵を楽しむ夕べin福岡」など、県外でも多数のイベントが行われた。
〇今後の展望
・三蔵めぐりの強化⇒三蔵でお酒を飲んでいただくことは、延岡での宿泊者増につながり、経済への貢献にも!
・自前予算の総合パンフレットの作成
・地元消費増をねらった販促活動
・三蔵合同での海外進出(現在台湾と商談中)
「水郷」延岡のPR
武井さんには、コーディネーターの視点から見た三蔵会についてお話いただきました。
三蔵協議会結成前の三社は、単独で見てもレベルが高いが、小規模なので発信力が弱かったそうです。
しかし共通点としてはどの蔵も美しい水のある場所に蔵を建てられています。酒造りで「水郷・延岡」を証明することは、観光にも繋がるのではと語られました。
コーディネーターの役割
武井さんは、『三蔵の魅力は延岡の魅力』だと考えているそうです。
・三種の酒蔵の珍しさ
・同じ市内にあり、それぞれが30分以内で回れる範囲。また、三社をめぐることで、川、まち、山、全てを見ることができます。
コーディネーターとして大切にされていることは、「過大評価と過小評価の取り違えをなくしていくこと」だそうです。
他所から来たという、地元の人と違った目線を活かしてアドバイスをされています。例えば地元の人たちが「知っていて当然」という過大評価的な意識から説明不足になりがちな点は、観光客に対して分かりやすい説明になるように指摘をしたり、逆に当たり前だと思っていて過小評価されているところは、すばらしさを伝えたりされています。
三蔵を、みんなが満足する「満蔵」にしていきたいという言葉でしめてくださいました。
試飲
参加者の皆さんに三蔵の商品を試飲していただきました♪
栗からできた焼酎、栗や桃のリキュール、きんかんフレーバーのビールと、珍しいお酒がたくさん並びました!


ワークショップ
ワークショップでは、5班に分かれ気付きの振り返りと、永野さん・武井さんへの質問を考えていただきました。


気付きの振り返りでは、
・夢や目標という‘キーワード’を言い続けることの大切さ。
・協力のpower!(連携+第三者+上手なPRやマーケティング)
・県民性としてのPR下手⇒「ヨソモノ」の存在による気付き。
・行政が乗っかる仕組みづくり
といったことがあげられました。
質疑応答では時間に収まりきらないほどの質問があがりました。「ボランティアから収益になる方法が聞きたい」という質問に対して、お二人は、「やはり収益がなくボランティアだけでは活動は続かない。」「はじめはボランティア的な関わりもあったが、活動する中で評価してくれた周囲の人々が、職になるよう働きかけてくれた。」とコメントされていました。よそ者としての風当たりも強いなか、地域の人々との結びつきの強さを感じました。
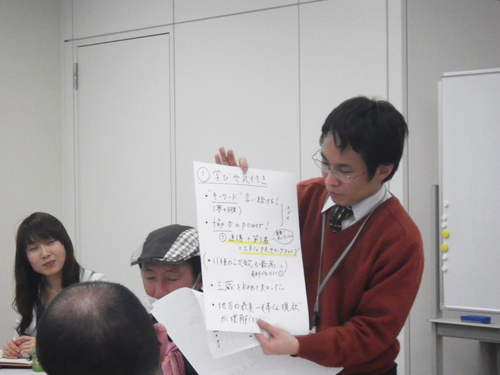

ご参加いただいた皆様からは
・酒の仲間とはいえ、ライバルの三社が協力して町おこしをしようという発想は気付きであり発見でした。
・三蔵はレアケースでもあると思います。この中の「外の目線」をエッセンスとして異なるエリアにも転用したいと考えました。
・地域の中にある資源、他と差別化できる特質にいかに気付き、価値に変えていけるか。長いスパンで価値をどう磨き上げていくか。その過程で大事なのは、ゆるぎない思いと情熱なのだと感じました。
といったご感想をいただきました!
永野さん、武井さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
2015年02月22日
『地域版ヒムカレッジin西米良 ~「もったいない」「おかげさまで」の気持ちでつなぐネットワークづくり~』を開催しました!
2月19日(水)に、本年度第2回目の地域版ヒムカレッジ『本田節氏地域づくり講演会「もったいない」「おかげさまで」の気持ちでつなぐネットワークづくり~』を、西米良村基幹集落センターにて開催しました。
今回の講師は、ひまわり亭代表取締役・本田節さんです。

本田さんは、熊本県球磨郡相良村出身。ガンとの闘病生活中、本田さんは人生の師と仰ぐ下村婦人会農産加工組合元代表の山北幸さんに出会います。山北さんは「食べ物は粗末になんかできない。全てを生かす」という、『もったいない』精神の元祖のような方で、戦後女性の立場が弱い時代から、女性雇用の場を切り開いてこられた方でした。
本田さんは、山北さんから『もったいない』のポリシーや、人づくりへの思いを受け継ぎ、ボランティア活動や地域づくりに参画するようになりました。その過程で夢の具現化として「ひまわり亭」を仲間と共にオープンされました。
「郷土料理家」、「地域活性化伝道師」、「6次産業化プランナー」など多くの役職を務められ、食・農・女性・地域づくりなど様々なテーマで、年100回に及ぶ講演会を行い、年の半分近くを走り回っている、パワフルな女性です。

当日は大変寒いなか、なんと西米良の人口の約8%に当たる、100名近くの方がご参加くださいました!会場は追加の椅子を持ってこなければ足りなくなるほどの人・人・人…!
西米良の皆さんの意識の高さに驚かされました!

〇これからはコンパクトな地域の方が面白い!ふるさとの抱える課題を解決するグリーンツーリズム
高齢化、少子化、過疎化、産業の低迷・・・ふるさとはたくさんの課題を抱えています。しかしそんな課題を解決し、地域を元気にする可能性を、グリーンツーリズムは秘めています。
〇グリーンツーリズムとは?
緑豊かな農山漁村で、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動がグリーンツーリズムです。他の地域から来た人にとっては、現場での体験によって癒され、感動する機会になり、地域にとっても多くの人に地域を訪れてもらうことで地域の活性化に繋がり、体験を提供することが住民にとっての生きがいとなったりします。
例えば、農家民宿や農家レストラン、農林漁業の体験などを行います。西米良でも既に、日本でもいち早く西米良ワーキングホリデーが実施されています。また、本田さんのひまわり亭も、農村レストランとしてグリーンツーリズムの精神が活かされています。
『ないものねだりではなく、あるものを見つける地域づくりを!』と本田さんは語られました。
〇キーワードは『もったいない』 ひまわり亭の始まり
地域の財産、「おばちゃん・おばあちゃんの知恵、経験、技、感性」がもったいない。築120年の古民家が、家に眠る食器類が、地域の食材がもったいない。そんな思いからひまわり亭はスタートしました。仲間のそれぞれの家から持ち寄った食器はばらばらでしたが、それが返って面白いと話題になったそうです。
そこにある文化を大切にしながら付加価値をつけ村をブランド化していくこと、またそのためには『よそ者』の意見も大事にすることの大切さをお話くださいました。
西米良の「ゆずごしょう」は、まさに素材に付加価値をつけたブランドで、おばちゃんの知恵が詰まっていると絶賛されていました!西米良の地域の特性を生かして、さらに面白いことが生まれそうです。
〇人が輝くグリーンツーリズムの実践例
ひまわり亭以外にも、九州各地で人が、特に女性が輝いている数件の実践例をご紹介くださいました。
・「ただいま」「おかえり」と、お客さんと声を掛け合う大分県の農家民宿
・物を売るだけではなく、農家の心を伝えるための施設を目指す福岡県の直売所 等々
グリーンツーリズムのポイントはかあちゃん、奥さんの元気だそうです!
〇「もったいない」と「おかげさま」
本田さんが人生の師と仰ぐ山北さんはたくさんの教えを残してくださり、本田さんは今もその思いを受け継がれています。
一、意志(こころざし)あるところに道がある
一、継続は力なり
一、ひとつひとつ障害は乗り越えよう
一、時間(とき)はあるものではなく、つくるもの
一、寝ていても何も転がってきた試しはない
一、起業は人づくりから
本田さんの原動力となっているのは、「人は、人との関わりでしか元気にならない。出会った人は家族」という考えかただそうです。「地域の宝は皆さんの笑顔。ふるさと大好き、人間大好きという思いを大切に地域づくりを」という言葉でしめてくださいました。


ご参加いただいた皆様からは
・とても元気をいただきました。まだまだやれること、学ぶことはたくさんあるのだと認識しました。少しでも地域にとけこんで皆さんと交流しながら元気にやっていきたいと思いました。(60代以上・女性)
・自分でできることを楽しみながら、たくさんの人と繋がりができるってすごくステキなことだと思いました!!(20代・女性)
・私たちのやりたいことのお手本です。勇気をいただきました。(50代・女性)
といったご感想をいただきました。
本田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
2014年11月07日
Design Lab Miyazaki vol.4 山口成美氏 地域づくり講演会を開催しました!!!
11月5日(水)に、Design Lab Miyazaki vol.4『アイデアを有機的に繋いで、地域を変える!6次産業化の店づくり』山口成美氏 地域づくり講演会をみやざき県民協働支援センターにて開催いたしました!
平日の夜にも関わらず、学生から実際に地域づくりを実践されている方まで、幅広い層から35名のご参加をいただきました!

講師はおおむら夢ファームシュシュの山口成美社長。
「おおむら夢ファームシュシュ」は長崎県大村市にある農業複合施設です。「シュシュ」とはフランス語で『お気に入り』という意味だそうです。
18年前に、8軒の専業農家が立ち上げた農産物直売所で、今では年間約49万人の観光客が訪れる農業複合施設へと成長を遂げました。
直売所を主軸に、加工品の開発やレストラン・観光農園、農業塾などさまざまな事業を展開されています。
「地域にあるもの」を生かしてどのように大人気の店づくりをしていったのか、山口さんのアイデアや実践されていることを、オヤジギャグを交えながら軽快かつ温かみのあるトークでお話いただきました!

〇農業の現状とシュシュの目指す農業
日本の農業就業平均年齢は、66歳。従来言われてきた3K農業は、「きつい、汚い、危険」でしたが、現在は「高齢化、後継者不足、荒廃農地」だそうです。そんな中シュシュの目指す3K農業は「観光農業、感動農業、希望農業」。何事もプラス思考で考えていきたいと語る山口さん。
『百姓⇒百商・百笑・飛躍しよう』時には、どこに売れるのか、求められるところに求められるだけ作るなど戦略を立てながら、夢のある農業に自分たちがしていくことが大切だとお話してくださいました。
〇ニーズに合わせた農業を
昔に比べて、今の人たちは、フルーツや野菜の皮をむいてまで食べなくなってきているそうです。「包丁が家にない」という家庭も増えてきているそう。そんな、カット野菜・フルーツが売れる時代、丸のままの野菜や果物が売れないことを嘆くのではなく、「求められるもの」に工夫して加工しているそうです。例えばシュシュでは、あまった野菜を使ってアイスを作っています。
様々な種類の野菜・フルーツを使った、大人気のアイスだそうです。
一手間かける発想と工夫の大切さを感じました。
〇農業×〇〇でビジネス
シュシュでは直売や加工品の販売の他にレストランで旬の食材を使ったバイキング、ウェディング、そしてなんと法事まで様々な新しいことに取り組んでいらっしゃいます。実践事例から農業の可能性を感じることのできるお話でした。
・レストラン⇒バイキングは「有料で試食してもらう」というイメージだそうです。おいしい旬のものを提供し、食材の販売に繋がることを狙っています。
・ウェディング⇒シュシュでしか体験できないような工夫の詰まったウェディングプランです。例えば新郎新婦にパッションフルーツの受粉体験をしてもらい、収穫された果物はジュースにして、披露宴の引き出物として活用されているそうです。
〇シュシュが目指すこと「地域の活性化には混浴がいい!」
地域の活性化には、様々なグループの人たちが交流し協力することが大切です。足を引っ張るのではなく、みんなで温泉に入るように手を携えた地域づくりを目指し、年中夢を求めて活動していきたい、という言葉で講演をしめてくださいました!

■グループワークと質疑応答
講座後半は、グループで山口さんの講演を聞いての気づきをシェアしあい、山口さんに聞きたいことをグループで1つきめて質問してもらいました。


皆さん、真剣に、楽しそうに相談されていました。
□Q&Aの一部
Q:今後の一番の夢は何ですか?
A:今は小さな農業者としての夢だが、農業者以外の人も含めた、地域の夢を育てていきたい。人も地域も、スポットが当たると美しくなる。
Q:ネーミングが面白いですが(君を愛す(アイス)、ケッコーいけてるシュシュプリンなど)どのように考えられていますか。
A:常にラベルを見たときに笑顔が出るように考えています。


参加者からは
・王道のマーケティング戦略にのっとって、明るく行動し続ける山口さんの人間力に尊敬しました。
・農業の広がりに限界はないということを感じました!
・農業は無縁だと思っていましたが、6次産業化によって地域を巻き込めること、活性化、存在意義が生まれることが分かりました。
・ポジティブな考え方、アイデアの生み出し方を見習いたいと思います。
といったご感想をいただきました。
「宮崎のこれから」にも生かせる貴重なアイデアをお話いただいた2時間半でした。山口さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
平日の夜にも関わらず、学生から実際に地域づくりを実践されている方まで、幅広い層から35名のご参加をいただきました!

講師はおおむら夢ファームシュシュの山口成美社長。
「おおむら夢ファームシュシュ」は長崎県大村市にある農業複合施設です。「シュシュ」とはフランス語で『お気に入り』という意味だそうです。
18年前に、8軒の専業農家が立ち上げた農産物直売所で、今では年間約49万人の観光客が訪れる農業複合施設へと成長を遂げました。
直売所を主軸に、加工品の開発やレストラン・観光農園、農業塾などさまざまな事業を展開されています。
「地域にあるもの」を生かしてどのように大人気の店づくりをしていったのか、山口さんのアイデアや実践されていることを、オヤジギャグを交えながら軽快かつ温かみのあるトークでお話いただきました!

〇農業の現状とシュシュの目指す農業
日本の農業就業平均年齢は、66歳。従来言われてきた3K農業は、「きつい、汚い、危険」でしたが、現在は「高齢化、後継者不足、荒廃農地」だそうです。そんな中シュシュの目指す3K農業は「観光農業、感動農業、希望農業」。何事もプラス思考で考えていきたいと語る山口さん。
『百姓⇒百商・百笑・飛躍しよう』時には、どこに売れるのか、求められるところに求められるだけ作るなど戦略を立てながら、夢のある農業に自分たちがしていくことが大切だとお話してくださいました。
〇ニーズに合わせた農業を
昔に比べて、今の人たちは、フルーツや野菜の皮をむいてまで食べなくなってきているそうです。「包丁が家にない」という家庭も増えてきているそう。そんな、カット野菜・フルーツが売れる時代、丸のままの野菜や果物が売れないことを嘆くのではなく、「求められるもの」に工夫して加工しているそうです。例えばシュシュでは、あまった野菜を使ってアイスを作っています。
様々な種類の野菜・フルーツを使った、大人気のアイスだそうです。
一手間かける発想と工夫の大切さを感じました。
〇農業×〇〇でビジネス
シュシュでは直売や加工品の販売の他にレストランで旬の食材を使ったバイキング、ウェディング、そしてなんと法事まで様々な新しいことに取り組んでいらっしゃいます。実践事例から農業の可能性を感じることのできるお話でした。
・レストラン⇒バイキングは「有料で試食してもらう」というイメージだそうです。おいしい旬のものを提供し、食材の販売に繋がることを狙っています。
・ウェディング⇒シュシュでしか体験できないような工夫の詰まったウェディングプランです。例えば新郎新婦にパッションフルーツの受粉体験をしてもらい、収穫された果物はジュースにして、披露宴の引き出物として活用されているそうです。
〇シュシュが目指すこと「地域の活性化には混浴がいい!」
地域の活性化には、様々なグループの人たちが交流し協力することが大切です。足を引っ張るのではなく、みんなで温泉に入るように手を携えた地域づくりを目指し、年中夢を求めて活動していきたい、という言葉で講演をしめてくださいました!

■グループワークと質疑応答
講座後半は、グループで山口さんの講演を聞いての気づきをシェアしあい、山口さんに聞きたいことをグループで1つきめて質問してもらいました。


皆さん、真剣に、楽しそうに相談されていました。
□Q&Aの一部
Q:今後の一番の夢は何ですか?
A:今は小さな農業者としての夢だが、農業者以外の人も含めた、地域の夢を育てていきたい。人も地域も、スポットが当たると美しくなる。
Q:ネーミングが面白いですが(君を愛す(アイス)、ケッコーいけてるシュシュプリンなど)どのように考えられていますか。
A:常にラベルを見たときに笑顔が出るように考えています。


参加者からは
・王道のマーケティング戦略にのっとって、明るく行動し続ける山口さんの人間力に尊敬しました。
・農業の広がりに限界はないということを感じました!
・農業は無縁だと思っていましたが、6次産業化によって地域を巻き込めること、活性化、存在意義が生まれることが分かりました。
・ポジティブな考え方、アイデアの生み出し方を見習いたいと思います。
といったご感想をいただきました。
「宮崎のこれから」にも生かせる貴重なアイデアをお話いただいた2時間半でした。山口さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
2014年10月15日
『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』第4回 プレ審査会&振り返りを開催しました!
10月11日(土)に、計4回の連続講座『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』の第4弾 プレ審査会&振り返り をみやざき県民協働支援センターにて開催いたしました!
4回連続講座の『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』もいよいよ最終回。今までの学びの総まとめとして、参加者の中から希望をいただいた10名に、企画をプレゼンしていただきました。

審査員は、第1回講座講師のNPO法人代表理事・石田さん、公益財団法人 宮崎県市町村振興協会の中武さん、宮崎県中山間地域政策課の東原さん。また、発表者以外の参加者の皆さんには、プレゼンを見ての評価をシートに書き込んでいただき、審査員を体験していただきました。


今回のプレ審査会は、発表7分、質疑応答5分の合わせて12分を持ち時間として、形式は定めず、スライドの有無を始め自由な形式で発表していただきました。
糖尿病予防のための血糖値測定の促進に関する企画から、神話や神楽を絡めた宮崎の観光に関する企画、動物用シャンプーに関するプレゼン、自分の団体の活動紹介プレゼンなど、さまざまな切り口からのプレゼンが飛び出しました!
また、発表の技法も様々で、前回のプレゼン講座で紹介された高橋メソッドを早速使っての発表や、スライドを使わず、印刷物を提示しながらの発表、手話を用いた発表など、個性の光るプレ審査会となりました。
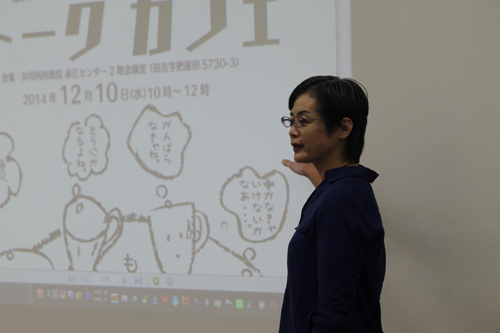


経験も、活動内容も様々な発表者たちでしたが、学生のプレゼンテーターも!今回のプレ審査会で度胸をつけ、今後より一層活躍してくれることに期待します!!

プレゼン終了後は、審査員の3名と会場に来ていただい皆さんに、「企画が素晴らしい!」「プレゼンが素晴らしい!」「投資したい!」「仲間になりたい!」の4つの観点から、いいと思った発表者の欄にシールを貼っていっていただき、評価してもらいました。
自分の発表のすばらしかった点、反省点を振り返る際の材料にしていただければと思います。
発表していただいた方も、今回は発表できなかった方も、ぜひこのヒムカレッジを機に企画したアイデアの実現に向けて活動していっていただきたいと思います。
参加者からは
・プレゼンすることへのハードルが下がりました。
・10名の方のプレゼンを見て、枠にとらわれず伝えたいことを伝えることの大切さを実感しました。本当にすばらしい内容で、大変勉強になりました。
・実際にface to face で会話したり、コミュニケーションをとることの大切さを再認識しました。本やネットにはない、「百聞は一見にしかず」でした。
・自分の考えを発信することで、新しいアイデアや繋がりが生まれると感じました。
といったご感想をいただきました!
約1ヶ月半に渡る講座となりました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
2014年10月02日
『ヒムカ地域づくりインターンシップ 事後研修会』を実施しました!
9月30日(火)に、『ヒムカ地域づくりインターンシップ』の参加者を対象とした事後研修会を、みやざき県民協働支援センターにて実施しました。
※『ヒムカ地域づくりインターンシップ』・・・県内各地の地域づくりの第一線で活躍するリーダーのもとで地域づくりの活動に取り組みつつ、実社会で求められるスキルを実践的に学んでいく、2週間から1か月のインターンシップのプログラムです。
事後研修会に参加したのは、
・五ヶ瀬町プログラムで研修した須田千晶さん
・日南市油津プログラムで研修した河野華寿美さん
・日南市酒谷プログラムで研修した安藤功くん、佐藤亜李紗さん
今回の事後研修会のミッションは、インターンシップを通じてどのようなことを学び、自分自身にどのような変化があったのかをしっかり整理すること。そして今後の学生生活にいかにつなげていくかををさまざまなワークを通じて考えてもらいました。

〇まずは、インターンシップを通じて知った地域の魅力やPR点、インターンシップでの取り組みをまとめたパネル作り。
たくさん撮ってきた写真から、心をこめて選び、体験を振り返りながら作ってくれました!

作成中の様子。熱がこもってます!
〇完成したら、作成したパネルを使って、インターンシップでの学びや気付きを共有してもらいました。
農業体験、カフェでの研修、おいしいご飯・・・なかには、「もっと地域で学びたかった!」という学生も。また、「地域の若者不足を切実に感じた」と、地域の課題をリアルに感じた面もあったようです。
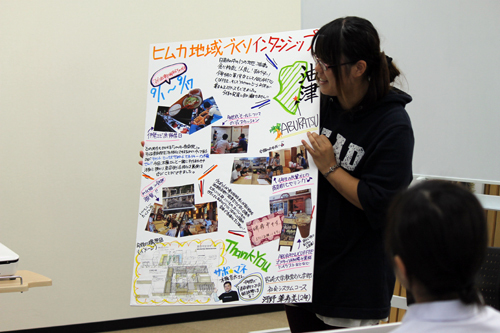
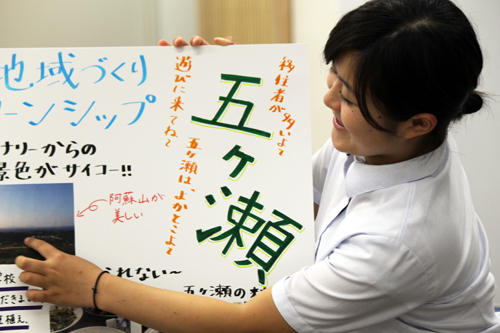

生き生きと発表してくれました!
〇体験の振り返りの後には、
インターンシップ前に立てた目標をどれぐらい達成できたのか、インターンシップを通じてどういう面が成長できたか、振り返りシートを使って考えてもらいました。
〇最後に「これからの大学生活を120%楽しむための作戦会議」と題し、自由な意見交換を行いました。


・まずは、勉強!
・就活
・地域に関わる。座ってるだけの勉強じゃもったいない。
・社会人と飲み会をする!
などなどたくさんの意見が飛び交いました。
参加学生が生き生きと話す様子から、地域での充実した経験と、確かな成長を感じることができました。また、実際に地域の魅力を実感した学生たちの言葉からは、受け入れ先への地域への思いが感じられ、「私も行ってみたい!」という気持ちにさせてもらいました。
学んだことを生かして、充実した学生生活にしていってもらいたと思います。インターンシップ生のみなさんお疲れ様でした!

なおインターンシップ生が作成した地域のパネルは、みやざき県民協働支援センター内に掲示します。センターにお越しの際は、ぜひご覧ください♪
※『ヒムカ地域づくりインターンシップ』・・・県内各地の地域づくりの第一線で活躍するリーダーのもとで地域づくりの活動に取り組みつつ、実社会で求められるスキルを実践的に学んでいく、2週間から1か月のインターンシップのプログラムです。
事後研修会に参加したのは、
・五ヶ瀬町プログラムで研修した須田千晶さん
・日南市油津プログラムで研修した河野華寿美さん
・日南市酒谷プログラムで研修した安藤功くん、佐藤亜李紗さん
今回の事後研修会のミッションは、インターンシップを通じてどのようなことを学び、自分自身にどのような変化があったのかをしっかり整理すること。そして今後の学生生活にいかにつなげていくかををさまざまなワークを通じて考えてもらいました。

〇まずは、インターンシップを通じて知った地域の魅力やPR点、インターンシップでの取り組みをまとめたパネル作り。
たくさん撮ってきた写真から、心をこめて選び、体験を振り返りながら作ってくれました!

作成中の様子。熱がこもってます!
〇完成したら、作成したパネルを使って、インターンシップでの学びや気付きを共有してもらいました。
農業体験、カフェでの研修、おいしいご飯・・・なかには、「もっと地域で学びたかった!」という学生も。また、「地域の若者不足を切実に感じた」と、地域の課題をリアルに感じた面もあったようです。
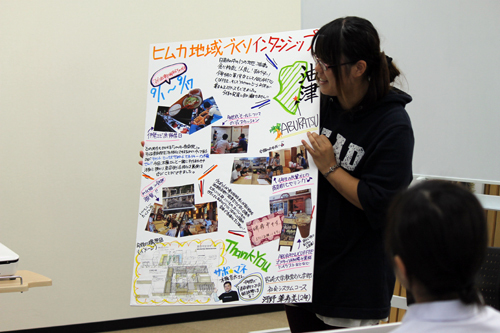
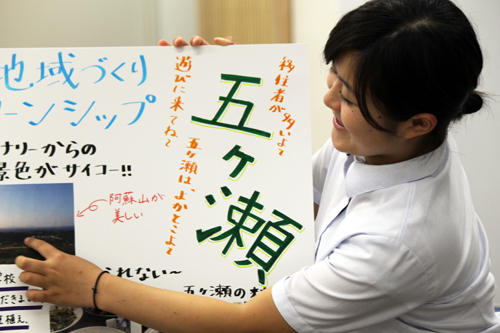

生き生きと発表してくれました!
〇体験の振り返りの後には、
インターンシップ前に立てた目標をどれぐらい達成できたのか、インターンシップを通じてどういう面が成長できたか、振り返りシートを使って考えてもらいました。
〇最後に「これからの大学生活を120%楽しむための作戦会議」と題し、自由な意見交換を行いました。


・まずは、勉強!
・就活
・地域に関わる。座ってるだけの勉強じゃもったいない。
・社会人と飲み会をする!
などなどたくさんの意見が飛び交いました。
参加学生が生き生きと話す様子から、地域での充実した経験と、確かな成長を感じることができました。また、実際に地域の魅力を実感した学生たちの言葉からは、受け入れ先への地域への思いが感じられ、「私も行ってみたい!」という気持ちにさせてもらいました。
学んだことを生かして、充実した学生生活にしていってもらいたと思います。インターンシップ生のみなさんお疲れ様でした!

なおインターンシップ生が作成した地域のパネルは、みやざき県民協働支援センター内に掲示します。センターにお越しの際は、ぜひご覧ください♪
2014年09月23日
『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』第3回 プレゼン講座を開催しました!
9月21日(日)に、計4回の連続講座『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』の第3弾、プレゼン講座をみやざき県民協働支援センターにて開催いたしました!
第3回目の講師は、都城工業高等専門学校 准教授の吉井千周さん。

吉井さんは、鹿児島大学法文学部、慶應義塾大学院政策・メディア研究科修士課程、同博士課程、タイ国立チュラロンコン大学社会調査研究所客員研究員を経て、現在都城工業高等専門学校にて准教授を務められております。タイ北部でのNGO活動を皮切りに国内の複数のNPOでの実践活動にも関わっていらっしゃいます。現在は、都城地区を中心とした社会人勉強会を主催するほか、プレゼンテーションの指導を全国各地の大学で行っていらっしゃいます。
今回は自分たちの団体や活動内容を第三者に分かりやすく伝えるためのプレゼンテーションのコツをお話いただきました!

〇オバマ氏の勝利演説から学ぶ
まずは「yes we can」の言葉が印象的な、オバマ氏の勝利演説から良いプレゼンテーションを考えました。
※伝えたいメッセージを安直な言葉ではなく、ストーリーで語りイメージを売ること。
※プレゼンテーションの目的は、自分の願うとおりに、相手に動いてもらうように仕向けること。
ということに、参加者は気づくことができました。

〇マーケティングの理論に学ぶ
プレゼンテーションでは、マーケティングの考え方が大切だそうです。プレゼンテーションは聞いてくれる人がいなければ意味がありません。自分が言いたいことを言うのではなく、受け手である聴衆のことをしっかり考えましょう。受け手はどんな人物であるか想定し、どんな情報を聞きたがっているのか、シュミレーションすることが大切です。
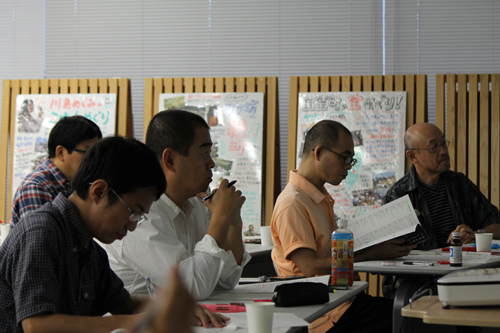

〇具体的なプレゼンの技法
プレゼンテーションではパワーポイントなどのスライドウェアを使うことが多くあります。しかしスライドウェアはプレゼンに必ず必要なものではありません。
悪い使用例やよい使用例から、効果的なスライドウェアの使い方を学びました。
(悪いスライドウェアの使用例)
・文字が多い。
・読みにくいフォント。
・重要なポイントが分からない。
・アニメーションの多様⇒重要なところをアニメーションにすると、表示される時間が短くなってしますので、大事なポイントにも関わらず見落とされる可能性があります。
(良いスライドウェアの使用例)
・文字は少なく。話せば分かることは書かない。
・数字や写真を効果的に使う。
・話題の転換に活用する。
※ポイント※
シンプルで洗練されたスライドを目指しましょう。また、写真には一目で分かるという強みがあります。普段からたくさん写真を撮って活用していきましょう。

〇まとめ〇
1.プレゼンの目的
・相手にどんな行動を起こさせたいのか
・聴衆はどんな人物なのか
2.スライドはシンプルに
・すべてではなく、伝える情報を絞る
3.いきなりスライドを作らない
・マインドマップでアイデアを書き出す
おまけ:プレゼンは時間内(早め)に切り上げる
吉井さんの講座自体が、良いプレゼンのお手本となっていました。ミュージカルのようなしゃべりに引き込まれるあっという間の3時間半でした。
参加者からは
・プレゼン力を磨くことで、「本質」、「一番大事なこと」をつかむ、たどり着く、共有することもできるはずだと実感しました。
・プレゼンって芸術だと感じました。完成度の高いモデルを見せていただきました。吉井さんの目的意識、とても参考になりました。
・人をひきつけるプレゼテーションは、思っていたよりシンプルで、簡単で良いのだと思った。情報があふれているので、伝えたい情報を絞ることの大切さに気づきました。
といったご感想をいただきました!
吉井さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
次回はいよいよ最終回、『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』プレ審査会&振り返りです。
第3回目の講師は、都城工業高等専門学校 准教授の吉井千周さん。

吉井さんは、鹿児島大学法文学部、慶應義塾大学院政策・メディア研究科修士課程、同博士課程、タイ国立チュラロンコン大学社会調査研究所客員研究員を経て、現在都城工業高等専門学校にて准教授を務められております。タイ北部でのNGO活動を皮切りに国内の複数のNPOでの実践活動にも関わっていらっしゃいます。現在は、都城地区を中心とした社会人勉強会を主催するほか、プレゼンテーションの指導を全国各地の大学で行っていらっしゃいます。
今回は自分たちの団体や活動内容を第三者に分かりやすく伝えるためのプレゼンテーションのコツをお話いただきました!

〇オバマ氏の勝利演説から学ぶ
まずは「yes we can」の言葉が印象的な、オバマ氏の勝利演説から良いプレゼンテーションを考えました。
※伝えたいメッセージを安直な言葉ではなく、ストーリーで語りイメージを売ること。
※プレゼンテーションの目的は、自分の願うとおりに、相手に動いてもらうように仕向けること。
ということに、参加者は気づくことができました。

〇マーケティングの理論に学ぶ
プレゼンテーションでは、マーケティングの考え方が大切だそうです。プレゼンテーションは聞いてくれる人がいなければ意味がありません。自分が言いたいことを言うのではなく、受け手である聴衆のことをしっかり考えましょう。受け手はどんな人物であるか想定し、どんな情報を聞きたがっているのか、シュミレーションすることが大切です。
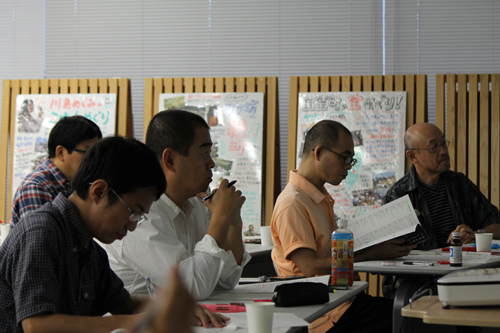

〇具体的なプレゼンの技法
プレゼンテーションではパワーポイントなどのスライドウェアを使うことが多くあります。しかしスライドウェアはプレゼンに必ず必要なものではありません。
悪い使用例やよい使用例から、効果的なスライドウェアの使い方を学びました。
(悪いスライドウェアの使用例)
・文字が多い。
・読みにくいフォント。
・重要なポイントが分からない。
・アニメーションの多様⇒重要なところをアニメーションにすると、表示される時間が短くなってしますので、大事なポイントにも関わらず見落とされる可能性があります。
(良いスライドウェアの使用例)
・文字は少なく。話せば分かることは書かない。
・数字や写真を効果的に使う。
・話題の転換に活用する。
※ポイント※
シンプルで洗練されたスライドを目指しましょう。また、写真には一目で分かるという強みがあります。普段からたくさん写真を撮って活用していきましょう。

〇まとめ〇
1.プレゼンの目的
・相手にどんな行動を起こさせたいのか
・聴衆はどんな人物なのか
2.スライドはシンプルに
・すべてではなく、伝える情報を絞る
3.いきなりスライドを作らない
・マインドマップでアイデアを書き出す
おまけ:プレゼンは時間内(早め)に切り上げる
吉井さんの講座自体が、良いプレゼンのお手本となっていました。ミュージカルのようなしゃべりに引き込まれるあっという間の3時間半でした。
参加者からは
・プレゼン力を磨くことで、「本質」、「一番大事なこと」をつかむ、たどり着く、共有することもできるはずだと実感しました。
・プレゼンって芸術だと感じました。完成度の高いモデルを見せていただきました。吉井さんの目的意識、とても参考になりました。
・人をひきつけるプレゼテーションは、思っていたよりシンプルで、簡単で良いのだと思った。情報があふれているので、伝えたい情報を絞ることの大切さに気づきました。
といったご感想をいただきました!
吉井さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
次回はいよいよ最終回、『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』プレ審査会&振り返りです。
2014年09月10日
『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』第2回 ファシリテーション講座を開催しました!
9月7日(日)に、計4回の連続講座『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』の第2弾、ファシリテーション講座をみやざき県民協働支援センターにて開催いたしました!
第2回目の講師は、NPO法人 日本ファシリテーション協会 フェローの加留部 貴行さん。

加留部さんは、九州大学法学部卒業後、㈱西部ガスに入社。人事、営業、新規事業部門に従事。学生時代からまちづくり活動に携わり、入社後も活 動を継続。2001年には西部ガスより福岡市へNPO・ボランティア支援推進専門員として2年半派遣。西部ガス復帰後は指定管理者制度を担当。2007年からは九州大学へ出向し、大学改革プロジェクトを経て、ファシリテーション導入を通じた教育プログラム開発や学内外プロジェク トを担当。 企業、大学、行政、NPOの4つのセクターを経験している「ひとり産学官民連携」を活かした共働ファシリテーションを実践されています。 2011年4月に独立し、現在は、加留部貴行事務所AN-BAI代表、㈱トライローグ取締役でいらっしゃいます。
今回は会議運営をスムーズにするためのファシリテーションについてお話いただきました!

〇なぜ私達はわざわざ集め・集まって会議を開くのでしょうか?
わざわざ集まって会議を開くには、3つの理由があるという加留部さん。
①個人では限界があるから。・・・会議を開くことで、個人で解決できない物理的な問題を解決できたり、質を上げることができます(知らないことを知る・他の人の経験を追体験できる・気づきがある)
②文字情報には限界があるから。・・・現代社会には情報があふれています。文字情報では伝えたいことが伝わっていない可能性があります。
③互いに確かめあう必要があるから。・・・こちらが伝えたと思っている通りに、相手は受け取ってくれているでしょうか?受け取り方はバラバラかも知れません。確かめ合うために、実際に集まり顔をつき合わせて会議をします。
※パソコンの普及により、私達は画面を見ている時間が長くなり、なかなか顔を見て話す場をもつことを意識できていません。会議は人と人が向き合って話す、貴重な場になりつつあるそうです。
〇ファシリテーション・ファシリテーターとは?
・ファシリテーションは、「引き出す力」。その他にも、「その気にさせる・芽吹かせる」といった意味があります。会議の場という「土」に、参加者という「種」がまかれます。ファシリテーターは、参加者がのびのびと参加できるようにする「発芽促進剤」のイメージだそうです。
・進行役とファシリテーターはどう違うの?
進行役は、議題に沿って会議を進めるという役割ですが、ファシリテーターはより予定調和的でない、場にゆだねた進行をします。「やってみないと分からない!」というところが強いそうです。
〇ファシリテーターの役割
・中立的な立場で、(最後に発言をする)⇒このポイントを意識すれば「お先にどうぞ」の気持ちが生まれます。
・チームのプロセスを管理し、(進め方を意識する)⇒進め方は誘導しますが、内容は誘導しません。「決定の仕方を決める」といった、合意形成を促す役割です。
・チームワークを引き出し、(ひとりでやらない)⇒「ひとりでやらない・ひとりでさせない・ひとりにさせない」という気持ちで気を配ることが大切です。
・そのチームの成果が最大になるよう支援する。
〇プロセスを「交通整理」するファシリテーター
・ガードレールのように、話が逸れそうになったら、議題に戻すのがファシリテーターの役割。
そのためのポイントは、実は私たちが小学生のころから経験している、「議題を板書すること」
議題を始めに目に付くところに書いておくだけで、話が逸れていくのを防ぐことができるそうです。
〇「成果」さることながら、「納得感」を引き出すために注力する。
会議では、すぐ結果が目に見える「成果」の出る結論を出そうとしがちになります。しかし、
まずは、決まったことに対して「それじゃあ、みんなでがんばっていこうか!」と思える納得感のある会議を目指しましょう。(図■部分のイメージ)

〇ワークショップ~五年後の私たちはどのようなくらしをしているでしょうか~
今回は「ワールド・カフェ」という形式で、ワークショップを行いました。
【参考】「ワールド・カフェ」の基本的な進め方
①1グループ4~6人ほどで構成されたテーブルを複数つくる
②進行役から提起される発問についてテーブルで話し合いを進め、そこで
話されたこと、感じたこと、気づいたことなどを模造紙に落書きをする
③20分置きくらいに、ホスト1名を残して、全員席替えをする
④新しいメンバー同士で先程まで自分がいたテーブルで話し合われていた
内容を披露しあう
⑤これを時に数回繰り返し、最後には元のテーブルに戻る
まずは、模造紙中央に大きく議題を書きます!これで議題から逸れた話も自然に戻すことができます。

グループで話しあわれた「みんなの意見」を背負って次のテーブルに移ります。人から聞いたいい意見も、自分のことのように話すことができます。


最後に、自分の中で引っかかったキーワードを、個人で抜き出してもらいました。


参加者からは
・緊張する体質ですが、雰囲気・言葉遣いで意見が言いやすくなることを実感できました。
・6人以下のグループ、雰囲気作り、リズム、声のトーンなど、目からうろこなことがたくさんで勉強になり、勇気が出ました。ありがとうございました。
といったご感想をいただきました!
加留部さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
次回の『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』は第3回・プレゼン講座です。
2014年08月30日
『ヒムカ地域づくりインターンシップ 事前研修会』を実施しました!
8月23日(土)に、『ヒムカ地域づくりインターンシップ』の参加者を対象とした事前研修会を、みやざき県民協働支援センターにて実施しました。
※『ヒムカ地域づくりインターンシップ』・・・県内各地の地域づくりの第一線で活躍するリーダーのもとで地域づくりの活動に取り組みつつ、実社会で求められるスキルを実践的に学んでいく、2週間から1か月のインターンシップのプログラムです。
まずは趣旨説明。参加者の学生さんも少し緊張気味です。

自己紹介に続いて、インプロに挑戦!
インプロとは即興劇のことですが、インプロを取り入れたゲームは、コミュニケーションを学ぶツールとして活用されています。隣の人に目だけで合図を送って同じタイミングで手をたたく「拍手ゲーム」など3種類のインプロで、『しっかり相手の目を見る、相手からの目線を受けとる』練習をしました。


失敗したらみんなで罰ゲーム。緊張もほぐれてきました!
アイスブレイクをはさんで、午前中最後のプログラムは人生曲線の記入と班での発表。
自分の今までの人生を振り返り、曲線の図に落とし込んでいきます。班内でお互いの人生曲線について質問し合いながら、自分の人生についての振り返りを深めてもらいました。

午後1番目のプログラムは、今春、日南市でのファームステイプログラムを手掛けた中央大学の渡邉 泰典さんによる講演。
取り組み内容や大事な心構えなどについて話をしてもらいました。

ピエロ姿での登場と風船の手品でみんなの心をがっちり掴んだ渡邉さん。プレゼンの仕方もとても勉強になります!実際に地域で活躍されている学生さんのお話を聞くことで、参加者の皆さんのモチベーションもぐっと上がったようです。
その後、ワークショップ『自分が住みたいと思う10年後の宮崎をイメージしてみよう』をワールドカフェ形式で行い、宮崎の良さや課題を再確認しました。
中には、「おいしいものを食べたいなら宮崎に来い!」という強気な“農業鎖国”といったユニークな意見も飛び出しました。
そして最後は、このインターンシップを通じての目標設定の時間。
現在の自分を自己分析し、このインターンシップを通じてどういう能力を伸ばしたいか、終わったときにどうなっていたいか、目標を設定してもらいました。

「自分の殻を破って成長したい!」、「地域に何か残したい!」という声が聞こえてきました。成長した姿が楽しみです!
参加者の皆さんには、この目標を胸に地域でたくさんのことを学び取ってほしいと思います。
事前研修お疲れ様でした!いってらっしゃい!

※『ヒムカ地域づくりインターンシップ』・・・県内各地の地域づくりの第一線で活躍するリーダーのもとで地域づくりの活動に取り組みつつ、実社会で求められるスキルを実践的に学んでいく、2週間から1か月のインターンシップのプログラムです。
まずは趣旨説明。参加者の学生さんも少し緊張気味です。

自己紹介に続いて、インプロに挑戦!
インプロとは即興劇のことですが、インプロを取り入れたゲームは、コミュニケーションを学ぶツールとして活用されています。隣の人に目だけで合図を送って同じタイミングで手をたたく「拍手ゲーム」など3種類のインプロで、『しっかり相手の目を見る、相手からの目線を受けとる』練習をしました。


失敗したらみんなで罰ゲーム。緊張もほぐれてきました!
アイスブレイクをはさんで、午前中最後のプログラムは人生曲線の記入と班での発表。
自分の今までの人生を振り返り、曲線の図に落とし込んでいきます。班内でお互いの人生曲線について質問し合いながら、自分の人生についての振り返りを深めてもらいました。

午後1番目のプログラムは、今春、日南市でのファームステイプログラムを手掛けた中央大学の渡邉 泰典さんによる講演。
取り組み内容や大事な心構えなどについて話をしてもらいました。

ピエロ姿での登場と風船の手品でみんなの心をがっちり掴んだ渡邉さん。プレゼンの仕方もとても勉強になります!実際に地域で活躍されている学生さんのお話を聞くことで、参加者の皆さんのモチベーションもぐっと上がったようです。
その後、ワークショップ『自分が住みたいと思う10年後の宮崎をイメージしてみよう』をワールドカフェ形式で行い、宮崎の良さや課題を再確認しました。
中には、「おいしいものを食べたいなら宮崎に来い!」という強気な“農業鎖国”といったユニークな意見も飛び出しました。
そして最後は、このインターンシップを通じての目標設定の時間。
現在の自分を自己分析し、このインターンシップを通じてどういう能力を伸ばしたいか、終わったときにどうなっていたいか、目標を設定してもらいました。

「自分の殻を破って成長したい!」、「地域に何か残したい!」という声が聞こえてきました。成長した姿が楽しみです!
参加者の皆さんには、この目標を胸に地域でたくさんのことを学び取ってほしいと思います。
事前研修お疲れ様でした!いってらっしゃい!

2014年08月27日
『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』第1回 企画力アップ講座を開催しました!
8月24日(日)に、全4回の連続講座『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』の第1弾、企画力アップ講座を開催しました!
第1回目の講師は、NPO法人 宮崎文化本舗の代表理事、石田達也さん。

石田さんは、宮崎県立宮崎商業高校卒業後、米国バージニア州オールド・ドミニオン大学に入学。1984年に同校中退。帰国後塾講師、飲食店を経営する傍ら、宮崎バージニア・ビーチ市姉妹都市協会を発足、初代事務局長に就任。1995年より宮崎映画祭実行委員会の初代事務局長に就任。ボランティア活動の限界を感じ、特定非営利活動法人宮崎文化本舗を2000年に設立。2014年から綾長役場エコパーク推進室まちづくり専門監としても活動。芸術文化のまちづくりと、ボランティア相互のネットワーク化を柱とした事業を中心に、様々な活動を行っていらっしゃいます。
今回はアイデアを具現化するための方法を、ワークショップを交えながら、「負けない企画を作る勘所」というテーマでお話いただきました!
※みなさん、勘所という言葉をご存知ですか?勘所は「はずすことのできない大事なところ、ポイント」という意味なのですが、語源は三味線を弾くときに弦を指で押さえる場所のことなのだそうです。

「将来、何を次世代に残すことができるのか?」
私たちが背負っている日本の負債、減少していく人口・・・そんななかで小さいことでも何か行動を起こしていかなくてはならない、という現状が根底にあるという石田さん。
助成金が首をしめる!?
「助成金を取るための企画」は、むしろ首をしめることがあるといいます。例えば、助成金は2分の1補助がほとんど。では、残りの2分の1の資金はどうするのか・・・自分たちが何がしたいのかをしっかりもっていないと、お金に振り回され最低な企画になってしまいます。
何がしたいのか、どのように行うのか・・・企画をしっかり練ることが大切です。
5W1H+α
誰がするの? どうやってするの? いつするの? 何をするの? どのぐらいするんの?
いくらかかるの? 誰のためにするの?
特に誰のためにやるのか、ということを明確にすることで、分かりやすい企画になるそうです。
○グループワーク○
後半は、まず個人で考えた企画をグループで発表し合い、その中から「緊急性・重要性」の特に高い事業をグループで1つ選んで、メンバーで意見を出し合い、ブラッシュアップするワークショップを行いました。

講座で学んだポイントを元に、班で企画を練ります。みなさん、熱心に議論を交わし、時間内に収まらないほど盛り上がるワークショップになりました!

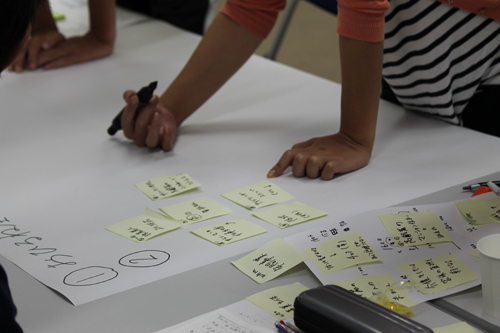
「小児がん経験者と家族のための交流キャンプの開催」事業から「おひるね屋を通した高齢者交流スペースの創出」事業まで、多様な5つの企画が発表されました。

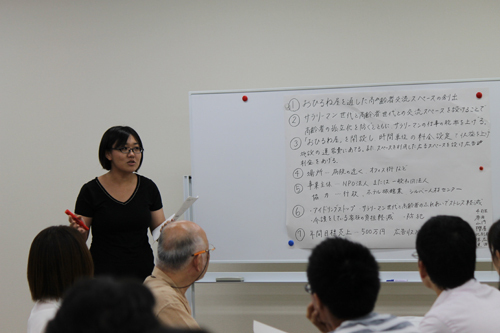
参加者からは、
○「勘所」の整理、数字や視覚的材料を活かしたプレゼン等、勉強になりました。
○企画のツボ・・・具体的な日程、スケジューリング、賛同できるものをクリアにすることが分かりました。「誰のための企画」なのかしっかり考えたいです。
○企画書を書くことは難しいことですが、この部分をしっかりと行うことが、事業を滞りなく、また失敗しても修正するのに大切であることが分かった。また、大変理解しやすかった。
といったご意見・ご感想をいただきました。
石田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
次回の『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』は第2回・ファシリテーション講座です。
第1回目の講師は、NPO法人 宮崎文化本舗の代表理事、石田達也さん。

石田さんは、宮崎県立宮崎商業高校卒業後、米国バージニア州オールド・ドミニオン大学に入学。1984年に同校中退。帰国後塾講師、飲食店を経営する傍ら、宮崎バージニア・ビーチ市姉妹都市協会を発足、初代事務局長に就任。1995年より宮崎映画祭実行委員会の初代事務局長に就任。ボランティア活動の限界を感じ、特定非営利活動法人宮崎文化本舗を2000年に設立。2014年から綾長役場エコパーク推進室まちづくり専門監としても活動。芸術文化のまちづくりと、ボランティア相互のネットワーク化を柱とした事業を中心に、様々な活動を行っていらっしゃいます。
今回はアイデアを具現化するための方法を、ワークショップを交えながら、「負けない企画を作る勘所」というテーマでお話いただきました!
※みなさん、勘所という言葉をご存知ですか?勘所は「はずすことのできない大事なところ、ポイント」という意味なのですが、語源は三味線を弾くときに弦を指で押さえる場所のことなのだそうです。

「将来、何を次世代に残すことができるのか?」
私たちが背負っている日本の負債、減少していく人口・・・そんななかで小さいことでも何か行動を起こしていかなくてはならない、という現状が根底にあるという石田さん。
助成金が首をしめる!?
「助成金を取るための企画」は、むしろ首をしめることがあるといいます。例えば、助成金は2分の1補助がほとんど。では、残りの2分の1の資金はどうするのか・・・自分たちが何がしたいのかをしっかりもっていないと、お金に振り回され最低な企画になってしまいます。
何がしたいのか、どのように行うのか・・・企画をしっかり練ることが大切です。
5W1H+α
誰がするの? どうやってするの? いつするの? 何をするの? どのぐらいするんの?
いくらかかるの? 誰のためにするの?
特に誰のためにやるのか、ということを明確にすることで、分かりやすい企画になるそうです。
○グループワーク○
後半は、まず個人で考えた企画をグループで発表し合い、その中から「緊急性・重要性」の特に高い事業をグループで1つ選んで、メンバーで意見を出し合い、ブラッシュアップするワークショップを行いました。

講座で学んだポイントを元に、班で企画を練ります。みなさん、熱心に議論を交わし、時間内に収まらないほど盛り上がるワークショップになりました!

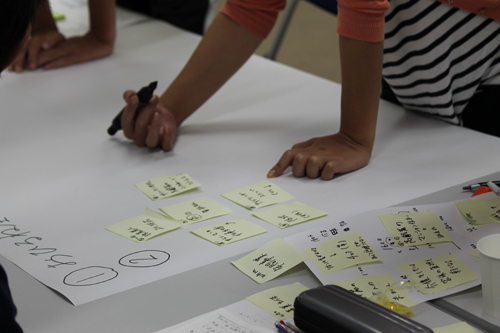
「小児がん経験者と家族のための交流キャンプの開催」事業から「おひるね屋を通した高齢者交流スペースの創出」事業まで、多様な5つの企画が発表されました。

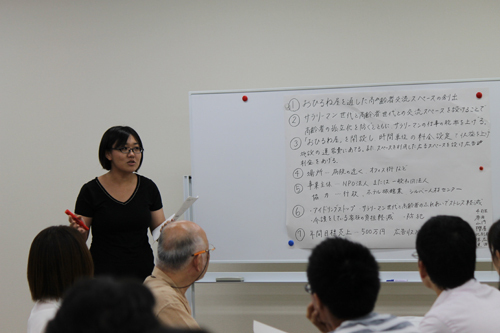
参加者からは、
○「勘所」の整理、数字や視覚的材料を活かしたプレゼン等、勉強になりました。
○企画のツボ・・・具体的な日程、スケジューリング、賛同できるものをクリアにすることが分かりました。「誰のための企画」なのかしっかり考えたいです。
○企画書を書くことは難しいことですが、この部分をしっかりと行うことが、事業を滞りなく、また失敗しても修正するのに大切であることが分かった。また、大変理解しやすかった。
といったご意見・ご感想をいただきました。
石田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
次回の『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』は第2回・ファシリテーション講座です。
2014年08月01日
『地域版ヒムカレッジvol.1』開催しました!
7月30日(水)に、本年度第1弾、地域版ヒムカレッジ「木のおもちゃと子どもの育成~木育を通じて、地域の中で子どもの豊かな心を育むには?~」を日南市ふれあい健やかセンターで開催いたしました!
今回の講師は、東京おもちゃ美術館 多田千尋館長。

東京おもちゃ美術館は、閉校した小学校を再利用し、多田館長が理事長を務めるNPO法人グッド・トイ委員会が運営しています。
「おもちゃはただの物ではなく、子ども同士はもちろん、親と子、人と地域…あらゆる人と人を繋いでいる。」という考えをもとに、おもちゃという魔法のコミュニケーション・ツールを使った壮大な実践の中心を担っています。
また、多田館長は、赤ちゃんの成長・発達とおもちゃの関わりから、お年寄りのリハビリ、ヒーリングおもちゃまで、幅広い視点でおもちゃを捉える「おもちゃコンサルタント」の養成にも力を入れられています。

今回は「木育」をテーマに、会場にも多数の木のおもちゃを展示し、参加者の皆さんに見ていただきながら講座を行いました。

まずは東京おもちゃ美術館での調査・研究に裏付けられた、木や木のおもちゃが親子に与える影響をお話いただきました。おもちゃ美術館の「赤ちゃん木育ひろば」は、全国各地の杉材を内装や家具、おもちゃに使用していているそうです。筑波大と埼玉大が木材を使用していない同様の施設との違いを効果測定した結果、次の3点の効果が測定されたとのこと。
・赤ちゃんが泣かない。
・ママが携帯(の操作)をしない。
・パパの滞在時間が長い。
参加者の方々は、「木に触れていると、赤ちゃんが泣かない」という話が特に印象に残られたようでした。
また、その他おもちゃ選びの大切さや、「乳幼児は遊びの天才」であること、幼児教育での木育のすすめなどについてお話をいただき、参加者の方々は熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

乳幼児は
・繰り返しを楽しむ天才 ・ききたがりの天才 ・ユーモアの天才
今回ご紹介していた木のおもちゃにも、そんな乳幼児が満足できる工夫がたくさんありました。乳幼児期に自然に触れることが、子どもの感性に大きく影響するそうです。

講座終了後、展示した木のおもちゃに触っていただける時間を設けました。夢中になって遊んでいただけたようです!
今回の講座を通じて、子どもに木や自然に触れさせる機会をどう作っていくのか、考える機会になったのではないかと感じました。
参加者からは、
○木育・自然とのふれあいの大切さを改めて感じることができた。
○0歳から6歳のときに、自然に対してわくわくさせる体験をする重要性を再認識できた。
○活動のすべてが感動的だった。
○飫肥杉は「隠された日本の宝」もっと日南市民にも知ってほしい。
といったご意見・ご感想をいただきました。
多田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
今回の講師は、東京おもちゃ美術館 多田千尋館長。

東京おもちゃ美術館は、閉校した小学校を再利用し、多田館長が理事長を務めるNPO法人グッド・トイ委員会が運営しています。
「おもちゃはただの物ではなく、子ども同士はもちろん、親と子、人と地域…あらゆる人と人を繋いでいる。」という考えをもとに、おもちゃという魔法のコミュニケーション・ツールを使った壮大な実践の中心を担っています。
また、多田館長は、赤ちゃんの成長・発達とおもちゃの関わりから、お年寄りのリハビリ、ヒーリングおもちゃまで、幅広い視点でおもちゃを捉える「おもちゃコンサルタント」の養成にも力を入れられています。

今回は「木育」をテーマに、会場にも多数の木のおもちゃを展示し、参加者の皆さんに見ていただきながら講座を行いました。

まずは東京おもちゃ美術館での調査・研究に裏付けられた、木や木のおもちゃが親子に与える影響をお話いただきました。おもちゃ美術館の「赤ちゃん木育ひろば」は、全国各地の杉材を内装や家具、おもちゃに使用していているそうです。筑波大と埼玉大が木材を使用していない同様の施設との違いを効果測定した結果、次の3点の効果が測定されたとのこと。
・赤ちゃんが泣かない。
・ママが携帯(の操作)をしない。
・パパの滞在時間が長い。
参加者の方々は、「木に触れていると、赤ちゃんが泣かない」という話が特に印象に残られたようでした。
また、その他おもちゃ選びの大切さや、「乳幼児は遊びの天才」であること、幼児教育での木育のすすめなどについてお話をいただき、参加者の方々は熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

乳幼児は
・繰り返しを楽しむ天才 ・ききたがりの天才 ・ユーモアの天才
今回ご紹介していた木のおもちゃにも、そんな乳幼児が満足できる工夫がたくさんありました。乳幼児期に自然に触れることが、子どもの感性に大きく影響するそうです。

講座終了後、展示した木のおもちゃに触っていただける時間を設けました。夢中になって遊んでいただけたようです!
今回の講座を通じて、子どもに木や自然に触れさせる機会をどう作っていくのか、考える機会になったのではないかと感じました。
参加者からは、
○木育・自然とのふれあいの大切さを改めて感じることができた。
○0歳から6歳のときに、自然に対してわくわくさせる体験をする重要性を再認識できた。
○活動のすべてが感動的だった。
○飫肥杉は「隠された日本の宝」もっと日南市民にも知ってほしい。
といったご意見・ご感想をいただきました。
多田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!
2014年04月04日
『みやざきPVづくりインターンシップ 報告会&講演会』開催しました!
3月29日(土)に、『みやざきPVづくりインターンシップ 報告会&講演会』を開催しました!
『みやざきPV(プロモーションビデオ)づくりインターンシップ』とは、県内の3つの地域(五ヶ瀬・日南市油津・西都市銀鏡)を大学生が直接訪問し、取材から映像編集までを全て自分達の手で行い、3分間のPV(プロモーションビデオ)を創り上げる約1ヶ月間のインターンプログラムです。
MRT宮崎放送 報道制作局専任局長の紫安伸一さんを講師に迎えての講演からスタートしました。

紫安伸一さんは平成23年に日本民間放送連盟賞のラジオ教養番組部門で優秀賞に選ばれた「戦艦大和沖縄特攻作戦~護衛艦隊生存者の証~」 や、(http://www.j-ba.or.jp/category/awards/jba100938)宮崎駅、都城駅、吉都線の100周年を記念し鉄道映像をまとめたDVD「宮崎鉄道物語」(http://www.the-miyanichi.co.jp/horou/_4813.html)等をてがけられ、現在は「わけもんGT」やドキュメンタリー番組などの制作をされています。
紫安さんには「ローカルメディアの未来 ~地方放送局が地域のなかで果たす役割とは?~」と題し、お話を伺いました。
初めにMRTが制作している番組をご紹介して頂きました。紫安さんが手がけられている「わけモンGT」は今では視聴率20%を超えるなMRT制作の番組を代表する一つとなっています。
そして今年で開局60周年を迎えるMRTの歴史と放送局の仕事を紹介するDVDを見ながら紫安さんに解説していただきました。

■ローカル局の役割
30年くらい前までは「ローカル局の番組なんてあってもなくてもいいんだ」という風潮があったといいます。
しかし紫安さんはその頃に全国で一番早く30分の夕方のニュース番組を始められました。視聴率も25%を記録するなど確かにローカルニュースの需要というものはあったそうです。

MRTの自社制作番組「わけもん!GT」当初は「ローカル番組がゴールデンタイムに進出するなんて失敗する」という周りの声があったそうですが、取材先での地域の人々からの「いつも見てるよ」という温かい声と同時に、これまでの朝や夕方の番組の制作以上の認知度や手応えを感じ、モチベーションやスキルのアップに繋げていったそうです。
そんな中でローカル局の役割として、「地域活性化のために地方局はあり、価値ある情報を見つけ、際立たせ、放送し、視聴者に役立ててもらうことが重要」だと語る紫安さん。そしてそれを伝える記者やディレクターは情報のフィルターとして重要であり、好奇心と知識、謙虚さと積極性の両方が必要であるとも話されました。
また地域密着が行き過ぎて地域癒着になってしまわないように気をつけることも大事だと話されました。
そしてインターンシップに参加した大学生や若い世代に向けて、「若い時代にいろんな地域に行き、様々な価値観や情報に触れ、幅広いものの見方を学んで欲しい」と話されました。
最後に紫安さんが仰った「いい番組を作っていけば、ローカル局の番組でもみんな見てくれる」という言葉が印象的でした。

質問タイムでは
「報道人として働きたいと思ったきっかけは?」という参加者からの質問に紫安さんは
「東京のキー局でバイトをしている時に出来たアメリカのCNNに影響され報道の仕事をしたい思った。しかし報道志望で入ったが営業部に配属されました。それから10年間ぐらいは営業の仕事をやったが、腐らず自分の信念を持ち、食らいついて何とか報道の仕事に就けました」と答えられました。
普段慣れ親しんでいるローカル番組にも、的確に情報を伝えるための工夫や努力、そして地域を活性化したいという思いの元に制作されているんだということを学ばせて頂いた紫安さんの講演でした。
そしていよいよ「みやざきPVづくりインターンシップ」に参加した大学生たちが制作したPV(プロモーションビデオ)の上映会及び報告会が始まりました。

9人の大学生が映像づくりを一から学び、3チームが3つの地域(五ヶ瀬・日南市油津・西都市銀鏡)に分かれ、取材から映像編集までを全て自分達の手で行い、3分間のPVを制作しました。
PVの上映会(3分)と報告会(5分)という形でそれぞれ3チームに発表して頂きました。
トップバッターは日南市・油津チームです。

テーマ「油津再生物語はここから始まる」
(テーマ設定の理由)
・「油津商店街を良くしたい」と心のそこから思っている方々が日ごろ感じることを沢山の方々に知ってほしいため。
・商店街再生へ向けての動きを知ってほしいため
・油津再生物語はここ(商店街)から始まるものであると感じたため
商店街の人々のインタビューを中心に、油津再生に向けての思いとテナントミックスサポートマネージャーとして油津商店街の活性化に貢献している木藤亮太さんの活動への思い、そして最後に木藤さん自身の油津再生に向けての思いを伝える形のPVとなっていました。
(今回のプログラムに挑戦してみての感想)
「自分の聞きたいお話を、聞き出すには長い間映像を撮らないと聞き出せないんだということを改めて感じました。」
「商店街に住んでいるたくさんの人とお話することで、親近感を持ち油津のことが大好きになりました。これからも応援していきたいです。」
「たくさんの材料があっても、伝えたいことを形にできるのはほんの一握りで、ものづくりの大変さを知りました。」
紫安さんのコメント
「ナレーションやテロップで何をしている人達なのかを説明したほうが分かりやすい。地域の人達とは上手く溶け込んでいた。文字のフォントの選び方も良かった」
花堂監督のコメント
「インタビューの順番が分かりやすくなかった。木藤さんの思いや商店街の人との関係性が分かりづらかった。思いを伝えるための情報量がもっと欲しかった」

そして会場にお越し頂いた木藤さんは、
「本当に商店街に溶け込んで取材していて、僕が行っても聞けないような話しを聞けていたと感じました。商店街のお店でも流したりもしてみたい。3分間に絞っていくのは大変だったと思う。今度は是非とも15分バージョンも作って欲しいです。」
といったコメントをいただきました。
続いて、西都市・銀鏡チーム。

テーマ「神とともに生きる人々」
(テーマ設定の理由)
・「ここには何もないけれど、銀鏡神社と神楽がある」「私たちには伝統を伝えていくことしかできない」という言葉から
・銀鏡の存続を真剣に考える住民の姿を見たから
・住民の行政への願いを伝えたい
銀鏡の自然や伝統文化の映像と、銀鏡に住む子どもたちと銀鏡地区の区長 浜砂重忠さんの銀鏡に対する思いをインタビューを通して伝える形のPVとなっていました。
(今回のプログラムに挑戦してみての感想)
「自分が知らないだけで宮崎には楽しい地域がたくさんあると思った。いろんな地域に行ってみたい。」
「どのようにすれば上手く伝わるかを試行錯誤することがとても楽しかった」
「映像編集の大変さも感じたが、一つ一つ出来る様になり達成感があった」
紫安さんのコメント
「映像が情緒があって綺麗でした。シーンの繋げ方も良かった。神楽を写真で表現したのも逆に効果的だったと思う。重忠さんの肩書きを入れると良かった」
花堂監督のコメント
「自分が出会った「好き」っていうのが良く出てて見やすかった。情緒が出ていて良かった。音楽の使い方も情感的だった」
最後は、五ヶ瀬チームです。

テーマ「五ヶ瀬物語」
(テーマ設定の理由)
・五ヶ瀬の魅力を伝え安らぎの場へ誘いたい
仕事に疲れたサラリーマンが五ヶ瀬に行き、五ヶ瀬の自然や食べ物や人に出会い、癒されていくというドラマ仕立てのPVとなっていました。
(今回のプログラムに挑戦してみての感想)
「だんだんと五ヶ瀬の魅力に惹かれていった」
「映像作品を作る難しさを感じた」
「PVを見る人々に五ヶ瀬の魅力を伝え、興味をもっていただきたい」
紫安さんのコメント
「構成が凝っていて面白かった。映像も美しかった。文字は映像に被せていった方がいいと思った。」
花堂監督のコメント
「映像が好きだということが撮り方やカメラワークで伝わった。比重的に後半の人々の映像がもっとあった方が、伝えたいものが伝わると感じた」

総評
紫安さんのコメント
「みんな初めて行く所で、いろいろ感じたことを映像にしていて良かった。まだまだ宮崎には良い所があるので是非とも足を運んでほしいです。」
花堂監督のコメント
「かなりの短期での制作でしたが、良くここまで辿り着いたなと感じた。この体験を通して、地域と向き合った感覚や夢中になれたことを自分たちの中に活かしてほしい。もう少し映像にも手を加えたら更に良くなると思うので、今日の皆さんからの感想も受け止めてまた作っていって欲しい」
3チームそれぞれの色があって、どのチームも地域と向き合い、地域の魅力やそこにいる人々の思いが伝わってくるPVだったなと感じました。
今回制作したPVはHPでの配信や宮崎キネマ館での上映を予定しております。そちらもお楽しみにして下さい。
参加者からは、
「ローカルメディアの現場がわかってよかったです。「わけもん」はゴールデンタイムに流れることで、家族が見る機会が増えました。とても楽しみに見ています、ありがとうございました。」
「テレビやラジオを通じた地域活性化、地域への想いが伝わりました。また、報道の仕事に就くことをあきらめなかったということを聴き、私も自分の夢などをかなえるためにはあきらめず頑張ることが必要であると教えられました。これからも地域に根ざした番組を制作してください。」
「作品は短期間でと考えたら本当にすばらしいものでした。できればこれで終わらず、うまく続けて先生方のアドバイスを参考にされて、良い作品に仕上げてください。学生だからこそ気付いたこと、聞き出せたことがきっとあるはず。
」
「大学生の皆さんが地域に入り、地域と向き合ったからこそ、皆さんの感じた地域の魅力が伝わってきたと感じています。音や映像にもこだわって、良かったです。」
「未来を担う学生が大切にしたいものが、今回のPVでわかりました。見ていて楽しかったです。」
といったご意見・ご感想をいただきました。
映像と地域づくりでは一見遠いような存在ですが、今回の紫安さんのローカル局の役割についての講演や学生たちが制作したPVを観て、地域と向き合い、地域の魅力や思いを伝える方法として、この二つを掛け合わせればとても効果的なものになるということを強く感じました。
講師の紫安さん、花堂監督、みやざきPVづくりインターンシップに参加した大学生、そして報告会&講演会に参加していただいた皆様ありがとうございました!
『みやざきPV(プロモーションビデオ)づくりインターンシップ』とは、県内の3つの地域(五ヶ瀬・日南市油津・西都市銀鏡)を大学生が直接訪問し、取材から映像編集までを全て自分達の手で行い、3分間のPV(プロモーションビデオ)を創り上げる約1ヶ月間のインターンプログラムです。
MRT宮崎放送 報道制作局専任局長の紫安伸一さんを講師に迎えての講演からスタートしました。

紫安伸一さんは平成23年に日本民間放送連盟賞のラジオ教養番組部門で優秀賞に選ばれた「戦艦大和沖縄特攻作戦~護衛艦隊生存者の証~」 や、(http://www.j-ba.or.jp/category/awards/jba100938)宮崎駅、都城駅、吉都線の100周年を記念し鉄道映像をまとめたDVD「宮崎鉄道物語」(http://www.the-miyanichi.co.jp/horou/_4813.html)等をてがけられ、現在は「わけもんGT」やドキュメンタリー番組などの制作をされています。
紫安さんには「ローカルメディアの未来 ~地方放送局が地域のなかで果たす役割とは?~」と題し、お話を伺いました。
初めにMRTが制作している番組をご紹介して頂きました。紫安さんが手がけられている「わけモンGT」は今では視聴率20%を超えるなMRT制作の番組を代表する一つとなっています。
そして今年で開局60周年を迎えるMRTの歴史と放送局の仕事を紹介するDVDを見ながら紫安さんに解説していただきました。

■ローカル局の役割
30年くらい前までは「ローカル局の番組なんてあってもなくてもいいんだ」という風潮があったといいます。
しかし紫安さんはその頃に全国で一番早く30分の夕方のニュース番組を始められました。視聴率も25%を記録するなど確かにローカルニュースの需要というものはあったそうです。

MRTの自社制作番組「わけもん!GT」当初は「ローカル番組がゴールデンタイムに進出するなんて失敗する」という周りの声があったそうですが、取材先での地域の人々からの「いつも見てるよ」という温かい声と同時に、これまでの朝や夕方の番組の制作以上の認知度や手応えを感じ、モチベーションやスキルのアップに繋げていったそうです。
そんな中でローカル局の役割として、「地域活性化のために地方局はあり、価値ある情報を見つけ、際立たせ、放送し、視聴者に役立ててもらうことが重要」だと語る紫安さん。そしてそれを伝える記者やディレクターは情報のフィルターとして重要であり、好奇心と知識、謙虚さと積極性の両方が必要であるとも話されました。
また地域密着が行き過ぎて地域癒着になってしまわないように気をつけることも大事だと話されました。
そしてインターンシップに参加した大学生や若い世代に向けて、「若い時代にいろんな地域に行き、様々な価値観や情報に触れ、幅広いものの見方を学んで欲しい」と話されました。
最後に紫安さんが仰った「いい番組を作っていけば、ローカル局の番組でもみんな見てくれる」という言葉が印象的でした。

質問タイムでは
「報道人として働きたいと思ったきっかけは?」という参加者からの質問に紫安さんは
「東京のキー局でバイトをしている時に出来たアメリカのCNNに影響され報道の仕事をしたい思った。しかし報道志望で入ったが営業部に配属されました。それから10年間ぐらいは営業の仕事をやったが、腐らず自分の信念を持ち、食らいついて何とか報道の仕事に就けました」と答えられました。
普段慣れ親しんでいるローカル番組にも、的確に情報を伝えるための工夫や努力、そして地域を活性化したいという思いの元に制作されているんだということを学ばせて頂いた紫安さんの講演でした。
そしていよいよ「みやざきPVづくりインターンシップ」に参加した大学生たちが制作したPV(プロモーションビデオ)の上映会及び報告会が始まりました。

9人の大学生が映像づくりを一から学び、3チームが3つの地域(五ヶ瀬・日南市油津・西都市銀鏡)に分かれ、取材から映像編集までを全て自分達の手で行い、3分間のPVを制作しました。
PVの上映会(3分)と報告会(5分)という形でそれぞれ3チームに発表して頂きました。
トップバッターは日南市・油津チームです。

テーマ「油津再生物語はここから始まる」
(テーマ設定の理由)
・「油津商店街を良くしたい」と心のそこから思っている方々が日ごろ感じることを沢山の方々に知ってほしいため。
・商店街再生へ向けての動きを知ってほしいため
・油津再生物語はここ(商店街)から始まるものであると感じたため
商店街の人々のインタビューを中心に、油津再生に向けての思いとテナントミックスサポートマネージャーとして油津商店街の活性化に貢献している木藤亮太さんの活動への思い、そして最後に木藤さん自身の油津再生に向けての思いを伝える形のPVとなっていました。
(今回のプログラムに挑戦してみての感想)
「自分の聞きたいお話を、聞き出すには長い間映像を撮らないと聞き出せないんだということを改めて感じました。」
「商店街に住んでいるたくさんの人とお話することで、親近感を持ち油津のことが大好きになりました。これからも応援していきたいです。」
「たくさんの材料があっても、伝えたいことを形にできるのはほんの一握りで、ものづくりの大変さを知りました。」
紫安さんのコメント
「ナレーションやテロップで何をしている人達なのかを説明したほうが分かりやすい。地域の人達とは上手く溶け込んでいた。文字のフォントの選び方も良かった」
花堂監督のコメント
「インタビューの順番が分かりやすくなかった。木藤さんの思いや商店街の人との関係性が分かりづらかった。思いを伝えるための情報量がもっと欲しかった」

そして会場にお越し頂いた木藤さんは、
「本当に商店街に溶け込んで取材していて、僕が行っても聞けないような話しを聞けていたと感じました。商店街のお店でも流したりもしてみたい。3分間に絞っていくのは大変だったと思う。今度は是非とも15分バージョンも作って欲しいです。」
といったコメントをいただきました。
続いて、西都市・銀鏡チーム。

テーマ「神とともに生きる人々」
(テーマ設定の理由)
・「ここには何もないけれど、銀鏡神社と神楽がある」「私たちには伝統を伝えていくことしかできない」という言葉から
・銀鏡の存続を真剣に考える住民の姿を見たから
・住民の行政への願いを伝えたい
銀鏡の自然や伝統文化の映像と、銀鏡に住む子どもたちと銀鏡地区の区長 浜砂重忠さんの銀鏡に対する思いをインタビューを通して伝える形のPVとなっていました。
(今回のプログラムに挑戦してみての感想)
「自分が知らないだけで宮崎には楽しい地域がたくさんあると思った。いろんな地域に行ってみたい。」
「どのようにすれば上手く伝わるかを試行錯誤することがとても楽しかった」
「映像編集の大変さも感じたが、一つ一つ出来る様になり達成感があった」
紫安さんのコメント
「映像が情緒があって綺麗でした。シーンの繋げ方も良かった。神楽を写真で表現したのも逆に効果的だったと思う。重忠さんの肩書きを入れると良かった」
花堂監督のコメント
「自分が出会った「好き」っていうのが良く出てて見やすかった。情緒が出ていて良かった。音楽の使い方も情感的だった」
最後は、五ヶ瀬チームです。

テーマ「五ヶ瀬物語」
(テーマ設定の理由)
・五ヶ瀬の魅力を伝え安らぎの場へ誘いたい
仕事に疲れたサラリーマンが五ヶ瀬に行き、五ヶ瀬の自然や食べ物や人に出会い、癒されていくというドラマ仕立てのPVとなっていました。
(今回のプログラムに挑戦してみての感想)
「だんだんと五ヶ瀬の魅力に惹かれていった」
「映像作品を作る難しさを感じた」
「PVを見る人々に五ヶ瀬の魅力を伝え、興味をもっていただきたい」
紫安さんのコメント
「構成が凝っていて面白かった。映像も美しかった。文字は映像に被せていった方がいいと思った。」
花堂監督のコメント
「映像が好きだということが撮り方やカメラワークで伝わった。比重的に後半の人々の映像がもっとあった方が、伝えたいものが伝わると感じた」

総評
紫安さんのコメント
「みんな初めて行く所で、いろいろ感じたことを映像にしていて良かった。まだまだ宮崎には良い所があるので是非とも足を運んでほしいです。」
花堂監督のコメント
「かなりの短期での制作でしたが、良くここまで辿り着いたなと感じた。この体験を通して、地域と向き合った感覚や夢中になれたことを自分たちの中に活かしてほしい。もう少し映像にも手を加えたら更に良くなると思うので、今日の皆さんからの感想も受け止めてまた作っていって欲しい」
3チームそれぞれの色があって、どのチームも地域と向き合い、地域の魅力やそこにいる人々の思いが伝わってくるPVだったなと感じました。
今回制作したPVはHPでの配信や宮崎キネマ館での上映を予定しております。そちらもお楽しみにして下さい。
参加者からは、
「ローカルメディアの現場がわかってよかったです。「わけもん」はゴールデンタイムに流れることで、家族が見る機会が増えました。とても楽しみに見ています、ありがとうございました。」
「テレビやラジオを通じた地域活性化、地域への想いが伝わりました。また、報道の仕事に就くことをあきらめなかったということを聴き、私も自分の夢などをかなえるためにはあきらめず頑張ることが必要であると教えられました。これからも地域に根ざした番組を制作してください。」
「作品は短期間でと考えたら本当にすばらしいものでした。できればこれで終わらず、うまく続けて先生方のアドバイスを参考にされて、良い作品に仕上げてください。学生だからこそ気付いたこと、聞き出せたことがきっとあるはず。
」
「大学生の皆さんが地域に入り、地域と向き合ったからこそ、皆さんの感じた地域の魅力が伝わってきたと感じています。音や映像にもこだわって、良かったです。」
「未来を担う学生が大切にしたいものが、今回のPVでわかりました。見ていて楽しかったです。」
といったご意見・ご感想をいただきました。
映像と地域づくりでは一見遠いような存在ですが、今回の紫安さんのローカル局の役割についての講演や学生たちが制作したPVを観て、地域と向き合い、地域の魅力や思いを伝える方法として、この二つを掛け合わせればとても効果的なものになるということを強く感じました。
講師の紫安さん、花堂監督、みやざきPVづくりインターンシップに参加した大学生、そして報告会&講演会に参加していただいた皆様ありがとうございました!
2014年03月25日
『地域版ヒムカレッジvol.3 銀鏡で学ぶ地域づくり講座』
3月19日(水)に、「地域版ヒムカレッジvol.3」を開催いたしました!
今回は地域版ヒムカレッジとしては過去最多の47名の方にお越しいただきました!
今回の講師はNPO法人iさいと代表理事の井上優さん。

井上さんは昭和57年に東海大学文学部史学科 日本史専攻課程を卒業され、昭和57年~昭和61年3月まで(株)細川活版所にて商品開発・企画を担当。昭和61年~平成11年3月まで社会福祉法人の経営を行なわれ、現在は(特活)宮崎文化本舗副代表理事、宮崎県NPO活動支援センター・センター長、(特活)ⅰさいと代表理事、(特活)NPO事業サポートセンター理事、(一社)ユニバーサル社会創造支援センター理事など多岐に渡り活躍されています。
井上さんには「これからの銀鏡を語る ~世界遺産登録活動への展開を視野に入れて~」というテーマでお話いただきました。

■銀鏡という地域を「あなたは何で覚えられたいですか?」
神楽・山村留学・山の生活・豊かな食(猪・椎茸・ゆず)など様々な魅力がある銀鏡ですが、何よりも「人」がその最たる魅力だと話す井上さん。
平成24年度に実施された銀鏡・上揚地区自立促進事業「ひったまげたプロジェクト」での地域おこし講演会や銀鏡のお宝マッピング、郷土料理の試食会など様々な取り組みも紹介されました。
その時に参加した学生たちの感想として、銀鏡川や布水の滝など地域資源の素晴らしさやおもてなしがとても嬉しかったなどがありました。
しかし同時に同じような滝や川は他の所にもあるといった感想も出ており、差別化を図るにはアピールする材料や物語を語ることが必要なのだと話されました。
他にも自分の居場所や頼りにされているという感想もあり、そう思わせる地域の雰囲気づくりも大事なことなのだそうです。
また「住民の方々と沢山の話ができ、とても楽しかった」や「人生のアドバイスなど聴く事ができ、ためになった」など、人と人との繋がりや出会いの大切さを感じる声も多くありました。
そして「銀鏡に来ないと食べられないものに感動した」という感想もあり、井上さんは逆に言えばそれは銀鏡の住民はいつも食べているものであり住民にとっては当たり前だが、他所から来た人にとってはそれが当たり前ではなく魅力になるのだと話されました。

■発地型観光から地域主導型観光(行こうよ→おいでよ)
地域の自然、生活、文化を肌で感じ、地域の人々とのふれあいを求める体験・学習・交流型ツーリズムのニーズが高まっている昨今。
地域の生活者がつくる生活感のある地域主導型の観光や地域ぐるみの「おもてなし」、そして地域の住民も新しい発見や喜びを「おすそわけ」をすることが必要だということでした。
そういったなかで、で井上さんから銀鏡の足元にあるもの全てを博物館に見立てた屋根のない生活の博物館「銀鏡まるごとミュージアム」という提案が出されました。都市と農村との交流促進やコーディネーターの育成(行政からの自立)など様々な角度から銀鏡の活性化に繋がる展開が含まれており住民の方々の意識の向上も図られているのだと感じました。

■世界遺産登録活動へ
まず世界遺産に関する条約がどのような種類に分けられるのか、そして実際に登録された日本の世界遺産などを紹介していただきました。
無形文化遺産になっている岩手県の早池峰神楽を例に挙げ、なぜこの神楽が選ばれたのかは「室町時代に能が大成する以前の姿をうかがわせるなどの特色がある」などといった理由付けがしっかりとされているからだと話す井上さん。
また世界遺産登録には、何よりも住民の熱意と子どもから大人まで「銀鏡の神楽は凄いんだ」という意識を持つことが大切であり、そういった意識の中で活動をしていけば銀鏡の未来は明るいと話されました。
最後に「銀鏡の魅力を銀鏡に住む住民の方々がもう一回再認識していくことが大事なことなのではないか」と話され講座は終了しました。

質問タイムでは
「世界遺産になった場合、良い面もあるが悪い面も出てくると思うのですが、どういった事がでてくるのでしょうか?」という参加者からの質問に井上さんは
「人がたくさん来るようになる。そうした時にルールのない人がたくさん来ます。例えば「ゴミを捨てたらいけない」というルールを守れない人が出てくる。100人だったら捨てないけど1000人だったら捨ててしまう。その結果その場所が汚れてしまうというような事が出てきます。なのでしっかりとしたルール作りが必要になって来ると思います。」と答えられました。
参加者からは、
「観光は、地元の「人」が大事な事が分かりました。他人事では何も進まないこと。」
「時には、表面だけでなく、少し深く考えたり、見たりしなければ、と思いました。そして未来につないでいかなければいけない。」
「自分たちの村を見直すことができた。」
「銀鏡が好きだけど、銀鏡の好きな場所3ケ所が答えられなかったのがショックでした。銀鏡でしか食べられない物って何なのでしょうか?」
「地区の光になる所を掘り出し、地区外からの多くの人々に来てもらいたい。」
といったご意見・ご感想をいただきました。
今回の講座で、銀鏡という地域にはまだまだ人を呼び寄せる魅力がたくさんあるんだということに気づかされました。そして、改めて自分達の地域を見直すことや、自分達では当たり前と思っている食や文化など、それこそが他所の人から見た地域の魅力に繋がっているんだということも強く感じました。
井上さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!
今回は地域版ヒムカレッジとしては過去最多の47名の方にお越しいただきました!
今回の講師はNPO法人iさいと代表理事の井上優さん。

井上さんは昭和57年に東海大学文学部史学科 日本史専攻課程を卒業され、昭和57年~昭和61年3月まで(株)細川活版所にて商品開発・企画を担当。昭和61年~平成11年3月まで社会福祉法人の経営を行なわれ、現在は(特活)宮崎文化本舗副代表理事、宮崎県NPO活動支援センター・センター長、(特活)ⅰさいと代表理事、(特活)NPO事業サポートセンター理事、(一社)ユニバーサル社会創造支援センター理事など多岐に渡り活躍されています。
井上さんには「これからの銀鏡を語る ~世界遺産登録活動への展開を視野に入れて~」というテーマでお話いただきました。

■銀鏡という地域を「あなたは何で覚えられたいですか?」
神楽・山村留学・山の生活・豊かな食(猪・椎茸・ゆず)など様々な魅力がある銀鏡ですが、何よりも「人」がその最たる魅力だと話す井上さん。
平成24年度に実施された銀鏡・上揚地区自立促進事業「ひったまげたプロジェクト」での地域おこし講演会や銀鏡のお宝マッピング、郷土料理の試食会など様々な取り組みも紹介されました。
その時に参加した学生たちの感想として、銀鏡川や布水の滝など地域資源の素晴らしさやおもてなしがとても嬉しかったなどがありました。
しかし同時に同じような滝や川は他の所にもあるといった感想も出ており、差別化を図るにはアピールする材料や物語を語ることが必要なのだと話されました。
他にも自分の居場所や頼りにされているという感想もあり、そう思わせる地域の雰囲気づくりも大事なことなのだそうです。
また「住民の方々と沢山の話ができ、とても楽しかった」や「人生のアドバイスなど聴く事ができ、ためになった」など、人と人との繋がりや出会いの大切さを感じる声も多くありました。
そして「銀鏡に来ないと食べられないものに感動した」という感想もあり、井上さんは逆に言えばそれは銀鏡の住民はいつも食べているものであり住民にとっては当たり前だが、他所から来た人にとってはそれが当たり前ではなく魅力になるのだと話されました。

■発地型観光から地域主導型観光(行こうよ→おいでよ)
地域の自然、生活、文化を肌で感じ、地域の人々とのふれあいを求める体験・学習・交流型ツーリズムのニーズが高まっている昨今。
地域の生活者がつくる生活感のある地域主導型の観光や地域ぐるみの「おもてなし」、そして地域の住民も新しい発見や喜びを「おすそわけ」をすることが必要だということでした。
そういったなかで、で井上さんから銀鏡の足元にあるもの全てを博物館に見立てた屋根のない生活の博物館「銀鏡まるごとミュージアム」という提案が出されました。都市と農村との交流促進やコーディネーターの育成(行政からの自立)など様々な角度から銀鏡の活性化に繋がる展開が含まれており住民の方々の意識の向上も図られているのだと感じました。

■世界遺産登録活動へ
まず世界遺産に関する条約がどのような種類に分けられるのか、そして実際に登録された日本の世界遺産などを紹介していただきました。
無形文化遺産になっている岩手県の早池峰神楽を例に挙げ、なぜこの神楽が選ばれたのかは「室町時代に能が大成する以前の姿をうかがわせるなどの特色がある」などといった理由付けがしっかりとされているからだと話す井上さん。
また世界遺産登録には、何よりも住民の熱意と子どもから大人まで「銀鏡の神楽は凄いんだ」という意識を持つことが大切であり、そういった意識の中で活動をしていけば銀鏡の未来は明るいと話されました。
最後に「銀鏡の魅力を銀鏡に住む住民の方々がもう一回再認識していくことが大事なことなのではないか」と話され講座は終了しました。

質問タイムでは
「世界遺産になった場合、良い面もあるが悪い面も出てくると思うのですが、どういった事がでてくるのでしょうか?」という参加者からの質問に井上さんは
「人がたくさん来るようになる。そうした時にルールのない人がたくさん来ます。例えば「ゴミを捨てたらいけない」というルールを守れない人が出てくる。100人だったら捨てないけど1000人だったら捨ててしまう。その結果その場所が汚れてしまうというような事が出てきます。なのでしっかりとしたルール作りが必要になって来ると思います。」と答えられました。
参加者からは、
「観光は、地元の「人」が大事な事が分かりました。他人事では何も進まないこと。」
「時には、表面だけでなく、少し深く考えたり、見たりしなければ、と思いました。そして未来につないでいかなければいけない。」
「自分たちの村を見直すことができた。」
「銀鏡が好きだけど、銀鏡の好きな場所3ケ所が答えられなかったのがショックでした。銀鏡でしか食べられない物って何なのでしょうか?」
「地区の光になる所を掘り出し、地区外からの多くの人々に来てもらいたい。」
といったご意見・ご感想をいただきました。
今回の講座で、銀鏡という地域にはまだまだ人を呼び寄せる魅力がたくさんあるんだということに気づかされました。そして、改めて自分達の地域を見直すことや、自分達では当たり前と思っている食や文化など、それこそが他所の人から見た地域の魅力に繋がっているんだということも強く感じました。
井上さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!
2014年02月25日
『みやざきPVづくりインターンシップ』始まりました!
大学生が県内の地域を直接訪問し、自らが感じた地域の魅力をスマートフォンを使って動画撮影し、PV(プロモーションビデオ)という3分間の映像作品に創り上げる「みやざきPVづくりインターンシップ」がいよいよスタートしました!
まずは23・24日の2日間で撮影・インタビュー動画編集などの講座を実施しました。
1日目は、花堂純次監督による講座&ワークショップ。

花堂監督は、宮崎県立宮崎南高等学校卒業後、日本大学藝術学部映画学科へ進学。高校時代は、映画研究部の部長に1年生時で就任。大学在学中から助監督として活動し、テレビドラマ「愛の嵐」で監督デビュー。以降多くのテレビドラマの演出を手掛け、2001年「羊のうた」にて劇場映画デビューを果たされました。
花堂監督には映像づくりに関するノウハウや、地域に入ってのコミュニケーションの取り方、そして今回の訪問先の一つでもある西都市銀鏡の銀鏡神楽の映像(実際に監督が撮影された)を観ながら撮影技法の解説もしていただきました。
またこの講座には一般の方の参加募集もさせていただき、多くの方にご参加いただきました。
○アイデアの一つ目は捨てる
一つ目に思いつくことは大抵誰でも思いつくことなので、捨てる。
○最小限の説明(画)で見せる
映像の中に全ての情報を収めるのではなく、部分的に見せたり、自然や色の変化や被写体へのピントのあわせ方などで見せていく。
○時間
映像は時間芸術、時間を楽しませる。
○観客
皆に見せようとするのではなく、対象をしぼる。基本は自分と同じような人(同姓)がいい。自分と違う世代に見せる時は入念なリサーチが必要。
○コミュニケーションが大事
被写体やテーマに対して好奇心を持ち、相手の中に入って深く関わる。人に対しては先に自分をさらけだすことが重要。
そして『「感情力」が「感動」になる』という監督の言葉に、多大な好奇心と地域のことをもっと知ってもらいたいという思いが、人の心を動かす映像を作り出すことに繋がるのだと感じました。
講座後のワークショップでは、まず参加する学生同士で自己紹介や、頭や体を使い全員で協力して成功させるゲームを行いました。
そして、訪問する地域毎にチームに分かれて、どのような映像を作っていくのか、花堂監督を交えながらアイデア出しが行われました。
2日目は、児玉泰一郎アナウンサーによる「インタビューのコツ講座」と下出淳平さんによる映像編集の基礎講座でした。
まずはテレビ宮崎のアナウンサー児玉泰一郎さんによる講座。

児玉さんは、宮崎県宮崎市出身。小学生の頃からアナウンサーになることを志していました。そして宮崎大学在学中に地域づくりや商店街活性化の活動に携わり、イベントや祭りなどで司会を数多くこなされました。
卒業後、大分のテレビ局に入社しアナウンサー職と記者職に就くき、その後、テレビ宮崎に転職されました。

児玉アナウンサーには「インタビューのコツ講座」と題しまして、どうすれば地域やインタビューする相手の魅力を引き出せるのか、実際に児玉さんがインタビューされている映像を観てからお話いただきました。
また、インタビュー者やカメラの立ち位置により映像が変化していくことを、学生たちをインタビュー者やカメラマンに見立てて直接ご指導していただく場面もありました。
最後には、「自分が一番輝いていた瞬間」というテーマで実際に学生同士でインタビューをしてもらい、それをスマートフォンで撮影したものを全員で観ながら児玉さんにご指導をして頂きました。
・とにかく相手と仲良くなり会話をすること。
・リアクションを大きく。
・最低限の下調べはしておく
・原稿になるような情報は相手に言ってもらわなくていい。相手の気持ちを引き出すことが大切。
・インタビュー者やカメラの立ち位置によって緊張感がでたり、リラックスしたり、映像が変化する。
実際に学生達にインタビューをしてもらった時は緊張していた様子も見受けられましが、どのチームも共通して「笑顔」で臨んでおり、講座内で学んだことを押さえながら、取り組んでいました。
そして午後からはDIRスタジオの下出淳平さんによる講座。

下出さんは、鹿児島県志布志市出身。都城高専を卒業後、福岡の企業に就職。仕事の傍ら、経営の勉強を始め、子どもが出来たことを機に独自に映像の勉強を始めました。現在は結婚式や企業のPRを中心に記憶に残る映像制作を手がけられています。
下出さんには初めに撮影に関して、構図や照明の当て方などを実践してもらいながら解説していただきました。

講師の皆様、そしてキックオフ講座に参加していただいた皆様、ありがとうございました!
3月から実際に地域を訪問し、撮影を開始します。
訪問地域は、五ヶ瀬町・西都市銀鏡・日南市油津の3地域です。
不安な部分もあると思いますが、失敗を恐れず、今回の二日間の講座で学んだ事を活かし、また学生たち自身がチームの皆で話し合いを重ねて素晴らしいPVを作っていって貰いたいと思います!
そしてスタッフ一同、学生達を全力でサポートしていきます!!
まずは23・24日の2日間で撮影・インタビュー動画編集などの講座を実施しました。
1日目は、花堂純次監督による講座&ワークショップ。

花堂監督は、宮崎県立宮崎南高等学校卒業後、日本大学藝術学部映画学科へ進学。高校時代は、映画研究部の部長に1年生時で就任。大学在学中から助監督として活動し、テレビドラマ「愛の嵐」で監督デビュー。以降多くのテレビドラマの演出を手掛け、2001年「羊のうた」にて劇場映画デビューを果たされました。
花堂監督には映像づくりに関するノウハウや、地域に入ってのコミュニケーションの取り方、そして今回の訪問先の一つでもある西都市銀鏡の銀鏡神楽の映像(実際に監督が撮影された)を観ながら撮影技法の解説もしていただきました。
またこの講座には一般の方の参加募集もさせていただき、多くの方にご参加いただきました。
○アイデアの一つ目は捨てる
一つ目に思いつくことは大抵誰でも思いつくことなので、捨てる。
○最小限の説明(画)で見せる
映像の中に全ての情報を収めるのではなく、部分的に見せたり、自然や色の変化や被写体へのピントのあわせ方などで見せていく。
○時間
映像は時間芸術、時間を楽しませる。
○観客
皆に見せようとするのではなく、対象をしぼる。基本は自分と同じような人(同姓)がいい。自分と違う世代に見せる時は入念なリサーチが必要。
○コミュニケーションが大事
被写体やテーマに対して好奇心を持ち、相手の中に入って深く関わる。人に対しては先に自分をさらけだすことが重要。
そして『「感情力」が「感動」になる』という監督の言葉に、多大な好奇心と地域のことをもっと知ってもらいたいという思いが、人の心を動かす映像を作り出すことに繋がるのだと感じました。
講座後のワークショップでは、まず参加する学生同士で自己紹介や、頭や体を使い全員で協力して成功させるゲームを行いました。
そして、訪問する地域毎にチームに分かれて、どのような映像を作っていくのか、花堂監督を交えながらアイデア出しが行われました。
2日目は、児玉泰一郎アナウンサーによる「インタビューのコツ講座」と下出淳平さんによる映像編集の基礎講座でした。
まずはテレビ宮崎のアナウンサー児玉泰一郎さんによる講座。

児玉さんは、宮崎県宮崎市出身。小学生の頃からアナウンサーになることを志していました。そして宮崎大学在学中に地域づくりや商店街活性化の活動に携わり、イベントや祭りなどで司会を数多くこなされました。
卒業後、大分のテレビ局に入社しアナウンサー職と記者職に就くき、その後、テレビ宮崎に転職されました。

児玉アナウンサーには「インタビューのコツ講座」と題しまして、どうすれば地域やインタビューする相手の魅力を引き出せるのか、実際に児玉さんがインタビューされている映像を観てからお話いただきました。
また、インタビュー者やカメラの立ち位置により映像が変化していくことを、学生たちをインタビュー者やカメラマンに見立てて直接ご指導していただく場面もありました。
最後には、「自分が一番輝いていた瞬間」というテーマで実際に学生同士でインタビューをしてもらい、それをスマートフォンで撮影したものを全員で観ながら児玉さんにご指導をして頂きました。
・とにかく相手と仲良くなり会話をすること。
・リアクションを大きく。
・最低限の下調べはしておく
・原稿になるような情報は相手に言ってもらわなくていい。相手の気持ちを引き出すことが大切。
・インタビュー者やカメラの立ち位置によって緊張感がでたり、リラックスしたり、映像が変化する。
実際に学生達にインタビューをしてもらった時は緊張していた様子も見受けられましが、どのチームも共通して「笑顔」で臨んでおり、講座内で学んだことを押さえながら、取り組んでいました。
そして午後からはDIRスタジオの下出淳平さんによる講座。

下出さんは、鹿児島県志布志市出身。都城高専を卒業後、福岡の企業に就職。仕事の傍ら、経営の勉強を始め、子どもが出来たことを機に独自に映像の勉強を始めました。現在は結婚式や企業のPRを中心に記憶に残る映像制作を手がけられています。
下出さんには初めに撮影に関して、構図や照明の当て方などを実践してもらいながら解説していただきました。
構図を意識して撮るだけでも印象が変わったり、何気ない写真にも意味が加わり、照明は機材がなくても自然光を上手く利用したり、影の付け方で上手く撮れるなど、とても実践的なお話をしていただきました。
また機材を使わなくてもアイデア一つで本格的な映像が撮れる方法なども動画を見ながらお話していただきました。
また制作した動画をYouTube等の動画サイトやSNSを使ってPRする方法についてもお話いただきました。
検索して引っかかりやすくする為には「タイトル」が重要だと話す下出さん。
広く知ってもらう映像にするにはSEO対策などPR方法も重要なのだと感じました。
そして、実際に映像編集ソフト(vegas)を学生達に使ってもらいながら、基礎的な操作方法から効果の付け方、音や文字など様々な編集作業を行ないました。最終的には自分達で用意した写真や音楽を組み合わせながら映像編集を学んでもらいました。
全員、編集作業に入ってからは黙々と作業に没頭しており、とても集中して取り組んでいました。
最後に下出さんからかっこいいものから、感動するものまでオススメの動画をご紹介して頂きました。
また制作した動画をYouTube等の動画サイトやSNSを使ってPRする方法についてもお話いただきました。
検索して引っかかりやすくする為には「タイトル」が重要だと話す下出さん。
広く知ってもらう映像にするにはSEO対策などPR方法も重要なのだと感じました。
そして、実際に映像編集ソフト(vegas)を学生達に使ってもらいながら、基礎的な操作方法から効果の付け方、音や文字など様々な編集作業を行ないました。最終的には自分達で用意した写真や音楽を組み合わせながら映像編集を学んでもらいました。
全員、編集作業に入ってからは黙々と作業に没頭しており、とても集中して取り組んでいました。
最後に下出さんからかっこいいものから、感動するものまでオススメの動画をご紹介して頂きました。
技術的な面で優れていたり、ストレートに心に響くものなど今後映像を制作するにあたって、とても勉強になる動画ばかりでした。

講師の皆様、そしてキックオフ講座に参加していただいた皆様、ありがとうございました!
3月から実際に地域を訪問し、撮影を開始します。
訪問地域は、五ヶ瀬町・西都市銀鏡・日南市油津の3地域です。
不安な部分もあると思いますが、失敗を恐れず、今回の二日間の講座で学んだ事を活かし、また学生たち自身がチームの皆で話し合いを重ねて素晴らしいPVを作っていって貰いたいと思います!
そしてスタッフ一同、学生達を全力でサポートしていきます!!
2014年02月21日
『ヒムカレッジvol.9』開催しました!
2月18日(火)に、本年度最後となる「ヒムカレッジvol.9」を開催いたしました!
お足元の悪い中、県内外から22名の方にお越しいただきました!
まずはアイスブレイクで今回の講師高橋勝栄さんに因んで「延岡」というワードを起点に皆さんに連想ゲームをしていただきました。
皆さん最初の延岡からは想像も出来ないような言葉に繋がっていく人もいて、和やかなムードの中、今回のヒムカレッジは始まりました!

講師は延岡マリンサービスの高橋勝栄さん。

高橋勝栄さんは、30年以上無事故の実績を誇る『延岡マリンサービス』の店長。 県内外から訪れたダイバー達に延岡の海の魅力を120%満喫してもらうため、ダイビングスポットの開拓、延岡ならではの飲食店の情報提供、人との交流の場を創りだすなどの工夫で、毎年3000人以上が訪れる九州有数のダイビングスポットに育てあげました。
お足元の悪い中、県内外から22名の方にお越しいただきました!
まずはアイスブレイクで今回の講師高橋勝栄さんに因んで「延岡」というワードを起点に皆さんに連想ゲームをしていただきました。
皆さん最初の延岡からは想像も出来ないような言葉に繋がっていく人もいて、和やかなムードの中、今回のヒムカレッジは始まりました!

講師は延岡マリンサービスの高橋勝栄さん。

高橋勝栄さんは、30年以上無事故の実績を誇る『延岡マリンサービス』の店長。 県内外から訪れたダイバー達に延岡の海の魅力を120%満喫してもらうため、ダイビングスポットの開拓、延岡ならではの飲食店の情報提供、人との交流の場を創りだすなどの工夫で、毎年3000人以上が訪れる九州有数のダイビングスポットに育てあげました。
NPO法人ひむか感動体験ワールド の代表としても宮崎県北部地域の活性化や発展を目的とした、自然環境の保護活動、人材を活用した体験活動、観光関連事業も展開されています。

「ネットワークを活かした延岡ならではの最高のおもてなし!」というテーマで、アウトドア天国・延岡の魅力を様々な活動を通してお話いただきました。
・延岡ならではでおもてなし
延岡マリンサービスは創業37年で県内唯一の5スターIDダイブリゾートとして経営されています。

そして、延岡が発祥の地とされる「チキン南蛮」を始めとしたご当地グルメ、東九州と中九州の周遊ルートの活用、プロ野球のキャンプや神楽などの四季折々の周辺イベントの利用等も、新たなネットワークを生み延岡に人を呼び寄せることに繋がっています。


また、(社)延岡観光協会・常務理事や延岡観光大使としても活躍されています。

「ネットワークを活かした延岡ならではの最高のおもてなし!」というテーマで、アウトドア天国・延岡の魅力を様々な活動を通してお話いただきました。
・延岡ならではでおもてなし
延岡マリンサービスは創業37年で県内唯一の5スターIDダイブリゾートとして経営されています。
また勝栄さんはダイビングのインストラクターを育てることの出来るPADIコースディレクターの資格を持っており、これもまた県内唯一だそうです。
「おもてなしはほどこし」
ほどを超えるほど人に良く思われたい、気に入ってもらう為に相手のことを思ってやる、それこそが最高のおもてなしだと勝栄さんは話されました。

黒潮と反流の豊かな恵みを受けて生息する魚や、日本一のオオスリバチサンゴ大群生を始めとする100種類以上のサンゴや希少種であるカエルアンコウなどが生息している延岡の海。
沖縄などに比べるとネームバリューが弱く、「延岡って潜れるの?」という人が未だに多いそうですが、だからこそ沖縄や海外とは違う延岡ならではの南国情緒溢れる魅力を最大限に活かして、今現在年間3000名のダイバーを延岡に呼び込んでいます。
そして、延岡が発祥の地とされる「チキン南蛮」を始めとしたご当地グルメ、東九州と中九州の周遊ルートの活用、プロ野球のキャンプや神楽などの四季折々の周辺イベントの利用等も、新たなネットワークを生み延岡に人を呼び寄せることに繋がっています。
リピーター率60%以上、宿泊率20%以上を誇る「延岡ダイビング観光バックツアー」でも、来てくれたお客さんの心を離さない最高のおもてなしで迎えることがその結果にもつながっているのだと感じました。
また、宮崎県地域づくりネットワーク協議会が開いた延岡での研修交流会の実行委員長を経験したことで、市・県など周りの地域づくりの方々と繋がり、今日までの活動を支えてきたネットワークの形成にも繋がったのだと話されました。

・ひむか感動体験ワールド
冒険家の椎名誠氏に「アウトドア派にはたまらない、とても素晴らしい場所!」「オンリーワンの観光地」と言ってもらった後押しもあり、宮崎県北部地域の活性化や発展を目的とした「NPO法人ひむか感動体験ワールド」を立上げた勝栄さん。
山・川・海それぞれの達人がおり、延岡の大自然を体感できることができます。漁業体験や手軽に出来るフットパス、パワースポットなどのメニューも用意されております。
またコンシェルジュとして各エリアの宿泊・飲食・お土産なども紹介できるシステムにもなっており、ここでもお客さんの心を離さない行き届いたおもてなしが発揮されています。
また子どもや修学旅行生などの団体向けのプログラムも備えており、幅広い年代層にも対応出来る仕組みにもなっています。この体験活動が子どもたちの「生きる力」「想像力」「成功体験」「地域愛」などを育てることに繋がると話す勝栄さん。
教育の観点からもひむか感動体験ワールドの活動が活かされていることを感じました。
近年、世界各地で起こる大災害に対して、ひむか感動体験ワールドの達人達のようなアウトドア派の力が見直され、指導者として様々な活動を始め、その力を多大に発揮しているということにも言及されました。

・新たなネットワーク
昨年の3月に延岡で開催されたTOKYO GIRLS COLECTIONを支えたのは延岡の新たなネットワークとして活躍している「延岡サポートネットワーク」です。
2月14日~16日に初開催となった延岡花物語「このはなウォーク」には3万5千人を集め、ボランティアにも1000人の方が集まるなど、その強力なネットワークの力を表しています。
・延岡が持つ今後の可能性
東九州自動車道 延岡~宮崎間が3月16日に開通することにより、これまで南から繋がることの多かった宮崎に延岡を始めとする北からの繋がりが増え今後延岡が更に活性化していくと話す勝栄さん。
高速道路の開通に伴った「延岡ハブ計画」では、
・一時間圏内で最高の観光地が揃う
・宮崎県が北の玄関口として要になる
・市街地から各アウトドアフィールドへは車で20~60分
・延岡ハワイ化計画の推進
など、新たな延岡の発展に繋がる利点や展望をお話いただきました。
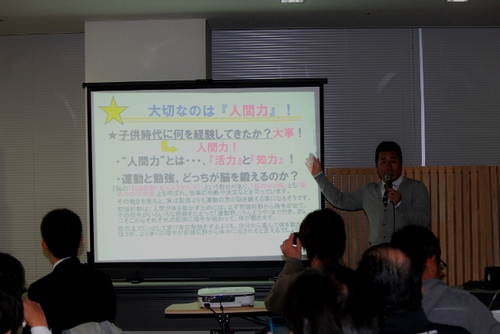
講座の中でも「大切なのは人間力」と話された勝栄さん。
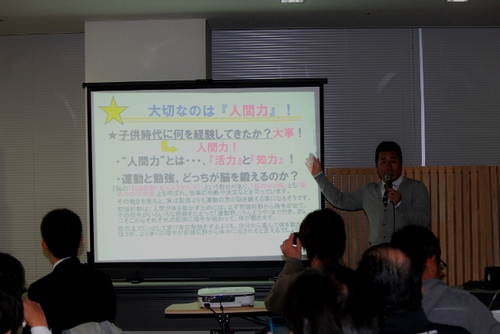
講座の中でも「大切なのは人間力」と話された勝栄さん。
まさに勝栄さん自身が人間力に溢れた方であり、だからこそ人を惹きつけ、大きなネットワークの形成と延岡に多くの人が訪れる原動力にもなっているのだと感じました。

ワークショップでは講座内でも出てきた、

ワークショップでは講座内でも出てきた、
「東九州自動車道 延岡~宮崎間が3月16日に開通!高速道路の開通を活かした観光客誘致のアイデアを考えてみよう」をテーマに、それぞれのグループで探求していただき、代表の方に発表して頂きました。

参加者の皆さんからは、
「やはり仕組み作りが大切だと感じました。(お客さんが自ら宣伝をしてくれる等)。それには地域内の連携が不可欠ですね。」
「北から客を下ろすという見方には目からうろこでした。また、県北の漁業についての話など、今までの自分の中の「?」がすーっとつながっていきました。」
「延岡の魅力がよく分かり、1度しか行ったことが無いので、またゆっくり行こうと思う。」
「アウトドアだけでなく、教育という観点も含まれていて、全てがつながっている感じでした。勝栄さんやっぱりすごいです。」
といったご意見・ご感想をいただきました。
勝栄さんの熱く、そして密度の濃い講演と、ご参加頂いた皆様のおかげで、本年度最後を締めくくるにふさわしい今回のヒムカレッジになったと感じました。
facebookページでも随時情報が発信されています。是非ともご覧下さい!!
【延岡マリンサービス】 https://www.facebook.com/NobeokaMarine
【ひむか感動体験ワールド】 https://www.facebook.com/nobestaworld
勝栄さん、そして参加していただいた皆様、ありがとうございました!

参加者の皆さんからは、
「やはり仕組み作りが大切だと感じました。(お客さんが自ら宣伝をしてくれる等)。それには地域内の連携が不可欠ですね。」
「北から客を下ろすという見方には目からうろこでした。また、県北の漁業についての話など、今までの自分の中の「?」がすーっとつながっていきました。」
「延岡の魅力がよく分かり、1度しか行ったことが無いので、またゆっくり行こうと思う。」
「アウトドアだけでなく、教育という観点も含まれていて、全てがつながっている感じでした。勝栄さんやっぱりすごいです。」
といったご意見・ご感想をいただきました。
勝栄さんの熱く、そして密度の濃い講演と、ご参加頂いた皆様のおかげで、本年度最後を締めくくるにふさわしい今回のヒムカレッジになったと感じました。
facebookページでも随時情報が発信されています。是非ともご覧下さい!!
【延岡マリンサービス】 https://www.facebook.com/NobeokaMarine
【ひむか感動体験ワールド】 https://www.facebook.com/nobestaworld
勝栄さん、そして参加していただいた皆様、ありがとうございました!






